-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
2010年、フランスのパロット社が発売した「ARドローン」がきっかけとなり、だれでも、どこでも手軽に飛ばせる無人航空機=ドローンは世界中に広まった。一方で、飛躍的な発展と急速な普及に法整備が追いつかず、安全性の確保が大きな課題となっているのも事実である。「空の産業革命」の健全な育成には何が必要なのか。長らく航空機の研究に携わるとともに、日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の理事長として、新産業、新市場の創出をリードする鈴木真二氏に伺った。
“雄バチ”の由来は、第二次大戦中のアメリカの軍用機
――無人航空機の研究はいつから取り組まれたのですか。
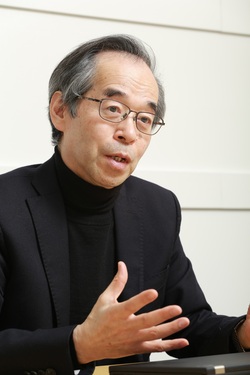
本格的にスタートさせたのは2005年です。愛知万博でロボットの特別展示があり、その一つに、飛行ロボットが採択されたのが最初です。当時は模型飛行機にコンピューターを搭載して、自動で飛ばすようなものをつくっていました。研究開発の背景には、2000年代に入り、携帯電話などでも使用されているリチウムポリマー電池の軽量化・大容量化が進んだことがあります。
飛行ロボットは、自動飛行を行うためにGPSを搭載しています。あらかじめ決められた場所を正確に飛ぶことができるので、空撮などに適していると考えました。有人の飛行機をチャーターするよりも低コストですし、低い高度から撮影することができます。実際に災害現場や海岸線の調査、植物の生育状況を定期的にモニタリングするために、飛行ロボットを使いました。
もう一つ、私は「落ちない飛行機」の研究も行っています。落ちない飛行機とは、飛行中に機体が壊れても、人工知能などのコンピューターが自動制御するものですが、人が乗った飛行機で実際に事故を起こして実験を行うことはできないので、これに無人航空機を使っています。
最近では、医師のグループと連携してAEDの空輸実験や、企業らと共同でマルチコプターの室内自律飛行の研究も行っています。通常、室内などでマルチコプターを自動で飛ばすには、特殊な装置が必要でしたが、機体に搭載したカメラで自分(マルチコプター)がどこを飛んでいるのか把握し、自律飛行できるような仕組みを開発ました。
――あらためて、ドローンについて伺います。どのような種類、特徴があるのですか。
遠隔操作によって無人で飛ぶ航空機を指します。固定翼を持った飛行機タイプ、ヘリコプター、マルチコプター、サイズも大型から中型、小型までいろんな種類があります。そもそもドローンというのは雄バチのことですが、第二次大戦中のアメリカでつくられたターゲットドローンがその由来です。日本ではマルチコプターをドローンと呼ぶ風潮がありますが、海外では無人航空機自体をドローンといいます。
ターゲットドローンは遠隔操作で飛ばしながら、撃ち落とす標的として使われていました。その後、さまざまな研究開発がなされたのですが、実用化は進みませんでした。一方、独自の進化を遂げたのが模型飛行機をベースとした偵察機と、農薬散布を行うラジコンのヘリコプターです。日本は土地が狭いので、本物の飛行機やヘリコプターを使って農薬をまくのは効率が悪く、危険です。そこで、1980年代に国家プロジェクトとして農薬散布ヘリの開発がなされました。実は、非軍事目的で無人航空機が最も活用されていたのは日本でした。




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)





