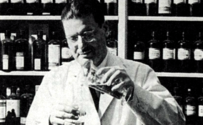-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
バリューベース・プライシングとは、「差別化された機能の価値」を基に値付けをする手法だ。その最も基本的な考え方と、避けるべき誤解を説明する。
私は15年以上にわたり、価格戦略に関して企業への支援およびMBA受講生への指導をするなかで、気づいたことがある。バリューベース・プライシング(value-based pricing:価値に基づく価格設定)は、非常に頻繁に議論される概念であると同時に、最も誤解されてもいるということだ。
バリューベース・プライシングは、他のどの価格設定論よりもマーケターを――そして価格設定の専門家の多くですらも――混乱させている。さらに、誤解のせいで企業はその活用を敬遠することも多い。その代わりに、コストベースやそれ以外の価格設定法で満足し、十分な儲けを手にできていないのだ。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)