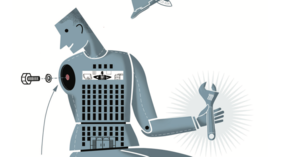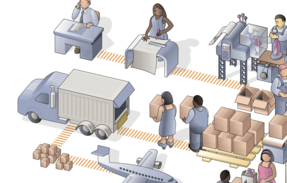-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
経営会議でも「悪貨は良貨を駆逐する」
コナー・コーポレーション(仮名)は、IPO(株式公開)したものの、ほどなく迷走し始めた。経営陣はこれまでと同じく、月次の経営会議を一日かけて開いていたが、その焦点は定まっていなかった。
経営会議では、午前中に業務上の問題を話し合い、午後は戦略上の問題について検討することになっていた。しかし、四半期目標の達成というプレッシャーから、議事次第では戦略について話し合うはずが、業務上の問題に戻っていった。
月次の実績と四半期の業績予想によれば、売上目標の未達、支出の超過は間違いなかった。業績不振を懸念した経営陣は、価格の見直し、生産の縮小、間接部門の人員削減、販促計画など、目標と実績のギャップを埋める方法について何時間もかけて話し合った。
ある役員は、「我々に、戦略を検討している時間などありません。この四半期の目標が未達に終わったら、明日はないかもしれないのです。我々にとって、長期とは短期のことなのです」と述べた。
コナー同様、大手上場企業も含め、多くの企業は、経営会議にも「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則が当てはまることを知っている。すなわち、業務の悪化を話し合うと、戦略をよく実行するための話し合いが脇に置かれるのはしかたがないと──。
この罠に陥ってしまうと、早晩業績はおぼつかなくなり、四半期目標を何とか達成することに汲々とする。そのような状況では、成長の機会を生み出すためにどのように戦略を修正すべきか、一時的に資金不足に陥るパターンからどのように抜け出すかについて話し合われることはない。やがて、証券アナリスト、投資家、取締役会は、経営陣の想像力と真剣さを疑い始める。
ところが、我々の経験によれば、業績不振の原因は、経営陣の無能や努力不足にあるのではなく、マネジメント・システムの機能不全にある。マネジメント・システムとは、企業が戦略を立案し、それを一連の業務活動に落とし込み、戦略と業務の改善度をモニターするためのプロセスとツール全般のことである。
戦略と業務がちぐはぐだと、広範にわたって累が及ぶ。この25年間になされたさまざまな調査によれば、新しい戦略を立案したものの、思いどおりの成功を実現できなかった企業が6~8割を占めるという。