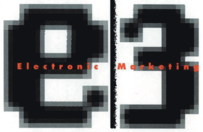戦略コンサルタント、クリスチャン・マズビャーグによるSensemaking(未訳)は、モーソンとシャピロの本の続きから、前述のハートリーの本へとつながっていく内容だ。彼の主張によると、データセットに表現されている人間を理解するための努力を必死に行わない限り、企業は事業を展開する市場とのつながりを失うおそれがある。そして、企業に必要な深い文化的知識は、数字中心の市場調査などではなく、人文科学中心の文章、言語、人間の研究によってもたらされる、と彼は言う。
マズビャーグは、フォードの高級車ブランド、リンカーンを例に挙げる。
リンカーンはわずか数年前までBMWとメルセデスに大きく後れを取り、フォード社内ではブランド廃止まで検討された。競争力の回復には米国以外、特に次の大きな高級車市場である中国で販売台数を伸ばすしかないと経営陣は判断していた。
そこで、世界中の購入者が車という商品を(運転するだけでなく)どのように体験しているかを入念に調べることにした。リンカーンの営業マンたちは1年間をかけて、顧客の日常生活や「高級(ラグジャリー)」の意味合いについて顧客と話し合った。そして、多くの国で移動はドライバーの最優先条件ではないことに気づいた。むしろ車は、取引先の人をもてなす社交の空間として使われていたのである。リンカーンは、性能は十分だったが、顧客の人間的側面に対処するためのコンセプトを改める必要があった。
その後のデザインへの取り組みは報われる。2016年、中国国内での売上げが3倍に跳ね上がったのだ。
以上3冊の本に共通するのは、専門分野の選択よりも、思考の幅を広げる方法を見出すほうが、ずっと重要だという理念である。この考えは別の新刊書籍でも強調されている。経営学教授ランダル・ストロスのA Practical Education(未訳)と、ジャーナリスト、ジョージ・アンダースのYou Can Do Anything(未訳)である。
STEM系の学生も人間に配慮することができ、同様に、英語学専攻の学生も科学的に物事を探求することができる(大学でコンピュータ科学を学び始めた私自身も、そうだ)。学問分野間のライバル意識に煽られて、自分の専門分野にだけ固執しないよう心掛けなければならない。「カナヅチしか持っていないと、すべてのものがクギに見える」ということわざにもある通り、あらゆる問題に常に同じアプローチで立ち向かっていたら、自分にとって、そして世界にとって、どれほどの損失を生むかわからない。
HBR.ORG原文 Liberal Arts in the Data Age, HBR, July-August, 2017.
■こちらの記事もおすすめします
これまでよりずっと多くの本を読む8つの方法
共感こそイノベーションの原動力である
JM. オレジャーズ (JM Olejarz)
『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌のアシスタントエディター。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)