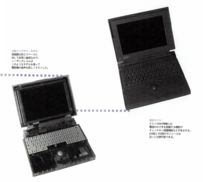知識も学び方も、アップデートし続ける
例えば本書では、心理学を専攻する学生たちの事例が取り上げられている。現在、データ分析が強力なツールであることに疑問の余地はなく、多くの分野で統計の基礎を理解しておくことが不可欠だ。心理学専攻の学生たちも、研究論文の発表にはデータ分析が必要で、統計学の知識が欠かせない。けれども、学生たちは統計学に対して苦手意識を持っていたり、つまらないと感じていたりした。
そこで、教授が自分の生活で統計学を使うシーンを想像させ、それを短いエッセイにまとめさせたという。すると、学生たちは統計学が自分の将来の職業、趣味などにとって大事であることを意識し、学習意欲が大幅に高まり、成績が向上するという効果が現れた。
当たり前のように思えるかもしれないが、受け身では学習成果は上がらず、自ら学ぶ意義を見つけるだけで、成果は変わってくる(「こんな勉強、役に立たないじゃん」と思っていた科目が、軒並み成績が悪い…という記憶を持っていると、なおさら納得感が増す)。
仕事においては、いつも好きなものだけ学べば良いという訳ではない。そういった場合にも、自分で学ぶ価値や自分との関連性を見いだすことが、まずは重要になるのだ。
冒頭で述べた蛍光ペンを使う方法は、その効果を裏付ける研究はごく限られているという。また、繰り返し読むという方法は、学習アプローチとしては効果がないそうだ。いずれも機械的にマーカーを引いたり、目を通すだけになりがちで、能動的に関わっていないことが、その理由だ。
私たちを取り巻く環境の変化は早くなり、「学び続けること」はビジネスパーソンの必須条件になっている。そして、簡単に情報が得られる現代において、知識は単に情報を記憶するだけではなく、本質的に理解して、獲得しなければ意味を持たなくなっている。
このような状況だからこそ、過去のやり方を踏襲せずに、まずは学び方そのものを、アップデートしたい。学び続けることに価値を見いだし、よりベストな方法で知識を習得していく方法を、いま改めて身に付けたいものである。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)