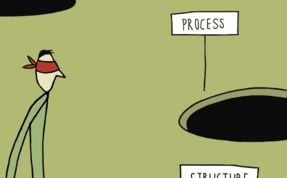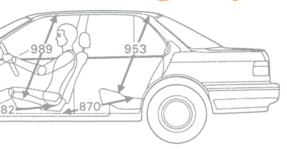-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
製造アウトソーシングは「諸刃の剣」
PC産業の生みの親といえば、事実上IBMである。しかし、PCからIBMのロゴが消え、PCメーカーの聯想集団(レノボ・グループ)との合弁事業のみを残して、IBMがPC業界から完全撤退する日はそう遠くない。
1984年に中国で創業された聯想は、もともとIBMをはじめ、各社PCの中国国内向け卸売業者だった。その聯想のロゴがついたPCが登場するのは、同社にすれば間違いなく長足の進歩といえよう。
同じく、IBMブランドのPCをOEM生産していたアメリカのサンミナSCIも、同様の進歩を遂げてきた。聯想同様、同社もIBMのPC工場をいくつか買収し、各種有名ブランドの製品を組み立てている。いまでは同社の業容は拡大し、特注の電子部品の設計や製造も請け負っている。
OEM生産を請け負う無名メーカーから成り上がり、委託企業のブランドを押しのけるまでに成長した企業は増えており、ここで挙げた2社はその代表例である。
さらに言えば、一般的には、受託製造業者(完成品メーカーから、部品調達や製品の組み立てを請け負う契約メーカー)へのアウトソーシングは、利益率の低下に悩む大手ブランド企業にとっての窮余の策と考えられてきた。しかし、IBMのケースは複雑で、こうした単純な見方に疑問を投げかけることになった。
たしかに、完成品メーカーが製品の組み立てをすべてアウトソーシングすれば、人件費の削減や資本の有効利用、労働生産性の向上につながる。その結果、完成品メーカーは製品の価値を最大化する活動、すなわちR&D、設計、マーケティングなどに集中できる。
一方、受託製造業者は低賃金な国や地域に立地し、規模の経済、優れた製造能力など、独自の強みを生かして、完成品メーカーのメリットに一役買っている。
さまざまな完成品メーカー向け製品の生産プロセスや開発プロセスに携わるという経験も、彼らの強みの一つだ。受託製造業者が他のクライアントに製品の改善を提案できるのも、このような経験があればこそである。
しかし、IBMなどの企業がこれまでに学んできた教訓からすれば、製造アウトソーシングは「諸刃の剣」でもある。一つには、受託製造業者は完成品メーカーの知的財産を知りうる立場にあり、それを不正に活用したり、他の顧客企業にそれを漏らしたりするおそれがある。
また、えてして新興の受託製造業者は野心的であり、完成品メーカーに提供しているその強みを武器に、利己的に振る舞うことも考えられる。さらには、完成品メーカーとの取引経験を生かし、自社ブランドを立ち上げ、完成品メーカーの取引先である小売業者や卸売業者と独自に関係を構築しようとするかもしれない。
このような事態にあっては、完成品メーカーにすれば、業務受託先のリスクが高まるだけでなく、これまで下請けと見なしていた相手がいつの間にか新たなライバルとして眼前に立ちはだかるかもしれないのだ。