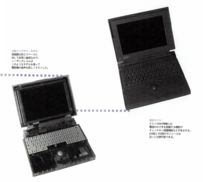線形ではなくループ図で
動的な社会システムを捉える
システム思考と他のアプローチとの大きな違いは、「ループ図」を用いることにある。
通常、たとえば何かの戦略を立てようとすれば、Aという課題を考え→Bという解決策を実行すれば→Cという成果を導く、というように考えがちである。時間軸でいえば左から右に、つまり「線形」に捉えてしまう。
これを従来のロジックモデルで示せば、「投入(インプット)→活動(アクティビティ)→産出(アウトプット)→成果(アウトカム)」というフレームワークが当てはまるだろう。
しかし、ループ図の考え方は違う。先の例でいえば、Bを実行したことで、思わぬDというマイナス要因を生み出していないのか。また、Cという成果が出たことでAという課題に時間差で影響を与えていないのかについても、検討することになる。相互に与える影響や時間軸をも考慮にするため、より現場の実態に近づくのだ。
なぜ、このような考え方が必要なのか。本書は、実社会では次のような事柄が現実に起きているからだと挙げる。
・ホームレス保護施設があるために、ホームレスがなくならない
・犯罪取り締まりを強化し、厳罰を与えても、凶悪犯罪への恐れが減らない
・職業訓練プログラムが失業率悪化を起こす
一見、適切とみられる社会の課題解決策が達成すべき目的を阻害しているというのだ。その際に役に立つのが、この思考法なのである。
とはいえ、そういわれてもピンと来ないだろう。そこで、本書はループ図について5つの「型」を示す(「システム原型」と呼び、本来は10種ある)。これを解釈すると、次のようなパターンを示すことができる。
1)短期的には機能しても意図せざる悪い結果を招くパターン
2)応急処置に頼るあまり、根本的な解決から遠のくパターン
3)一時は勢いがあってもその成長が限界を迎えてしまうパターン
4)ある分野で強い者にリソースが集中し、さらに強い者になる循環パターン
5)本来、協力関係にある者同士が意図せずに敵対するパターン
なるほど、これらは社会の身近な出来事において、よくある話である。1)については、たとえば、企業の業績が悪いからといってリストラを実施すると有能な人材から流出し、後に企業の悪化の原因となることが当てはまる。2)については、日本銀行の金融緩和政策が当てはまるだろう。5)は官僚と政治家の関係がそうであろう。
1)から5)は、単なる一つのパターンではあるものの、このようなパターンが複雑に絡み合ったのが実際の社会である。社会課題とは、こうした型がいくつも組み合わさって、しかも”時差”があることに解決の難しさがある。
本書は、こうした構造を浮き彫りにすることを説くとともに、「構造のツボ(レバレッジ・ポイント)」を見つけるように促す。つまり、どこに投資をすれば、最もリターンを生み出すのかを考えなければならない。そのためにも、数字で表せる指標を検討しなければならない。
たとえば、ホームレスをなくすためにどうするのか。その問いに対して、本書は「恒久住居に移り住んだ路上生活者数/月)-(路上生活者になった人の数/月)」という指標を掲げる。これにより、月次のホームレス実減少数に注目し、「全体としての有効性」を測ることが可能になるのだ。
このように、システム思考は、動的に変化する社会システムを捉えるのに優れた思考法である。多様なプレイヤーを動かす上で必要なメソッドであり、これまでの静的なロジックメソッドとは一線を画すものだ。いつまでたっても解決していない身近な課題を考えるときにも、きっと役に立つことだろう。
なお、日本版は、井上英之・慶應義塾大学特別招聘准教授による「日本語版まえがき」(全文が公開されている)と小田理一郎氏による「監訳者による解説」が計約50ページあり、充実している。コレクティブ・インパクトの意味やシステム思考を扱う上での躓きやすい点がわかるのも魅力的である。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)