-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
空前の日本企業による海外M&Aブームが続いているが、前編で記したように、成功のハードルはなかなか高い。しかしそんな中で、実績を積んでいる日本企業もある。ベインのプロジェクト経験、今回の調査で行ったケーススタディ、そして成功企業の経営者のインタビューなどを踏まえて、4つの「成功の道」を提案する。

ベイン・アンド・カンパニーのパートナー。京都大学経済学部卒業、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学修士課程(MBA)修了。東海旅客鉄道株式会社(JR東海)を経て、ベインに参画。テクノロジー、産業財・自動車、消費財、流通等の業界において、M&Aや企業統合、構造改革などを中心に、幅広い分野のプロジェクトを手がけている。ベイン東京オフィスにおけるM&Aプラクティスのリーダーであり、2014年より東京オフィス代表。
前回述べたように、日本企業を海外M&Aに向ける環境要因・要請に変化がない以上、「あつものに懲りてなますを吹く」ように海外M&Aを敬遠することは、問題の解決にはなりにくい。では、どうすればよいのか。
我々は日本を含む世界の大型M&Aの支援(M&A戦略、デューデリジェンス、PMIなどを含む)では多大な実績を積んでいる。そのプロジェクト経験と、今回の調査で行ったケーススタディ、さらには海外M&Aで実績を上げている日本企業の経営者の方々へのインタビューなどを踏まえ、4つの「成功への道」を提案したい。
(1)戦略目的の明確化
1つ目は、海外M&Aの前提となる戦略的目的の明確化である。例えば、国内市場の飽和を受けて、成長のために勝ち組グローバルブランドと海外販路を獲得することが必要、との明確なビジョンのもと、主に欧州やオセアニアでM&Aを積み重ねるサントリー食品インターナショナルやアサヒグループホールディングスはその好例であろう。
飲料に限らず、日本の消費財メーカーの大きな弱点の1つは、グローバルブランドの不足である。日本国内では圧倒的知名度を誇るブランドでも、世界中で名の知れたものは少ない。そうした中でサントリーやアサヒは、既に確立したグローバルブランドの買収に、海外M&Aを積極的に活用している。
その一方で、ブランドのない製造や販売だけの会社や、ブランドの確立が浅い新興国のプレーヤーには、両社はほとんど手を出しておらず、ブランドのコントロールのために経営権の取得にもこだわっている。
ある消費財メーカーのCFOは、「M&Aの究極的な目的はブランドと人材の獲得」とまで言い切っているが、そうした「何のために買うのか」「何を買うのか」の極めてシンプルで言い訳のきかない明文化と経営陣の間での意思統一は、海外M&A成功の第一要件といえよう。
逆に言えば、戦略的裏付けの希薄な「将来への布石」「ここで買わないと後悔する」的論法は、できるだけ避けられなければならない。
(2)能動的かつ自律的なディールの遂行
2つ目は、能動的かつ自律的なディールの遂行である。案件のスクリーニング、デューデリジェンス、交渉、それぞれにおいて「定石」が存在する。
各プロセスにどの程度時間をかけるべきなのか、どこでどういった外部専門家を活用すべきなのか、事業部門をどこでどこまで巻き込むべきなのか、デューデリジェンスで何を徹底的にみるべきなのか、交渉の撤退ラインをどこに設けるべきなのか、などなど、これらの「定石」を理解することは、「大成功」の確率を上げることにはならずとも、失敗のリスクは確実に低減してくれる。
プロセス以外にも、例えば前述の消費財メーカーCFOは、「スタンドアローン(買収先企業単体)で採算の取れる価格設定が大前提」と強調する。特にスコープディールの場合は、確実に見込めるシナジーも多くないので、スタンドアローンの企業価値で価格設定することは、極めて重要な成功法則である。
加えて、「誰がやるか」もディールの自律性をもたらす重要なポイントであろう。案件探索も、投資銀行等からの持ち込みを待つだけでなく、自ら能動的にターゲットのロングリストを構築して積極的にアプローチすることが重要である。
「誰がやるか」という点では、リクルートホールディングス取締役専務執行役員の池内省五氏は「海外企業のM&Aでは、計画、交渉、買収後のPMIと経営を同じ人がやり切ることが、当社の定石」と言い切る。そうすることで、無謀な価格設定に自制が働き、また買収時からその後の経営を考えた仕込みがなされるのである。実際に同社は、これまでに米インディード社を含む20件以上の海外M&Aを成功させている。
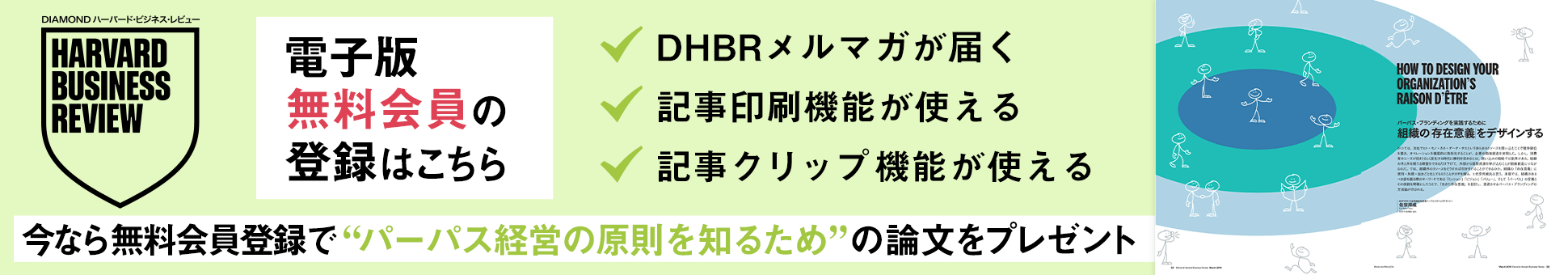




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









