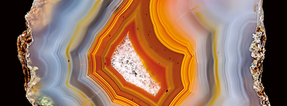-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
サイエンティストに
なぜいま注目するのか
山形県鶴岡市にある慶應義塾大学先端生命科学研究所。その所長を務める冨田勝教授は、この20年間に、多数の有名雑誌に論文を発表するだけでなく、メタボローム解析技術[注1]を持つヒューマン・メタボローム・テクノロジーズを共同創業し、上場を果たした。さらに、優秀な学生を育てて送り出し、人工クモ糸を合成し新たな素材を製造するSpiber(スパイバー)など6社のベンチャー企業の創業にも携わってきた。
なぜ、冨田教授は長期にわたり多くのイノベーションを起こすことができたのだろうか。冨田教授は、学生が自由に研究することを「放牧モデル」と名付け、学生からの自由な発想や奇抜のアイデアが創出されることを推奨してきた。本人が面白いと感じてワクワクするようなテーマを見つけることを奨励し、誰でも思い付きそうなアイデアは「普通のアイデア」と呼び、「普通とは0点だから、やる価値はない」と明言してきた。
学生起業したスパイバー創業者の関山和秀氏が幾度となく挫折しそうになっても、冨田教授は「気の済むまでやったらよい」と励ました。いまでは企業価値が1000億円規模の国内有数のスタートアップとなったが、この裏には指導者である冨田教授が失敗を奨励し、その評価がグループのコンセンサスになっていたことが大きい。