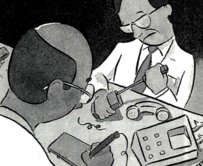-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
デジタル化の進展がビジネスの前提を大きく変えている。既存の競争優位が次々に無効化される中、いわゆる「ディスプラター」の猛攻を受けて苦戦する大企業は多い。変革の時代に大企業が生き残っていくためには、どんな戦略が必要だろうか。日本を代表するシステムインテグレーターとして数多くの大企業のデジタルプロジェクトをサポートしてきたNTTデータの山口重樹氏が、その解として提案するのが「顧客価値リ・インベンション戦略」だ。大企業の「信頼」という強みにデジタルの力を掛け合わせることで新たな価値を生み出そうという戦略が生まれた背景とその狙いを聞いた。
デジタル時代こそ高まる「信頼」の価値
──著書『信頼とデジタル』では、デジタル時代の新たな戦略として「顧客価値リ・インベンション戦略」を提案されています。

「顧客価値リ・イベンション戦略」は、既存の市場で実績を重ねてきた日本の大企業が、今取り組むべきDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略として、本書で初めて体系化したものです。
GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)やBATH(バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ)の事例を紹介した書籍などは多いのですが、デジタルが経済に及ぼす影響や既存企業が取るべき戦略を論理的に説明したものはあまり見当たりません。
実際にお客さまのデジタルプロジェクトに携わっている経験と経営者としてのロジックをベースに、既存の市場で実績を重ねてきた企業が今取り組むべき戦略は何かを考えてみたいと思いました。
デジタルというと、AI/ビッグデータ、IoTなどの技術を活用し、部分的な業務改革や効率化を行うことと思っている方が多いのですが、デジタルは顧客に提供する価値そのものを「リ・インベンション(再発明/再創造)」する力を秘めています。経営戦略の基本である「誰に、何を、どのように提供するか」まで立ち返って、デジタル戦略を考えることが必要だと考えました。
これはまさに共著者である神戸大学大学院の三品和広教授が提唱されている「事業立地戦略」です。
背景には企業が持続的な成長を目指すためには、既存の枠組みの中で製品やサービスをただ改良・改善するのではなく、「誰に、何を、どのように提供するか」という事業の構えそのものを問い直し、再創造すべき、という考え方が込められています。そして、私自身がIT実務に携わる中で「デジタル時代の今こそ、日本の大企業はリ・インベンションに取り組むべきではないか」との思いを強く持つようになったことから、この戦略が生まれたのです。
背景には、SIer(システムインテグレーター)としての私たちの仕事の変化があります。かつては顧客企業が示す要件をシステム化し運用することが業務の大半でしたが、ここ4〜5年でサービス領域がその前後に大きく広がり、デジタルを経営に生かすための戦略の策定から、成果をいかに出すかという結果まで求められるようになりました。そして、成功するDXにおいては、デジタルの使いこなし方の巧拙よりも、組織としてどれだけ明確な目標を持ち、経営本来の課題を掘り下げるかが大切であることを実感したのです。
本戦略において最も重要な点は、まだ満たされていない「顧客の真の課題」に着目し、顧客起点で、提供価値を根本的に見直すことです。そして相互の信頼関係に基づいて、デジタルを活用して顧客から継続的に学び続け、顧客の活動を引き受けながら提供価値を上げ続けていくことを提案しています。
──「信頼」が大きなキーワードになっているのはなぜでしょう。
日本の大企業はデジタル化に出遅れている、という指摘をよく耳にします。確かに一面においてそれは事実です。しかし私は、本当の勝負はこれからだと考えています。巨大プラットフォーマーがデジタル市場を席巻したといっても、その主戦場は、もともとデジタル技術と相性の良いコンテンツを中心とした一部の世界です。現実の生活や産業を根底から支える社会システムにデジタルを融合させていく「デジタル化の第2フェーズ」ともいえる段階が本格化するのはこれからなのです。
デジタルの世界だけに閉じている新興企業が、この新たなフェーズで必ずしも優位ではありません。むしろ、市場で長く親しまれ、一朝一夕には築くことのできない「信頼」を持つ大企業ほど有利に戦えるのです。新興企業が持たない信頼を資本に、デジタルというツールを活用しながら本質的な経営変革に取り組むべき好機といえます。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)