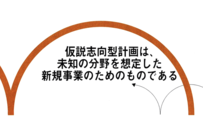民間による宇宙時代の幕開け
政府主導の有人宇宙探査というモデルが確立されたのは、1960年代のことだ。筆者らの最近の研究でも検討したように、この20年間で、それが新しいモデルに転換してきた。政府の取り組みだけでなく、民間による活動の比重が高まってきたのだ。
政府主導の宇宙開発は必然的に、政府の関心に沿って、スペース・フォー・アースの活動に力を入れることになる。国家安全保障、基礎科学、国威発揚などの活動が中心になるのだ。
これは当然の結果と言えるだろう。政府による宇宙開発プログラムへの予算拠出を正当化するためには、国民にとっての利点を示さなくてはならない。その点、政府を選ぶ国民はすべてが(厳密には、ほぼすべてと言うべきかもしれないが)地球上で暮らしているので、スペース・フォー・アースの活動から恩恵を受ける立場にある。
一方、民間企業が人類を宇宙に送り込もうとするのは、宇宙を訪れることを望む人々の需要に応え、その人たちのニーズを満たすことが目的だ。スペースXは、まさにそれを目指してきた。
同社は創業以来20年近くの間に、ロケット打ち上げ産業の様相を一変させ、世界の民間打ち上げ市場で60%のシェアを握るまでになった。同社がつくる宇宙船の規模もどんどん大きくなっている。国際宇宙ステーション(ISS)だけでなく、自社が火星で建設を目指す入植地に人を運ぶことも目指しているのだ。
現状では、スペース・フォー・スペースの市場は、すでに宇宙にいる人たち――つまり、NASAやその他の政府プログラムに雇われた一握りの宇宙飛行士――のニーズを満たすビジネスに限られている。スペースXは、膨大な数の民間宇宙旅行者のニーズに応えたいという壮大な目標を掲げているが、現時点で同社のスペース・フォー・スペースのビジネスは、政府機関(要するにNASA)を顧客とするものがほとんどだ。
しかし、打ち上げコストが下がれば、スペースXのような企業は規模の経済の力を追い風にして、もっと多くの人を宇宙に送り込めるようになるだろう。その結果、民間の需要(つまり、政府機関職員ではなく、旅行者や移住者の需要)が高まり、いまはまだデモンストレーション段階の取り組みが大規模で持続可能なビジネスに発展していく可能性がある。
まずはNASAを相手にビジネスを行い、将来的にはもっと大規模な民間の市場をつくり、それを拡大させていくことを狙う――そうしたモデルを実践している典型的な企業がスペースXだ。しかし、このアプローチを追求している企業は同社だけではない。スペースXはスペース・フォー・スペースの輸送に注力しているが、この新しい産業には製造業も含まれる。
メイド・イン・スペースは、2014年以降、「宇宙で、宇宙のための」製造を行うビジネスの先頭を走ってきた。この年、同社は3Dプリンタ―を使って、ISS内で工具のレンチをつくったのだ。
同社は現在、高品質の光ファイバーケーブルなど、無重力空間でつくられた製品に対して、地球上の顧客の需要が期待される製品の生産も模索している。しかし、それだけでなく同社は最近、NASAと7400万ドルの契約を結び、NASAの宇宙船で用いるための金属製の大きな建材を宇宙空間で3Dプリンタ―によってつくることになった。
未来の民間宇宙船でも、同じように宇宙船内での製造へのニーズが高まると予想できる。メイド・イン・スペースは、そのようなニーズに応えるビジネスで有利な立場に立ちたいと考えている。
スペースXがまずNASAのニーズに応えることから出発し、将来的にもっと大規模な民間市場相手のビジネスを行いたいと考えているのと同じように、メイド・イン・スペースがNASAと行っているビジネスは、民間部門向けに宇宙空間でさまざまな製品を――地上で製造して宇宙まで運搬すれば、途方もないコストがかかるような製品を――製造することに向けた最初の一歩になるのかもしれない。
スペース・フォー・スペースへの投資が活発に行われているもう一つの主な領域は、居住施設、研究施設、工場など、宇宙におけるインフラの建設と運営だ。現在この分野で先頭を走っているアクシオム・スペースは最近、2022年にスペースXの宇宙船「クルードラゴン」により、「史上初の民間人だけの商業宇宙ミッション」を宇宙空間に送り込むことを発表した。
同社は、ISSで居住モジュールの建設と配備を行う独占的な契約も結んでいる。これにより、ISSで(そしていずれは宇宙空間のそれ以外の場所でも)民間の活動を行うためのモジュールをつくるという同社の計画が前進するだろう。
このようなインフラが整備されれば、宇宙ステーションに滞在する人のためのさまざまな関連サービスへの投資が加速する可能性が高い。
たとえば、2020年2月、マクサー・テクノロジーズは、NASAと1億4200万ドルの契約を結び、地球に近い軌道を周回する宇宙船で設備の組み立てを行うロボットを開発することになった。将来、民間部門の宇宙船や入植地が登場すれば、このようにさまざまな建設・修理ツールが必要になるに違いない。
そして言うまでもなく、民間部門でニーズが生まれるのは、産業用の製品だけではない。宇宙に滞在する人たちの快適性を高めるためのビジネスも急成長すると予想される。
ビジネス界は、宇宙の過酷な環境の中で人々の生活の人間的な側面を支援する取り組みに乗り出すだろう。たとえば、2015年には、宇宙テクノロジー企業のアルゴテックとコーヒー会社のラバッツァが協働して、ISSの無重力環境で機能するエスプレッソマシンを開発した。これにより、乗組員の日々の暮らしがわずかに充実した。
人類はこれまで半世紀、宇宙空間の真空と無重量を活かして、地球上ではつくれないものを調達したり、製造したりしたいという夢を抱いてきた。しかし、これまでその試みはたびたび失敗してきた。それを考えると、宇宙空間での製造業に懐疑的な見方をする人がいても無理はない。
とはいえ、過去の数々の失敗は、スペース・フォー・アースのビジネスに向けた取り組みだった。たとえば、2010年代には2つの新興企業、プラネタリー・リソーシズとディープスペース・インダストリーズが宇宙における資源採掘ビジネスの有望性に目をとめた。しかし、スペース・フォー・スペースのビジネスが存在していなかったため、両社が差し当たり生き延びられるかどうかは、採掘した資源(貴金属やレアメタルなど)を地球上の顧客に販売できるかどうかにかかっていた。
結局、莫大なコストをまかなうために十分な需要がないことが明らかになり、資金が干上がって、両社とも別の事業に方向転換していった。
この2つの企業は、スペース・フォー・アースのビジネスが実を結ばず、失敗した。しかし、人間が宇宙に住み始めれば、宇宙で建設資材や金属や水を採掘するビジネスへの需要は極めて大きくなるだろう。その結果、現状よりはるかに安価に、これらの資源を供給することも可能になる。
人々が宇宙で生活し、働く時代が訪れた時、私たちはこれらの初期の小惑星資源採掘会社のことを「失敗した会社」というより、「時代を先取りしていた会社」だったと見なすようになるだろう。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)