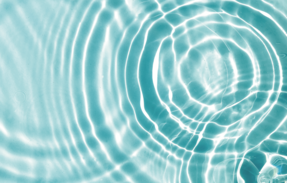-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
見逃せないメンタルヘルス軽視のダメージ
マッキンゼー・ヘルス・インスティテュートが行った調査[注1]では、世界では4人に1人、アジアでは3人に1人が燃え尽き症状を感じている。この症状は従業員の極度な疲労感、認知・感情処理の制御困難、心理的距離を示すものであり、アジアでは特に女性やフロントワーカーでその傾向が強いことがわかった。日本においては、悩み・鬱症状・不安、そして離職願望の度合いが世界水準に比べて低いものの、燃え尽き症状に関しては5ポイント高い31%となっており、対岸の火事ではない。
世界で見た時に、調査した8つの環境要因の中では、燃え尽き症状や鬱症状の最大の要因となったのは「害をもたらす職場活動」だった。これは公平でない対応や悪態をつかれるなどネガティブな対人関係を表すものだが、日本ではこの要因に加えて、「持続可能な仕事の欠如」(健全な仕事量・スケジュールを含むワークライフバランス)が大きな要因となっていることがわかった[注2]。
いずれにしても、従業員のメンタルヘルスを軽視した場合の代償は大きい。たとえば、メンタルヘルス起因の「アブセンティーズム」がその一つだ。これは遅刻や早退、就労が困難な欠勤や休職など、業務自体が行えない状態を指すものだ。オーストラリアではこの企業コストが年間96億豪ドルとなっており、日本でも精神および行動の障害による傷病手当金の支給件数が過去最多を記録している[注3]。また、たとえ従業員が出社できていたとしても、メンタルヘルスの低下は労働生産性の低下にもつながり、企業にとって多大なコストとなりうる。