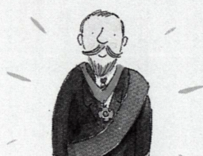-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
企業価値評価で名を上げるも「何かが足りない」
最初に告白しなければならない。
仕事を始めた頃の私なら、この本『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』を見かけても手に取ることはなかっただろう。「ビジネスは世界を良くしているか」とか、「パーパス(目的)と利益は両立するか」とか、そうしたテーマに興味がなかったわけではない。ただ、そうしたテーマが自分の人生に関係あるとは思っていなかったのだ。
私の最初の仕事は保険会社の分析と評価だった。株主に還元できる利益をあげているか、社員に良い暮らしをさせているか、顧客の役に立つ商品を売っているか──そうしたことよりもっと大きな意味で、果たして保険会社がこの地球のために役に立っているのかという問題は、私の最大の関心事ではなかったのである。
私はその仕事でさらに専門性を高めたいと思い、ビジネススクールに行くことにした。企業価値評価の高度に専門的な部分にどっぷりと浸かり、複雑な金融商品を徹底的に理解するという知的な挑戦は非常に面白かった。博士号を得てハーバード・ビジネス・スクールを卒業したとき、世は大金融危機の時代だった。金融の極めて専門的な部分に関わる私の研究は時流に乗り、その分野で最も権威ある複数の学術誌に私の論文が掲載された。幸運なことに、卒業と同時にトップレベルの大学から〝うちで教えないか〟という声がいくつもかかった。
それでも、何かが足りなかった。
ある日私は、良き友人であるイオアニス・イオアヌと話していた。彼はロンドン・ビジネス・スクールで戦略を教える教授だ。私とはハーバード・ビジネス・スクールの博士課程を共にし、いつか一緒に仕事をしたいと前から話していた。しかし、時間もなければ共通する研究テーマも見つけられず、そのままになっていたのだ。
その日、イオアニスは私に尋ねた。社会により良い影響を与えようと努力している企業について何か知らないか、と。我々は、社員の扱いを改善している企業、汚染を減らしている企業、誠実な行動をしている企業などについて議論を重ねた。そして、こうしたテーマが株主利益に負けないほど重要だと見なされることが滅多にないのはなぜか、と疑問に思った。「ソーシャルグッド(社会善)を意識した企業行動は、その企業のコアミッションから意識を逸らし、いずれ必ず企業業績の足を引っ張ることになる」という見方が広く普及しているが、それを裏付ける実際のデータはあるのだろうか──。
2人でこうした疑問点についてじっくり考えてみたところ、しっかりとした答えを持っていないことに気づいた。イオアニスとの議論で、私は当時やりかけだった自分の仕事についても改めて考えてしまった。それは、本当に私のスキルと知識を最も効果的に使った仕事だといえるのだろうか──。書きかけの論文は大事ではあるが、それが目的意識(センス・オブ・パーパス)を満たすものなのか、確信が持てなかった。もっと大きなことをしたかったのだ。そして、すぐに気づいた。「企業が社会に与える影響」について深く考えれば考えるほど、そうしたテーマが私にとって大事に思えると。
正直に言うと、当時の私はなぜ大きなパーパスを見据えて行動する企業とそうでない企業があるのか、わからなかった。その違いが結果的にどのような差を生むのかも、それを分析するのにどこから手をつけるべきかさえもわからなかった。わかっていたのは、この世界が極めて複雑にできており、企業行動を解き明かそうという取り組みは本質的にややこしいということだった。
もう1つわかっていたのは、もしイオアニスと私がこの難題に挑戦する──企業の行動を解き明かし、そこから教訓を得られるか探る──としたら、データの収集に苦労するだろう点だ。その当時、社員の多様性や福利厚生、偶発事故、二酸化炭素排出量、水の消費量、自社製品の手に入れやすさ、などを計量・分析するために必要なデータを公表している企業は極めてまれだったからだ。これは大きな問題だった。こうしたデータなしで、社会における企業の役割を解き明かし、評価することができるのだろうか。
当時なんとか手に入るデータを頼りに、まずは投資家の行動を解き明かしてみることにした。大きなパーパスを見据えて行動している企業の努力を、投資家は評価しているのだろうか──。数千社のデータを分析したところ、ウォール街のアナリストたちは、社会に与える影響をより良くしようと努める企業について、そうでない企業よりネガティブな投資推奨をしていることが証明できた。どうやら投資の世界では、「ある企業がプラスの社会的インパクトを持つことは、その企業の業績がいずれ競合他社に劣後するであろうサインだ」という驚くべき信念がまかり通っているらしい。善行をしたことで経営陣が罰せられるような世界で、我々はどのように生きていけばいいのだろう──。
そもそも、〝企業の善行は業績悪化の兆候〟という予測は正しいのだろうか。仮に正しいとすれば、そこにはどのような因果関係があるのだろうか。企業の善行が本当に将来の業績を悪化させるのだとしたら、我々はそれを現実として受け入れるべきか、それともその現実を変えようと努めるべきか。企業の善行が業績向上につながるような社会にするには、例えばどのような条件が必要なのだろうか──。
『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』
[著者]ジョージ・セラフェイム 著 [訳者]倉田幸信
[内容紹介]
企業の善行と利益は両立する--企業がよいインパクトを社会に与えるための戦術的方法や、こうした社会的変化によって可能になった価値創造の6つの原型、これからの投資家の役割など、ロードマップとベストプラクティスを提示。ESG投資の世界的権威、ハーバード・ビジネス・スクール教授が示す未来への道。
<お買い求めはこちらから>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

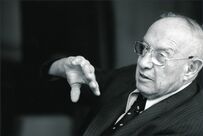





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)