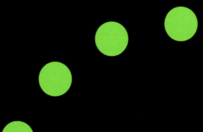-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
川上の企業が非難を免れるのはなぜか
サステナビリティは、みるみるうちにコーポレートガバナンスにおいて不可欠な要素となった。だが、企業が環境に配慮した取り組みに力を入れる一方で、憂慮すべき傾向も表面化しつつある。一部の企業は環境への配慮を謳いながら、それを裏づける具体的な活動をしていないのだ。
その例は多数ある。英国広告基準局(ASA)は最近、世界的な金融機関であるHSBCなどの有名企業のいくつかの広告を禁止した。広告の内容が、気候変動への取り組みに関して「誤解を招く」との理由からである。ライアンエアーの広告についても、同社が欧州で最も二酸化炭素排出量が少ない航空会社であるという主張に根拠がないとして、禁止を言い渡した。
規制当局だけではなく投資家や消費者も、環境に配慮したイメージを装いながら、その根拠を欠く企業を非難し、応報的措置や株の売却、ボイコット、抗議活動という形で、「グリーンウォッシング」(上辺だけの環境保護)に罰を与えている。しかし、筆者らの最近の調査では、一部の企業は同様の姿勢を取りながらも厳密な調査や処罰をある程度、免れていることがわかった。
調査で明らかになったのは、あるタイプの企業、特にいわゆるビジネスグループ(BG)の頂点に立つ企業が、しばしばグリーンウォッシングに関する厳密な調査を免れていることである。BGについてはまだ十分に研究が成されていないが、開発途上国か先進国かを問わず世界に広く存在する企業体であり、インドや韓国、トルコ、チリなど多様な国々の経済活動の大部分とまではいかずとも多くを担っている。
また、基本的に複数の業界にまたがり、リソースを共有し、株式保有と社会的なつながりによって結ばれた系列会社のネットワークである。BGに属する企業を統合するのは一般にグループの中核または頂点にある企業、つまりトップ企業のオーナーである。筆者らの研究は、この仕組みの奇妙なダイナミクスを明らかにした。すなわち、頂点の企業はサステナビリティの取り組みを自社の活動によって裏づけることなく、下層の系列会社の取り組みに「ただ乗り」して報告を出している。グリーンウォッシングのレッテルを貼られることなく、これができるのである。
この現象を解明するために、筆者らは35カ国のBGに属する上場企業515社のデータを分析した。具体的には、まず環境、社会、ガバナンス(ESG)評価機関のリフィニティブ(前身はASSET4)からESGのデータを入手した。それは、企業が報告する情報に基づいて、各企業のESGの実績を同じ業界の他企業との比較で測定したデータである。筆者らはこれを利用して、企業の実質的なサステナビリティ活動(社会的責任の方針やプログラムに関連するもの)と象徴的活動(報告、主張、開示など)を区分し、この2種類の活動のギャップを基準として、当該企業の「言葉」と「活動」がどの程度乖離しているかを判断した。
頂点にある企業は下層の系列会社と同等レベルのサステナビリティを発表しているにもかかわらず、実質的なサステナビリティ活動は少なかった。言い換えると、頂点企業はグループの他の企業に比べて、実際に「活動したこと」以上の「宣伝」を組織的に行っていたのである。
このダイナミクスにもう一つの層を加えるなら、系列会社とブランド名を共有する頂点企業は、共有するブランド名がない頂点企業に比べて、さらに実質的なサステナビリティ活動が少ないことがわかっている。残念なことに、株式市場はこの種のグリーンウォッシングについて、下層の系列会社よりも頂点企業に対して寛大なようである。
この矛盾をどう説明できるだろうか。BG以外の企業であれば見え透いたグリーンウォッシングと認識されるものが、BG独特のエコシステムでは正当な分業と解釈されているといえそうだ。
頂点企業は影響力のある立場と象徴的な力を利用して、グループの全体的なサステナビリティの取り組みを水増しして伝える「コミュニケーター」の役割を演じる。一方、下層の系列会社は「実践者」の役割を担い、実質的な取り組みを実践する。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)