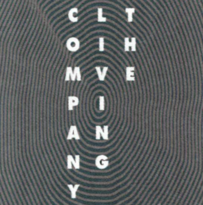このやり方は、グローバルなサステナビリティの運動に、要はただ乗りしようとする頂点企業に短期的利益をもたらすかもしれない。
一方、市場が頂点企業の明らかなグリーンウォッシングに寛大であっても、責任は免れないことを認識しなければならない。いずれグリーンウォッシングは長期的評判に深刻なダメージを与え、ステークホルダーの信頼を損なう可能性がある。リーダーはそれを理解し、この機会にサステナビリティの実践と報告を強化すべきである。実際、この研究結果は、BGに属する企業だけではなく、さらに広く、提携やジョイントベンチャーなどを通して他企業と提携関係にある企業のマネジャーにとっても、重要な意味がある。
サステナビリティの取り組みについて正直であること
サステナビリティの取り組みを誇張すると、言葉と現実のギャップが露呈した時に大きく裏目に出る。一つの系列会社のよい評判がグループ全体に好ましい影響を与えるように、グリーンウォッシングの疑惑があると、当の系列会社を超えて悪影響が及ぶ。
リーダーはサステナビリティに関するパブリックコミュニケーションには、グループの真の実践内容を反映させなければならない。サステナビリティ活動とコミュニケーションにずれがありそうであれば、それを報告し、修正すべきである。さらに、外部の保証機関による総合的な監視を確立するならば、透明性と説明責任を高め、グリーンウォッシングと見なされる可能性を減らすことができる。
共通のアイデンティティを通して、系列会社にサステナビリティのモチベーションを与える
グリーンウォッシングと見なされることを防ぐためには、頂点企業のリーダーはグループ内での自社の調整能力のみに頼るべきではない。グループのアイデンティティ、つまり企業の中核的な価値観や原則の源となる存在であることも利用できる。そして、長期的なサステナビリティの達成に向けてグループ企業を動員するために、アイデンティティを利用できるし、そうすべきである。
事実、多くのBGは自社の歴史をアピールすることで、それを実行している。たとえば住友グループは、相互の繁栄と公益の尊重(自利利他、公私一如)を謳った400年前の設立理念(住友の事業精神)を基盤として、サステナビリティの取り組みを促している。
サステナビリティのベストプラクティスと人材を共有する
頂点企業のマネジャーは、系列会社のサステナビリティの取り組みをただ報告するに留まらず、グループ全体に普及させるべきである。グループ内に張り巡らせた内部人事ネットワークを利用して、企業のサステナビリティを熟知する人材を採用することもできるし、グループ内のサステナビリティ活動を見つけ出して普及させるためのチームをつくるという手もある。
タタ・サンズを頂点企業とするタタ・サステナビリティ・グループ(TSG)はその一例で、「タタグループのすべての企業がサステナビリティを事業戦略に取り込めるように指導し、サポートし、思想リーダーとなる使命」を担っている。別の言い方をすれば、頂点企業のコミュニケーションの役割をグループ内のステークホルダーに広げることは、グループ全体の実質的なサステナビリティ戦略の形成に役立つのである。
ステークホルダーの期待を意識する
ビジネスの世界は急速に変化しており、サステナビリティに対するステークホルダーの期待も例外ではない。この展開を無視していると、顧客や従業員、投資家などの重要なステークホルダーとの関係で緊張が高まりかねない。リーダーはステークホルダーの期待に合わせて、サステナビリティへのコミットメントが透明性のある誠実なものになるよう努めるべきである。
最後に、サステナビリティの追求はマーケティングのための戦術ではなく、実質的な長期的活動が求められるコミットメントである。グループの強固なアイデンティティはBG内部では頂点企業を守ってくれるかもしれないが、その外では、報告の聞き手やステークホルダー、そして世界が、単なる象徴ではない実質的な活動を要求している。
特にBGや似たような組織構造の環境では、評判が少しでも傷つけば企業グループ全体に波及し、組織のエコシステム全体に深刻なダメージを与える。そのため長い目で見ると、サステナビリティの実践への誠実なコミットメントがあってこそ、企業は一貫して恩恵を得られるのである。
"Research: How Some Companies Avoid Accusations of Greenwashing," HBR.org, September 27, 2023.





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)