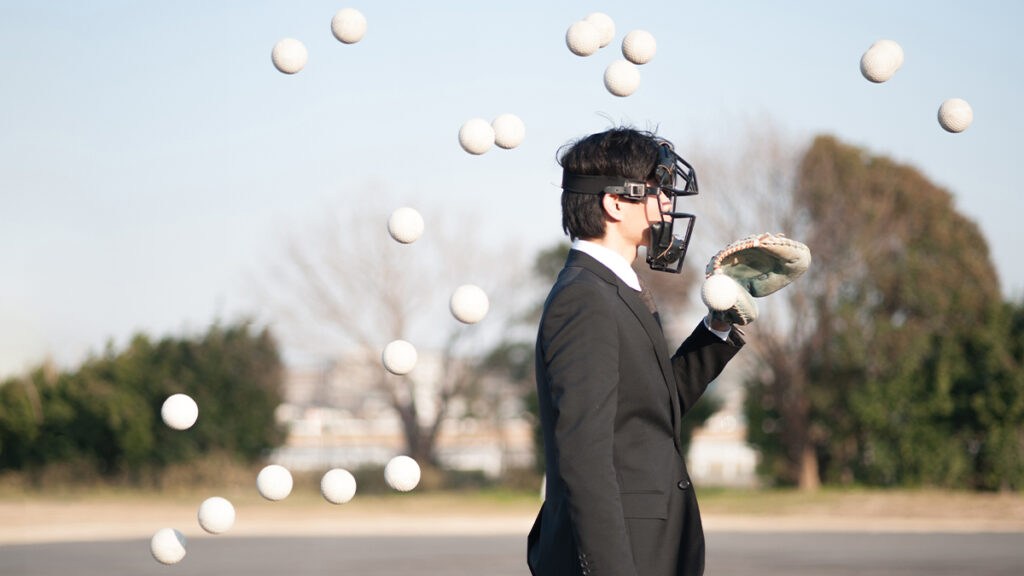
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
2種類の努力の違い
私たちは子どもの頃から、努力が重要だと教えられてきた。だが、努力には2つの種類があることは教えられてこなかった。実行する努力と、改善する努力だ。
この2種類の努力の違いをきちんと理解していないと、長い「やることリスト」を前に、実行する努力を延々と続ける罠に陥ることになる。自分が知っている最善の方法でタスクを実行し、ミスを最小限に抑えることに注力する。
筆者はこのマインドセットを「パフォーマンスゾーン」と呼んでいる。このゾーンに陥ると、物事を片付けることだけに集中して、視野が狭くなる。これは生産的と錯覚しがちだが、やがて停滞をもたらす。物事をやり遂げることばかりに意識が集中していると、困難に直面した時、より懸命に働き、より労働時間を増やし、より多くの人を雇い、場合によっては細部を端折ることで対処してしまう。だが、変化のスピードのほうが速いため、結局いつも後れを取っている感覚が残ってしまう。
そこで改善への努力に視点を切り替えて、筆者が「学習ゾーン」と呼ぶマインドセットに入ると、より効果的な方法で物事を成し遂げられるようになる。それはよりよい結果をもたらすだけでなく、目標を達成するプロセスをより興味深く、楽しく、充実したものにしてくれる。
マネジャーがチームをパフォーマンスゾーンから学習ゾーンに切り替えて、変化と成長を促しつつ、チームが効率的に働くことができるようにするための戦略は5つある。
1. 学習ゾーンの環境をつくる
たいていの人は、仕事でも日常生活でもパフォーマンスゾーンにはまり込み、物事をできるだけ間違いなくこなすことに集中しがちだ。初心者のうちはそれでもよいかもしれないが、熟練してくると、この一点集中は、停滞か、より悪い事態を引き起こす。
たとえば、ハーバード・メディカル・スクールのあるメタ分析によると、一般的に、総合診療医は、診療年数が長いほど治療成績は低下する。これは、多くの総合診療医がケアを提供すること、つまり診察し、診断を下し、自分の知っている最善の手当てをすることにだけ注力しているからだ。ところが、有効な学習、つまり新しい知識やスキルを探索し、間違いを検証する努力を続ける医師は、仕事を改善し続けている。
たいていの人は、毎日の重要な時間を特定のスキルの学習や練習に割く余裕がない。そうだとすれば、成長を加速させる最大のチャンスは、目の前の仕事を、改善につながる方法でこなすことだ。同時にパフォーマンスゾーンと学習ゾーンの両方に入る、筆者が「やりながら学ぶ」と呼ぶ方法で物事を進めるのである。
やりながら学ぶと、自分がすでに習得していることを超えた飛躍が可能になる。自分を次のレベルに押し上げる挑戦的な目標を設定し、何を学び、何を変えられるかに常に注意を払う。これは実行しながらできることだ。たとえば、どこかで聞いた新しいテクノロジーやテクニックによって、あなたのチームが顧客の問題をよりよく、よりスピーディに、より少ない労力で解決できるかどうか試してみる。
チームが慢性的にパフォーマンスを追求している状態から、「やりながら学ぶ」状態に移行させるために、マネジャーにできることはいくつかある。
・コアバリューや重要な姿勢、チームの規範など、チームの指針となるメッセージ表現を見直す。あなたが使っている表現は、継続的な変化や改善を中核的な目標として強化しているか。また、変化や改善するための取り組み方を部下たちに示しているか。
・どのような場合にパフォーマンスゾーンに留まることが適切か、どのタイミングで学習ゾーンに入るべきか、またその方法を明確にする。たとえば、ピンチに瀕している重要プロジェクトの期限が迫っている場合は、パフォーマンスゾーンに留まってもいいかもしれない。一方、定期的に学習ゾーンに切り替えられるようにするためには、実験的な行動が歓迎される仕組みを構築したり、部門横断的な話し合いの場をスケジュールしたりして、組織への理解を深め、コラボレーションを強化する方法を考えてみよう。
・顧客や同僚、上司、直属の部下などからフィードバックをどのように収集するか、それを得る理由、タイミング、方法を一致させる。フィードバックに耳を傾けると、チームがうまくできていることに関するインサイトや、変更を検討すべき点についてのアイデアを得ることができる。
・チームが定期的に協力方法や、やり方を変えるべき部分を話し合える機会をつくる。変化なくして改善はない。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









