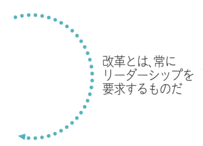(4)さらに情報が必要だ
ジェフ・ベゾスはアマゾン・ドットコムの株主に宛てた書簡で、ほとんどの意思決定は、ほしいと思う情報の70%くらいが集まった段階で行うべきだと述べている。筆者らが見てきた範囲でも、変革を主導することにつまずいたリーダーの一部は、情報が100%揃うまで待とうとしていた。言ってみれば、まだ書かれていない物語の結末が一点の曇りもなく明らかになるまで、動こうとしなかったのである。
このような思い込みを抱いているリーダーは、ある決定に対して従業員がどのような反応を示すかとか、思い切った戦略上の動きに対して同業他社がどのように反応するかといったことをすべて知っておきたいと考える。そこで、たくさん会議を行い、より多くのシナリオを検討したほうが安全だと感じる。しかし、その安心感は幻想にすぎない。待つことにより、組織の脆弱性は増大することこそあっても、縮小することはないのだ。
(5)速く動くのは軽率だ
この点は、思想家のラルフ・ウォルド・エマソンがさらに文学的な言葉で表現している。エマソンは、慎重さをテーマにしたエッセーの中で「薄い氷の上をスケートする時、安全をもたらすのはスピードである」と記した。速く動くことに疑念を抱いている人は、この言葉を肝に銘じよう。直感的なイメージとは反対に、速く行動すれば、危険が高まるのではなく、安全が増す場合がある。速く動けば、氷の下に落ちる確率が下がるからだ。
(6)ゆっくり動くことが正しい
信頼、インクルージョン、明晰さに関して強力な土台を築けていないのであれば、ぜひスピードを落としてほしい。その場合は、アクセスを踏むのをやめよう。しかし、それ以外のケースでは、スピードを落とせば、有意義な変化を起こすチャンスをふいにしかねない。物事が遅すぎる場合もあることを忘れてはならない。
(7)メンバーの負担が重くなりすぎている
時には、不安や燃え尽き(バーンアウト)などの社会的・組織的な問題への対策として、自分でも気づかずに、物事のスピードを減速させている場合もある。しかし、このような不安などの感情が組織内で大々的に頭をもたげてきた時は、ペースを落としてもあまり効果がない可能性が高い。それよりも、問題に直接向き合ったほうが効果的だ。リーダーたちがしかるべき問題を解決し、ステークホルダーへの配慮を示すことを通じて、信頼を育めれば、メンバーは問題に対処するために必要とされるスピードで前に進めるようになる。
(8)あらゆることを完璧に行わなくてはならない
すべての面で完璧でなくては気が済まない人は、一部のことで真に秀でるために、資本や時間やエネルギーなどのリソースを集中的に注ぎ込むことができない。スピードの面で飛び抜けた成果を上げようと思えば、ほかの側面では不十分な結果でよしとしなくてはならないのだ。リソースを集中的に注ぎ込む対象を決める際に留意すべきなのは、別の側面で質を落とせば高いレベルを達成できて、しかもその行動の結果として主要なステークホルダーの信頼を損うことがないものを選ぶことだ。難しそうに聞こえるかもしれないが、イメージほど難しくない。
(9)構造的な仕組みはスピードの敵である
米国海軍特殊部隊「SEALs」に、有名な格言がある。「ゆっくりはスムーズ、スムーズは速い」というものだ。筆者らは、この格言をこう解釈したい。摩擦を減らそうと思えば目先は時間がかかるけれど、プロセスを整備するために投資することにより、ペースを加速させることが可能になる、と。筆者らの経験から言うと、明確で良質なオペレーティングシステムを築くことこそ、摩擦軽減のための最良の方法だ。少なくとも、次の会議に向けて議題を設定するようにしよう。
(10)準備にもっと時間が必要だ
変化が予想されると、不安が生まれる。そうした不安に対する解毒剤は、実際に変化を起こし、不安を塗り替えることだ。リーダーが変化を主導するのを先送りにすればするほど、周りの人たちは、不確実な未来に生じるかもしれない破滅的な事態についての幻想──これは筆者らの同僚であるトム・デロングが用いている言葉だ──を抱くようになる。それに、言わば絆創膏を引きはがして前に進むことには、勢いよく出発するための勢いを生み出す効果も期待できる。重要なのは、まずは始めることなのだ。
* * *
本稿は、2人の近著Move Fast and Fix Things(未訳)からの抜粋に編集を加えたものである。
"10 Beliefs That Get in the Way of Organizational Change," HBR.org, October 24, 2023.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)