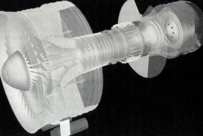課題設定を明確にする
強調したいことは、課題設定が漠然としていては、意思決定プロセスの課題に捉え直すことはできないということです。
例えば、「工場における出荷物の検品作業の改善」といっても課題は様々です。不良品の見逃しをなくすことかもしれないし、検品業務の人件費を抑制することかもしれないし、検品業務の後継者不足を解消することかもしれません。それによって、データ分析で何を解くべきかは変わってきます。もし、ビジネス課題を設定するときに、漠然と「検品業務の改善」という課題設定をしてしまい、そのまま「何を解けばいいか」考えると混乱するでしょう。意思決定プロセスの課題を言語化するステップを挟むことで、「検品業務の改善」という漠然とした課題設定ではそのような言語化はできないため、課題をもっと具体化しなければならないことに気付かせてくれるのです。
例えば、出店立地計画の課題といっても様々です。売上げを最大化するような立地を選ぶことかもしれないし、社内での合意形成を円滑にすることかもしれないし、ライバル店の後塵を拝さないように立地判断を迅速化したいのかもしれません。それによって、データ分析で解くべき問題は変わってきます。もし、ビジネス課題を設定するときに、漠然と「出店立地計画の改善」という課題設定をしてしまい、そのまま「何を解けばいいか」考えると混乱するでしょう。意思決定プロセスの課題を言語化するステップを挟むことで、「出店立地計画の改善」という漠然とした課題設定ではそのような言語化はできないため、課題をもっと具体化しなければならないことに気付かせてくれるのです。
ここでも、迷った時は何度も言語化してみることが大切です。無意識の漏れや抜け、曖昧な表現などに気づけるのではないでしょうか。ぜひ本書『データ分析・AIを実務に活かす データドリブン思考』巻末のワークシート②を活用いただければと思います。
本書の趣旨から少し外れますが、ビジネス課題を意思決定プロセスの課題と捉え直すことは、データ分析を活用しない場合でも、課題を突き詰める手立てとして有効です。
例えば、設備のメンテナンス費用が経営を圧迫するという問題を解消するために、「定期的な点検」から「状態監視型の点検(状態が怪しい場合のみ点検する)」に移行するという課題に取り組むとしましょう。往々にして、データサイエンティストに声がかかり、設備の故障を予測するモデル開発に取り組みます。
データサイエンティストは、精いっぱいの力量を発揮してモデルを開発しますが、どのような分析手法を使えども現実を捨象してモデリングするわけですから、100%確実に予測するには至りません。すると、社内で「外れた場合の責任は取れるのか? 現行よりも点検頻度が少なくなるということは、リスクは大きくなるということではないのか?」といった責任回避型の議論が巻き起こり、結論は出ず、なし崩し的にデータサインティストにゴールなき精度向上を目指させることになります。
しかしながら、「意思決定プロセスに課題がある」という意識を持てば、「定期的な点検から、状態監視型の点検に移行すべきかどうかの判断基準を確立できていないこと」が課題であると気付くかもしれません。課題は予測モデルの高精度化であるという意識のままではデータ分析にカネと時間をかけるだけの泥沼にはまりますが、課題は「定期的な点検から状態監視型の点検に移行するか否かを意思決定するプロセスを作ること」と考えれば、前進していくでしょう。
例えば、「競合他社と比べると革新的な商品を出せない」という問題を克服するべく、「革新的な商品開発力の強化」という課題に取り組んでいるとしましょう。これでは課題設定が漠然としており、何をすればよいか見えてこないでしょう。しかし、「意思決定プロセスに課題がある」という意識を持って掘り下げれば、「社内説明では従来路線から変える理由を厳しく問われるため、従来路線から外れる商品企画は通しにくい」ことに気付くかもしれません。
もしくは、「当初の商品企画は革新的であっても、社内で合意形成を進める間に、革新的な要素が削がれる」ことに気付くかもしれません。もしそうならば、課題は「商品開発の社内決裁プロセスにおける現状継持的な視点の排除」になるかもしれません。
いくらデータ収集のシステムや優秀なAIの専門家を入れても、それだけではビジネスには勝てない。国内のデータサイエンティストとして草分け的存在であり、大阪ガスのデータ分析専門組織を率いた筆者。現在は滋賀大学データサイエンス学部で教鞭をとり、約25年かけてたどり着いたデータドリブン思考の重要性を示す。
お買い求めはこちらから
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)