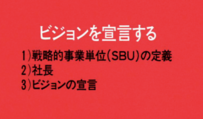-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
データが揃う前に行動しなければ、機会損失につながる
不確実性の高い状況で戦略上の方向性を定めることは容易でない。常について回る問題の一つは、ある行動の妥当性を裏づけるデータが入手できるまで待っていると、しばしば手遅れになってしまうという点だ。この「情報と行動のパラドックス」とでも呼ぶべき問題に対しては、逆説的な解決策が必要とされる。具体的には、リーダーは、データが行動すべきでないと示す時にこそ行動しなくてはならないのだ。
といっても、データを無視しろと言いたいわけではない。重要なのは、戦略上の投資に関する判断を下す際にふだん用いているデータ──市場規模、成長率、市場シェア、利益率など──の限界を認識することだ。すでにデータという形で存在している情報は、過去に起きたことを描き出しはするけれど、これから起きること、あるいは起きるかもしれないことは描き出せないのだ。
戦略立案を推測に委ねたり、勘頼みにしたりすべきではない。リーダーは、言わば意識的に「さまよい歩く」ことにより、新鮮なインサイトを獲得し、そうしたインサイトの助けを借りて不確実性のなかで現実を把握し、今後の進路を定める必要がある。本稿では、それを実践するための3つの具体的な方法を紹介する。
1. 変革の必要性を告げる「早期警戒警報」に目を光らせる
サティア・ナデラがマイクロソフトのCEOとして推進してきた変革プログラムの核を成す要素の一つは、売上高などの遅行指標ではなく、ネット・プロモーター・スコア(NPS)のような先行指標を重視するように転換することだった。遅行指標で把握できるのは、過去の意思決定がもたらした結果でしかない。それに対して、先行指標は、未来の問題、もしくは未来の機会を映し出すものである。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)