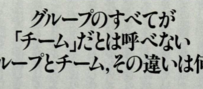-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
出社勤務の再開に苦戦する経営者とマネジャー
新型コロナウイルス感染症のパンデミックが知識労働者のリモートワークへの移行を加速させてから、4年余りが経過した。一部の組織が完全出社勤務の再開を試みてきたものの、リモートワークと出社勤務をミックスしたハイブリッドワークが今後も存続することは間違いない。だが、雇用主は依然として実行に苦労している。とりわけ筆者らが話を聞いたマネジャーは、スケジューリング、文化、生産性という3つの重要な課題を指摘する。
スケジューリング
多くの組織は、リモートワークと出社勤務を組み合わせた働き方に落ち着いてきた。たとえば、出社が3日(火~木曜日)とリモートが2日(月曜日と金曜日)といった具合だ。だが、従業員がこのガイドラインをきちんと守るとは限らない。実際、追跡データによると、一部の従業員は期待された(または義務づけられた)頻度で出社していない。出社してもできるだけ早く退社する「コーヒーバッジング」と呼ばれるトレンドさえある。また、通院や休暇を取得する日を、在宅勤務日ではなく出社勤務日にぶつける従業員が多く、チームで費やす時間がますます短くなることにいら立ちを覚えるマネジャーもいる。
要するに、無料の朝食やランチを用意したり、服装規程を緩くしたり、社内交流イベントを増やしたり、オフィスを快適にしたりと、出社を促す手段をあれこれ尽くしても、十分な効果は得られていないようなのだ。
この課題を克服するカギは、出社頻度ではなく、物理的なプレゼンスやチームで集まる必要があるタイミングに目を移すことだ。たとえば、従業員が入社したばかりで、新人研修を受けている場合は、出社して重要な同僚と直接つながることが決定的に重要になる。同じように、繁忙期や、チームワークや共同での意思決定が必要な時は、従業員に出勤を義務づけたり、強制したりする余地があるべきだ。その理由をきちんと伝えられれば、従業員もその勤務態勢を理解して、受け入れる可能性が高まる。
たとえば、極めて重要な会議に対面で出席することを義務づけるのは、完全に合理的である。実際、米食品大手JMスマッカーでは、この手法がうまくいっているようだ。同社は本社所属の従業員に対し、22週間の「コアウィーク」(前年中に発表される)には対面での会議への出席を義務づけている。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)