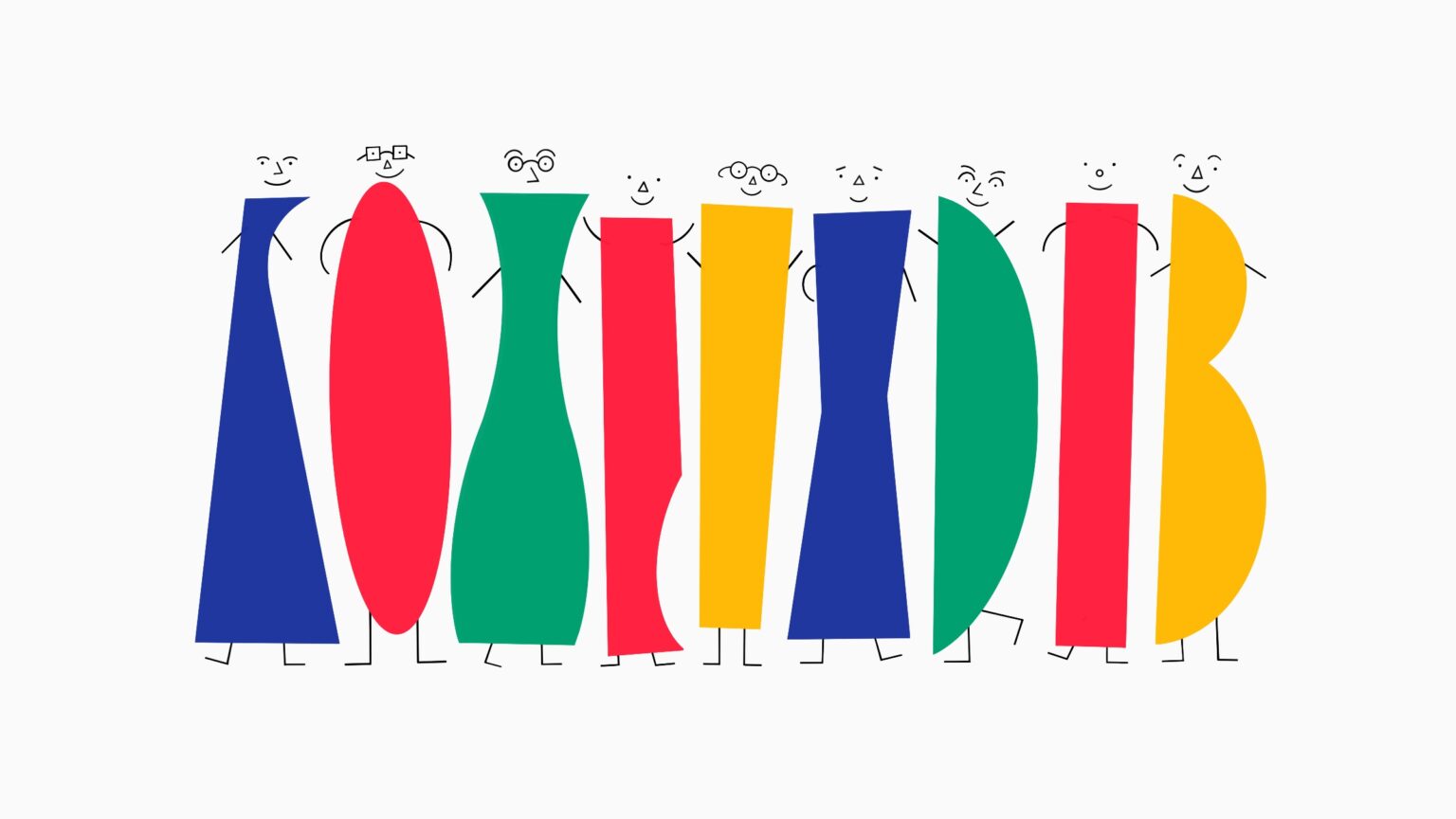
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
先日、HR専門家が集う中心的な組織であるソサエティ・フォー・ヒューマン・リソース・マネジメント(SHRM)が、インクルージョン(包摂性)、エクイティ(公平性)、ダイバーシティ(多様性)の略語「IE&D」を廃止し、「I&D」に変更すると発表した。
これにより、すべての従業員が活躍できる職場づくりに必要な要素から、「公平性」が除外されることになる。これは、職場でのDEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)に関する数十年にわたる研究の知見に反する危険な前例となる。
公平性が重要な理由
公平性からの脱却が進む理由の一つとして、公平性が何を意味するかという理解が人によって異なる点が挙げられる。公平性の本質はフェアネス(公正さ)にある。公正なプロセスを踏んでいれば、成功のチャンスを得られる人が増え、結果の再分配につながりやすくなる。
公平性を実現するためには、人によって対応を変える必要が生じることが多く、一見しただけでは、それを不快に感じる人もいる。だが、人によって異なる対応は、疎外されたグループの従業員がぶつかる壁──特権的なグループの人々はそうした壁にぶつかることはない──を乗り越えるためのものだ。言い換えれば、公平性とは、疎外されたグループの従業員が特権的なグループの同僚と同じ機会やリソースにアクセスできるよう、構造、政策、プロセスを変更する試みなのである。
包摂性と多様性を高いレベルで実現しているからといって、必ずしも公平な実践や結果が保証されるわけではない。たとえば、ジェンダーの多様性が高水準で実現されているが、管理職や経営層に女性がほとんどいないという組織を想像してみよう。企業データの数字が高水準の包摂性やジェンダー多様性を示していたとしても、明確な形で公平性を高める取り組みをしない限り、リーダーシップにおけるジェンダーギャップ(と最終的には報酬の格差)が解消されることはない。
これは職業分離の一例であり、これにより、女性や歴史的に疎外されてきたグループの人々はいまも不利益を被り続けている。また、公正さを重視する企業は、意図的に公平性に焦点を当てる必要があることも、この事例から浮き彫りになる。
SHRMは、HR部門および企業リーダーに向けて、公平性を軽視し、「職場と社会における包括的な変化の触媒」として包摂性を優先させるよう促している。SHRMは包摂性を「職場での帰属感」と定義し、「包摂性を最優先することで、社会的な反発や分極化の拡大を招いた現行のDE&Iプログラムの欠点を改善したい」と主張している。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









