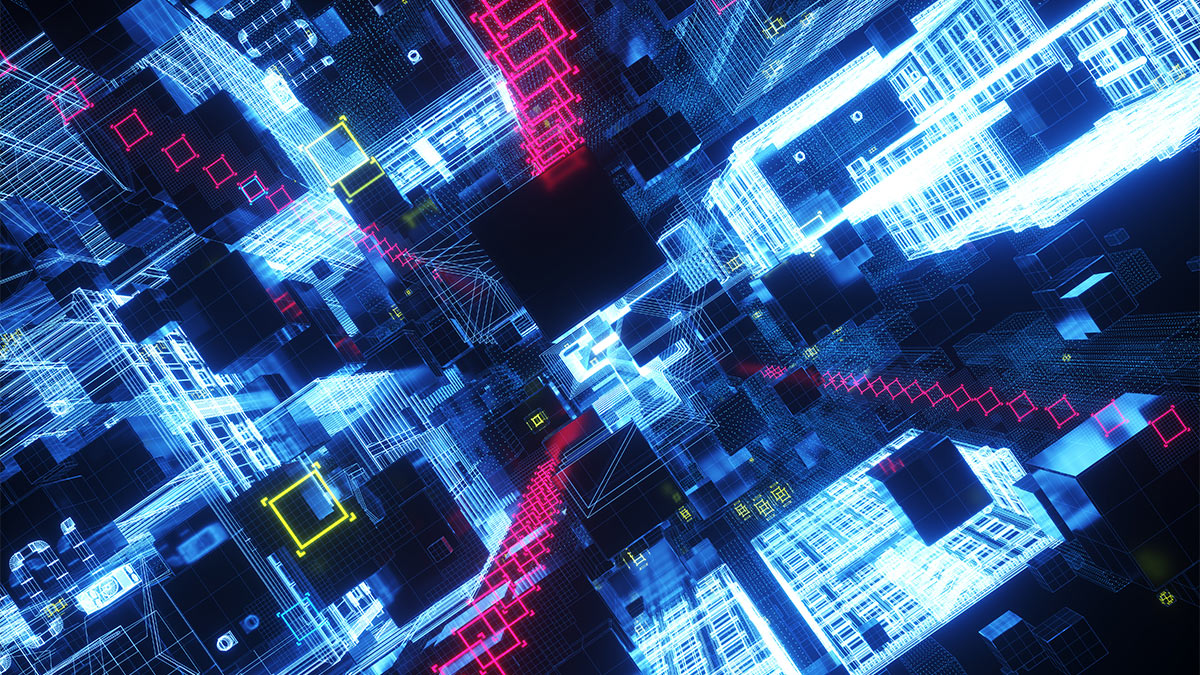
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
テクノロジーで分散型組織の「つながり」を強化する
AIの進歩とパンデミック後の働き方の不整合さによって、私たちは職場でどのようにつながりを築き、それを維持するかについて、見直すべき転換点に来ている。オフィス復帰の義務化に苦慮する大手企業も、リモートワークを恒久的に採用するその他の企業も、リーダーたちはデジタル化が進む職場において、真の人間関係をいかに育むかという大きな課題に直面している。この課題は、生産性という指標に留まらず、物理的な存在がもはや影響力の前提条件ではなくなった時代において、職場の公平性、従業員のウェルビーイング、組織の回復力といった根本的な問題にも関わっている。
分散型労働力の大きな矛盾は、私たち労働者を隔てる物理的な距離にある。つまり、従来の意味の「つながり」に疑問を投げかけると同時に、新興テクノロジーを活用した新しい有意義な交流の道を開こうとしている。何マイル離れていても、最新のイノベーションを利用すれば、そのギャップを埋め、コミュニケーションやコラボレーションを実際に顔を合わせているかのようにリアルで魅力的なものにすることはできる。物理的に離れていても、テクノロジーの力でつながりを維持・強化し、チームワークや仲間意識のエッセンスを、このデジタル時代にも保ち、育むことはできるのだ。
筆者らは、共著Employment is Dead(未訳)のための調査や、仕事をより魅力的で人間味あるものにする破壊的テクノロジーへの投資について企業に助言を行う中で、テクノロジーを活用して分散型チームのつながりを強化する方法をいくつか発見した。
リモートワークから完全分散へ
多くの企業がまだハイブリッドワークの是非について議論しているなか、より急進的なアプローチとして、分散型自律組織(DAO)の完全分散型チームを採用する企業も現れている。このモデルでは、本社や従来の階層構造は存在しない。代わりに、スマートコントラクトや集団的ガバナンスを通じて意思決定が行われる。これがリモートワークを導入する従来の企業と、地理的条件がまったく関係ないデジタルネイティブな組織との違いだ。
ステーブルコインDAI(ダイ)を発行・管理するMakerDAO(メーカーダオ)のような企業は、このモデルを実際に運用している。同社の貢献者は複数の大陸にまたがり、ブロックチェーンベースの投票システムを通じて財務管理から製品開発まであらゆることを協力して決定している。DAOのような構造を試している従来型企業もある。たとえば、AIを活用した人材紹介プラットフォームのブレイントラストは、ハイブリッドモデルを採用し、世界中にいる貢献者がプラットフォームを共同所有・管理し、分散化されたコア業務を担っている。
完全な分散は、機会を民主化する。完全分散型の企業であれば、地理的な制約や転居の必要なしに、グローバルな人材プールを活用できる。たとえば、GitLab(ギットラボ)は完全分散型モデルを採用し、65カ国以上にチームメンバーがいる。完全分散型ワークモデルでは、期待されてきたデジタルワークの究極の姿が見られる。つまり、時間と場所の制約からの解放、それによって何を生産し、どのようにコラボレーションするかに純粋に専念できる状態である。完全分散型の環境では、仕事は「行くもの」ではなく「やること」になる。
機会を民主化することは、テクノロジーが人々を結びつけると同時に孤立させるという現代の仕事の根本的な矛盾に意義を唱えることだ。また、従来の障壁をなくすことは、単にアクセスを広げるだけでなく、職場の人間関係のDNAそのものを書き換えることである。このアプローチでは、不快な疑問にも直面しなければならない。物理的にそこに「いる」ことは、本当にエンゲージメントとイコールなのか。デジタル空間では、会議室よりもその人らしさを発揮できるだろうか。物理的領域とデジタル領域の両方にアクセスを広げている企業は、真のつながりが空間の共有ではなく、目的の共有と発言の平等から生まれることを認めている。この認識によって、リモートワークは単なる物理的課題への対策から、ボーダレス化の進む世界で、どのように有意義な絆を築くかを考え直すきっかけになる。
メタバースにおけるコラボレーション
メタバースという概念が主流メディアで時折話題に上るが、集団的でバーチャルな共有空間という発想は、世界中の労働者にとって依然として非常に興味をそそるものだ。さまざまな企業が、会議やブレインストーム、さらには企業イベントの開催にメタバースプラットフォームを試験的に利用している。PwCの報告によると、仮想現実と拡張現実は、2030年までに世界経済に最大1兆7900億ドルもの付加価値をもたらす可能性があり、その大半はコラボレーションや業務関連活動の改善によるものとされる。
これによって得られる恩恵は、魅力を増した労働環境によるウェルビーイングの向上と効率性の改善である。メタバースは、創造性とウェルビーイングを同時に高める環境をモデル化する無数の機会を提供する。たとえば、仮想のビーチで行うブレインストーミングや、人造の山頂でのチームミーティング、あるいは静かな仮想庭園での個人作業時間を想像してほしい。SoWork(ソワーク)やVirbela(バーベラ)のような仮想オフィスは、こうした可能性を広げている。
メタバースはまた、このリモートワーク時代に大幅に減っている社交も可能にする。バーチャルな卓球台や同僚と座って食事ができるデジタルキッチンなど、オフィスの社交場的側面を再現し、さらに強化することさえ可能である。従来のオフィス環境では制約を感じていた障害を持つチームメンバーも、ニーズに合わせてカスタマイズされた仮想環境では自由に活動できる。たとえばメタ・プラットフォームズは、両脚のない男性の視点を通してホライズン・ワークルームズ(Horizon Workrooms)を紹介した。その男性は、同社のバーチャルオフィススペースを自由に歩き回り、物理的な世界ではできなかった同僚との交流を別の形で行うことができた。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









