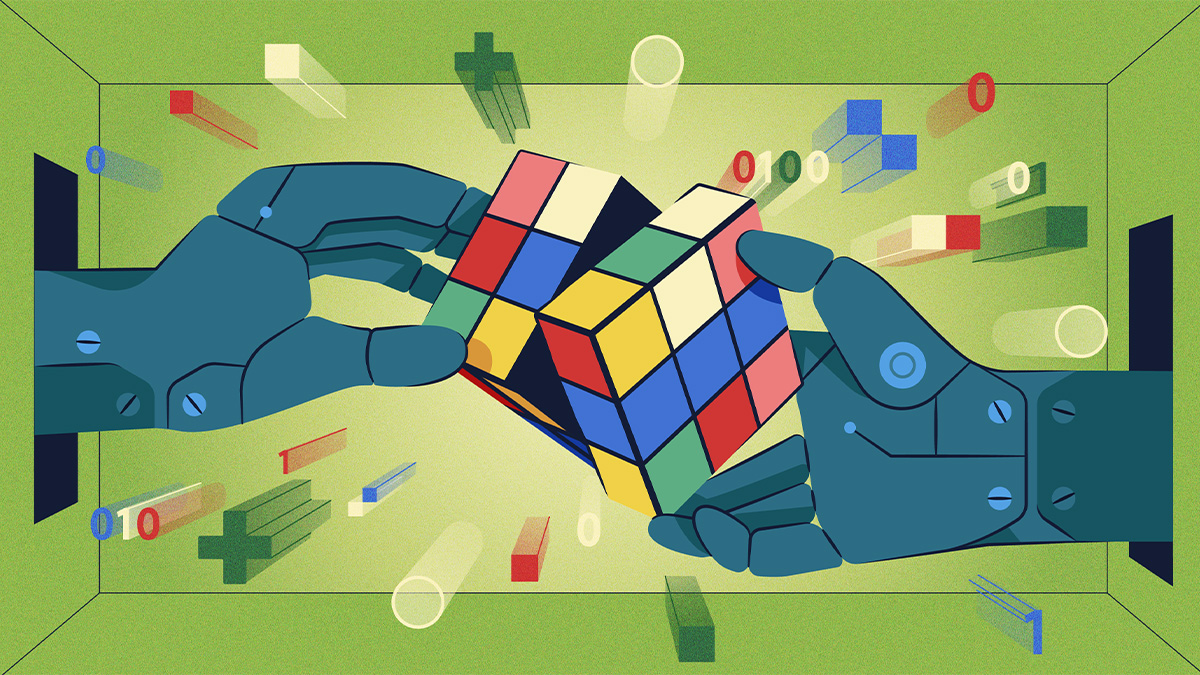
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
AIを思考のパートナーにする
組織が対話型生成AIモデルの利用を拡大するにつれて、多くのマネジャーが、このテクノロジーに単純な生産性向上のタスクをはるかに超える可能性があることを理解するようになった。いまやマネジャーの3分の2が、生成AIは思考のパートナーになりうると考えており、新たな視点の提供、長所と短所の比較検討、トレードオフの評価、戦略的思考の強化といった点で、リーダーシップの発展を支援できると期待している。
ただし、将来への期待は高いが、その道のりは遠い。自分は生成AIをこのような方法で活用するスキルと知識を持っていると答えたマネジャーは、わずか30%に留まる。
幸い、彼らはこのギャップをすぐに埋めることができる。筆者らはこれまでの経験と数えきれないほどの対話、そして数千回のプロンプトの反復をもとに、マネジャーが対話型生成AIツールを思考のパートナーとして活用する方法とツールをまとめた、HBR版ガイドを作成した。
これらのテクニックを使って人間とAIが協力すれば、別々に作業した場合は不可能であろう質の高い成果を達成できる。筆者らが「共思考」(co-thinking)と呼ぶこのプロセスについて、本稿ではその導入方法を説明する。
共思考の力
生成AIは、スピーチの準備に根本原因分析(RCA)、戦略策定などあらゆる場面で思考のパートナーとして活用できる。いくつか例を見ていこう。
・マリオは製造工場のプロジェクトマネジャーで、彼と彼のチームは技術的な課題を解決しなければならない場面が多い。問題の根本原因を突き止めることは、繰り返し発生するが複雑なタスクだ。マリオは生成AIとの構造化された対話を設計し、問題をじっくり考えるために役立てている。新しい問題が発生するたびに、プロンプトの順番を微調整してテストをしている。
・キムは大手消費財メーカーのコミュニケーション担当マネジャーだ。プレスリリースの作成や、プレスリリースにさまざまなステークホルダーがどのように反応しそうかを検討する際に生成AIを活用している。生成AIに個別のステークホルダーの役割を与え、それぞれの草稿について議論するという双方向の対話を行っている。対話の中でAIに反論し、AIから反論されること。それがキムの経験則だ。
・エイミーは大手テクノロジー企業で財務のリーダーを務めている。自分の部署を社内でサービスを提供する立場から、事業部門の戦略的パートナーへと変えるイニシアティブを推進している。このイニシアティブが求める新しいマインドセットや行動を受け入れる方法について、チームメンバーが理解して熟考できるように手助けする生成AIの質問シーケンスを作成した。
これらのストーリーは、AIとの関わり方について、質問に答えるだけ、クリックしてアウトプットを得るだけ、というレベルをはるかに超えたアプローチを明らかにしている。活発なやり取りが行われており、たとえば以下のチャートのように、人間とAIの双方がアイデアを提供し、対話のステップを一つずつ重ねながら互いの考えを深めていく。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









