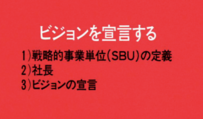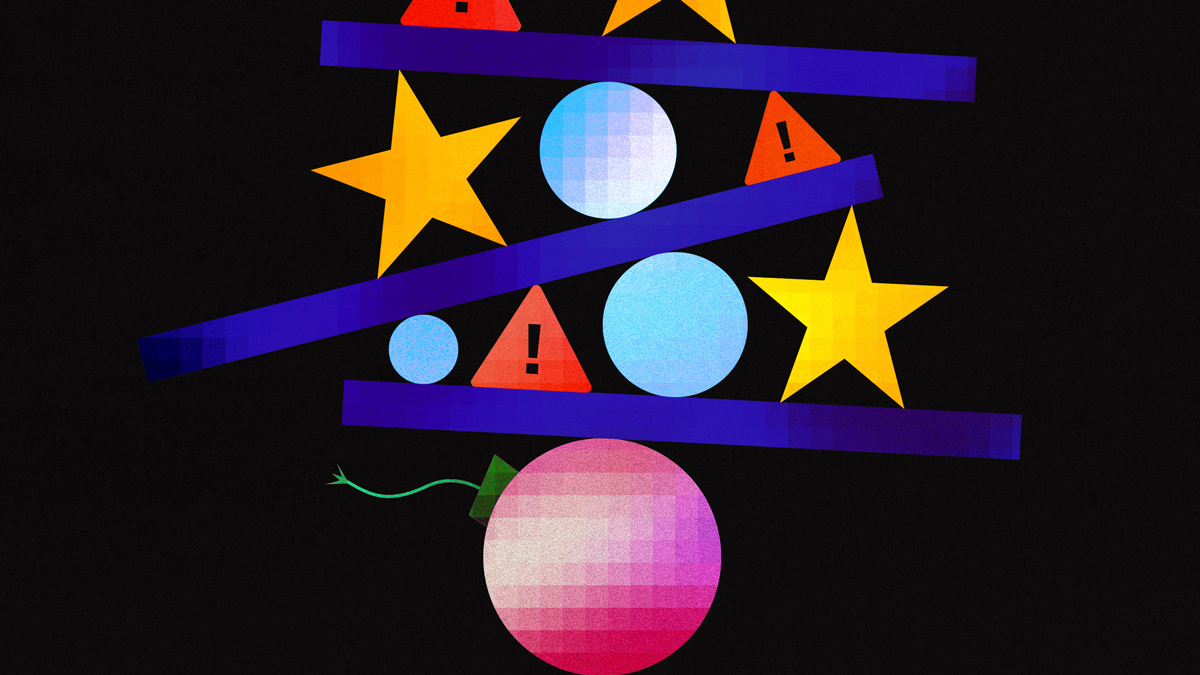
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
AIに対して「楽観」と「警戒」の姿勢を維持するフレームワーク
2024年のある調査によれば、AI製品の概念実証から実用化へとこぎつけた企業は26%に留まり、AIへの投資から大きな価値を生み出した企業はわずか4%にすぎない。野心と現実の間にある溝を埋めるには、AIトランスフォーメーションへの体系的な取り組みが必要とされる。すなわち、AIによる日々の影響を見失うことなく、AIが提起する最も重要な問いを熟考するよう組織を促すようなアプローチである。
リスクはこの上なく大きい。適応できない組織は、AI時代のポラロイドやブロックバスターになるだろう。とはいえ、軽率な実行にも危険が伴う。不動産データベースを運営するジロー(Zillow)が2021年2月、機械学習アルゴリズムで査定された物件の買い取りを始めると発表した時、AIの素晴らしき新世界に踏み込む動きとして広く歓迎された。8カ月後、この新規事業部は約3億ドルの損失を計上し、撤退を余儀なくされた。
AIがもたらすチャンスとリスクには、慎重な考慮と周到な戦略的対応が必要となる。断片的な方策では不十分だ。AI開発のスピードに加え、人間関係や組織文化を変容させるAI特有の能力を踏まえれば、「前例のない不確実性」と「早急な行動の必要性」にバランスよく対応できるフレームワークが求められる。自社の中核的パーパスと人間のステークホルダーを見失わずに継続的な変革を導くことができる、包括的な思考システムが組織には必要だ。
筆者は30年にわたり、フォーチュン2000に属する企業から大規模な政府機関まで、さまざまな組織を対象にデジタル・トランスフォーメーション(DX)を支援してきた。これらの経験を通して、新技術実装の成功を阻む2つのありがちだが対照的な姿勢に何度も遭遇した。変化に対する組織的な抵抗と、戦略的パーパスを欠いた衝動的な技術導入である。現在、AIへのアプローチでも同じ過ちを繰り返している組織が多く見られる。
どちらにしても厄介なこれらの問題を解決する方法は、2つの相互補完的なフレームワークを取り入れて組み合わせ、バランスの取れたAI導入のアプローチを構築することである。
OPENフレームワーク(Outline:アウトライン、Partner:パートナー、Experiment:実験、Navigate:ナビゲート)は、AIの潜在能力を引き出すための4段階から成る体系的プロセスを示し、組織を初期の検証から継続的実行に導く。
CAREフレームワーク(Catastrophize:最悪の事態を想定、Assess:検証、Regulate:統制、Exit:撤退)は上記と並行する形で、イノベーションのプロジェクトとより広範な企業環境の両方において、AI関連のリスクを特定し管理するための構造を示す。それぞれの目的は異なるが、どちらもAIとともに発展させることができるよう柔軟に設計されている。
これらのフレームワークは、AIの潜在能力に対する根本的な楽観と、AIのリスクに対する強い警戒という2つの相互補完的なマインドセットを内包し後押しする。イノベーション管理のプロセスと、ポートフォリオおよび財務管理(PFM)の手法を組み合わせることで、組織は強固な予防措置を維持しながら変革を推進できる。
OPENフレームワーク
OPENフレームワークは、組織のパーパスおよび人間とAIの体験を土台とし、AI導入の成功には技術だけでなく、継続的変革を維持できるリーダーシップと文化も求められることを強調する。プロセスの各フェーズがイノベーション・ポートフォリオの構築に役立ち、アイデア創出から実装、維持管理、そして最終的な撤退に至るまでAIプロジェクトの管理を後押しする。
1. アウトラインの策定
あまりに多くの組織が、AIの一連の取り組みを「この技術で何ができるのか」という問いから始める。「我々のミッションを実現するうえで、この技術はどう役立つのか」ではなく、だ。このアプローチは、実質的な価値を生み出す新たな方法ではなく、技術が先導して問題を後から探し求めるソリューションにつながる。
プロセスの最初に組織のパーパスを再確認し、そのパーパスを最も基本的かつ唯一の成功要件としてすべての意思決定を整合させることで、無限に近いAIの能力に気を取られて横道に逸れるのを防ぐことができる。
企業が最新の技術トレンドで実験したい衝動に駆られ、中核的パーパスへの焦点をいかに見失いやすいかを示す説得力のある事例は、コカ・コーラに見られる。2023年にコカ・コーラは、AIと共同開発した新飲料「Y3000」(西暦3000年がコンセプト)を発売した。そしておそらく意外ではないが、魅力のない味に対して幅広い批判が寄せられた。
2024年にコカ・コーラは再びAIを仕掛けとして利用したが、AIで生成した広告はほとんど誰の心にも響かず、クリスマス広告キャンペーンを成功させてきた同社の長い歴史を傷つけることになった。生成AIの能力を大規模にテストすること自体に一定の価値があったのは間違いないだろう。しかし、不気味の谷からそのまま抜け出てきたような奇妙なイメージを、愛されているブランドと結びつけることは明らかな失敗であった。
ナイキは反対の例として、AI施策をいかに組織のパーパスと密接に整合させることができるかを示している。ナイキのミッションは「すべてのアスリートにインスピレーションとイノベーションをもたらす」ことであり、「体ひとつあれば、誰もがアスリート」であることを強調している。ナイキはAIをマーケティングの仕掛けとして追求するのではなく、このミッションに直接貢献するAIソリューションを実施した。
「ナイキフィット」の技術はAI駆動のコンピュータビジョンを用いて、顧客がスマートフォンによる簡単なスキャンで最適な靴のサイズを見つけられるよう支援する。また、同社の「コンシューマー・ダイレクト・アクセラレーション」戦略は需要検知と在庫最適化のためにAIを活用し、適切な商品が適切な消費者に、適切なタイミングで届くようにしている。
アスリートへの貢献という中核的パーパスを起点にすることで、ナイキは技術のための技術という罠に陥ることを避け、顧客に本物の価値を提供すると同時にブランドを強化するAIのユースケースを開発したのである。
アウトラインフェーズの実践的ガイドライン
・組織のパーパスを再確認する:AI導入の前に自社のミッションを振り返って再確認し、明確性と賛同を確保する。
・現在の知識を検証する:AIに対する組織のリテラシーと準備態勢を検証する。ワークショップを実施して知識の不足を把握し、不足を埋めるためのプログラムを立ち上げる。
・ユースケースのブレインストーミングを行う:部門横断チームを選任し、AIの用途について既成概念に囚われない自由な発想をさせる。
・選別する:組織のパーパスとAIへの準備態勢を尺度にユースケースを検証し、可能性のあるものを選別する。
2. パートナー
AIイノベーション戦略の策定と実施は、多分野にまたがる課題の典型だ。IT部門やR&Dチーム、あるいは最高イノベーション責任者のみに任せておけばよい仕事ではない。AIソリューションで実質的な価値を生む機会を得るためには、これらの部門に加えて他の部門も関与、参加する必要がある。したがって、社内での協働はAI施策を成功させるために不可欠だ。ただし、それでこと足りるケースはめったにない。
社内に優れたケイパビリティを持つ組織であっても、AIの野心を実現するためには、通常は外部と提携関係を築く必要がある。大手テック企業であれば、独自のAIソリューションをゼロから構築できるかもしれない。だがほとんどの組織は、目標達成に必要となる特定の技術の開発と実装を支援できる専門的パートナーと協業しなければならない。これはサードパーティのサービスプロバイダーである場合が多いが、学者、独立系倫理アドバイザー、業界の規制当局なども該当しうる。
しかし、おそらく最も重要なのは人間とAIシステム自体の協働である。この協働によって、AIソリューションを導入するすべての組織の文化が根本から再形成され、仕事上の関係、報告体制、個々の役割が変わることになる。AIの導入がプロセスだけでなく、社内の人間体験全体をどう変革するのかを組織は慎重に考えるべきだ。
AIシステムは人間の能力を拡張するのか、それとも代替するのか。チームのダイナミクスと組織階層にどう影響するのか。AIは裏側で稼働するのか、あるいはユーザーと直接やり取りするのか。人間とAIの協働をめぐるこれらの問いは、どのAI施策においても最初に考慮する必要があり、技術ソリューションを構築してから後付けのように扱うべきではない。
パートナーフェーズの実践的ガイドライン
・社内の専門知識と協働機会をマッピングする:最初に、AI施策に活用できる社内の既存のケイパビリティを特定する。部門横断的な専門知識をマッピングし、適切なチーム間(例:データサイエンス、IT、オペレーション、マーケティング)でシームレスに協働できるようにする。
・外部のパートナーを評価、吟味する:技術ベンダー、学術機関、ニッチなAIスタートアップといった外部の協業者を選ぶことは、ケイパビリティの不足を埋めるために不可欠だ。リーダーは、潜在的パートナーが自社の目標、価値観、オペレーション要件に見合っていることを確認しなければならない。
・提携に向けたガバナンス体制を構築する:AIに関する提携はデータ共有、知的財産(IP)の考慮、協業によるイノベーションを伴うことが多い。これらの複雑性を管理して責任を担保するうえで、明確なガバナンス体制が役立つ。
・AIプロジェクトでは人間中心の設計を優先する:社内用であれ顧客向けであれAI導入においては必ず、人間の体験を設計と展開の中心に据え続ける。これは導入後の定着を図り、望ましい成果を生むために不可欠だ。
3. 実験
AIの可能性に関する自由な発想から実用化へと進むには、入念に構築された実験のアプローチが求められる。多くの組織はアイデア創出から本格展開へといきなり進んでしまう過ちを犯し、高くつく失敗や機会損失を招いている。また、実世界での価値に変換されない概念実証の終わりなきサイクルから抜け出せない組織もある。どちらのやり方もリソースを無駄にする。そして何より、組織の特定の状況下でAIがどのように価値を生み出せるのかについて、重要な学びを得る機会を逸してしまう。
AIの実験を成功させるカギは、実験を一つの検証行為ではなく、一連の学習プロセスとして構築することだ。各実験は、特定のAIソリューションが機能するかどうかをテストするためだけでなく、それがどのように価値を生み出せるのか、どのように拡大展開できるか、人間がどう関わるのかに関する洞察を得るために設計すべきである。
これは技術的な実現可能性のテストを超えて、全社レベルでの実行可能性、および人間にとってどれほど望ましいかを探ることを意味する。そしてAIシステム自体だけでなく、それを支える組織のケイパビリティをテストすることも伴う。さらに、素早く失敗し、素早く学ぶ姿勢も問われる。
実験フェーズの実践的ガイドライン
・コンセプトのプロトタイプを開発する:概念モデリングを用いて、AIが自社の現在のエンタープライズアーキテクチャにどう統合されるのかを視覚化する。カスタマージャーニーをストーリーボード化し、タッチポイントと課題を想定する。
・小さく始める:実現可能性とパフォーマンスのデータを集めるために、限定的に使うパイロット版を展開する。たとえば銀行はAI主導の不正検知を拡大展開する前に、一つの支店でテストするとよい。
・実世界のシナリオを取り入れる:理想的な設定ではなく、実世界の状況と例外を反映した実験を設計する。これにより結果が現実的かつ拡大可能になると同時に、より広範囲での展開において生じうる潜在的課題が明らかになる。
・成果指標を定義する:各実験のKPI(重要業績評価指標)を決める。業務効率や顧客満足度の向上など。
4. ナビゲート
ナビゲートフェーズでは、AI導入に向けて組織を舵取りしながら、より広範な戦略的目標および文化的価値観との整合を図る。技術的要因と人的要因が複雑に絡み合い急激に変化する環境における、継続的な学習と適応を重視する。
AIイノベーションを成功させるカギは、アイデアを運用システムに変換するための入念に設計されたイノベーションパイプラインを通じて、有望なプロジェクトの安定的な流れを維持することにある。プロジェクトは戦略的優先度、リスクレベル、潜在的価値、コスト、実行難易度を反映した総合的なランキングのスコアに基づいて、パイプラインを進んでいく。このランキングは、任意の時点でどのプロジェクトを優先的に進めるべきかを決めるための客観的基準となる。
パイプラインの速度、つまりプロジェクトをどれほど速く進めるのかは、慎重に管理する必要がある。速すぎる場合は準備が整う前にプロジェクトを進めてしまうおそれがあり、遅すぎれば機会損失や競争上の不利益を招きかねない。クオリティゲート(品質を確認するチェックポイント)が適切に適用されるよう徹底しながら、安定的な前進の勢いを維持することが重要だ。これは多くの場合、複数のプロジェクトを異なる段階で並行して進め、停止・開始のプロセスではなく継続的な流れを生み出すことを意味する。
ナビゲートフェーズの実践的ガイドライン
・客観的指標を適用する:リスク、利益、リソース要件、実行難易度、戦略的整合性に基づいてAI施策を分類するイノベーションポートフォリオを作成する。変化する優先順位と市場環境を反映させるために、ポートフォリオを定期的に見直して更新する。
・リソース配分の優先順位をつける:AIプロジェクトの潜在的インパクトと実現可能性に基づいて、リソースを戦略的に配分する。リソースを薄く分散しすぎることを防ぐために、自社の中核的ミッションおよび長期目標と密接に整合する取り組みに焦点を絞る。
・学習の文化を取り入れる:フィードバックループを取り入れることで、反復的な学習を促進する。たとえばルート最適化にAIを利用する物流会社は、ドライバーからのフィードバックをもとにモデルを調整するとよい。
・今後の動向を注視する:AIトレンドの最新状況を常に把握し、変化を予測する。次に来るイノベーションの波に備えるために、R&Dにリソースを配分する。
CAREフレームワーク
AIはすべての組織機能を変革することが期待される一方で、脆弱性も呼び込み、備えができていない組織を弱体化させたり、場合によっては破滅をもたらしたりするおそれがある。たとえば、AI駆動の診断ツールはヘルスケアの提供に革命をもたらしているが、AIシステムはバイアスのかかった訓練データによって、医療診断で致命的ミスを犯す可能性がある。同様に、組織が重要インフラの管理にAIを導入すると、相互接続されたシステムを通じて連鎖するサイバーセキュリティの脅威にさらされる機会が増える。
AIが組織と文化の変革を余儀なくさせ、チームが新たな働き方や考え方への適応を迫られる中で、こうした技術的課題は増幅される。組織は他にも、以下を含むさまざまなリスクに対処しなければならない。
・AI主導のPRの大失敗によって生じうるレピュテーションのリスク
・AIのバイアス、著作権の曖昧性、顧客のプライバシーの問題に起因する法的リスク
・AIが業界全体を急速に再編していく中で生じる、戦略的リスク
これらのリスクは複雑で相互に関連し合うため、特定、検証、軽減に向けた体系的なアプローチが求められる。
CAREフレームワーク(Catastrophize:最悪の事態を想定、Assess:検証、Regulate:統制、Exit:撤退)は、AIのリスク管理に受動的ではなく能動的に臨むものである。従来のリスク管理のアプローチとは異なり、CAREは特にAIリスクの技術的側面と人的側面の両方に対処すべく設計されている。AIの能力の急速な進化、予期せぬ行動が自然に生じる可能性、組織文化の変革、そして技術・オペレーション・人間の要因の複雑な相互関係が考慮されている。このフレームワークは、AIシステムが進化して新たなリスクが生じる中で反復的に適用することができる。
CAREは、AI関連のリスクを特定し管理するための体系的な方法論を組織に提供する。
・技術、オペレーション、戦略の側面にまたがる潜在的リスクを体系的に特定する。これにより包括的なリスク一覧ができ、以降のすべての計画の土台となる。
・リスクが生じる可能性、潜在的影響、組織の対応能力を検証する。これによりリスクの優先順位づけと、効果的なリソース配分が可能になる。
・特定されたリスクを管理するための規制、監視システム、ガバナンス体制を導入する。この段階で、分析を実行可能な予防措置と手順に落とし込む。
・システムをシャットダウンする手順や企業継続計画などを含め、リスク対応のための明確なプロトコルを策定する。これは予防措置が奏功しない場合の重要なセーフティネットになる。
AIが意味するのは、組織の運営方法と価値創出のあり方の根本的な変化である。企業が成功するためには、AIの潜在能力を受け入れると同時に、リスクにも注意するバランスの取れたアプローチを導入しなければならない。
OPENとCAREのような体系的フレームワークを取り入れることで、組織はAI導入に伴う複雑性に対処し、イノベーションを推進しながらレジリエンスを確保することができる。二面的なアプローチによって、AIの変革能力を活用しながら、潜在的な危険に対する予防措置を講じることが可能になる。結局のところAI時代における成功のカギは、戦略的で思慮深く、バランスの取れたアプローチにあるのだ。
"Two Frameworks for Balancing AI Innovation and Risk," HBR.org,March 06, 2025.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)