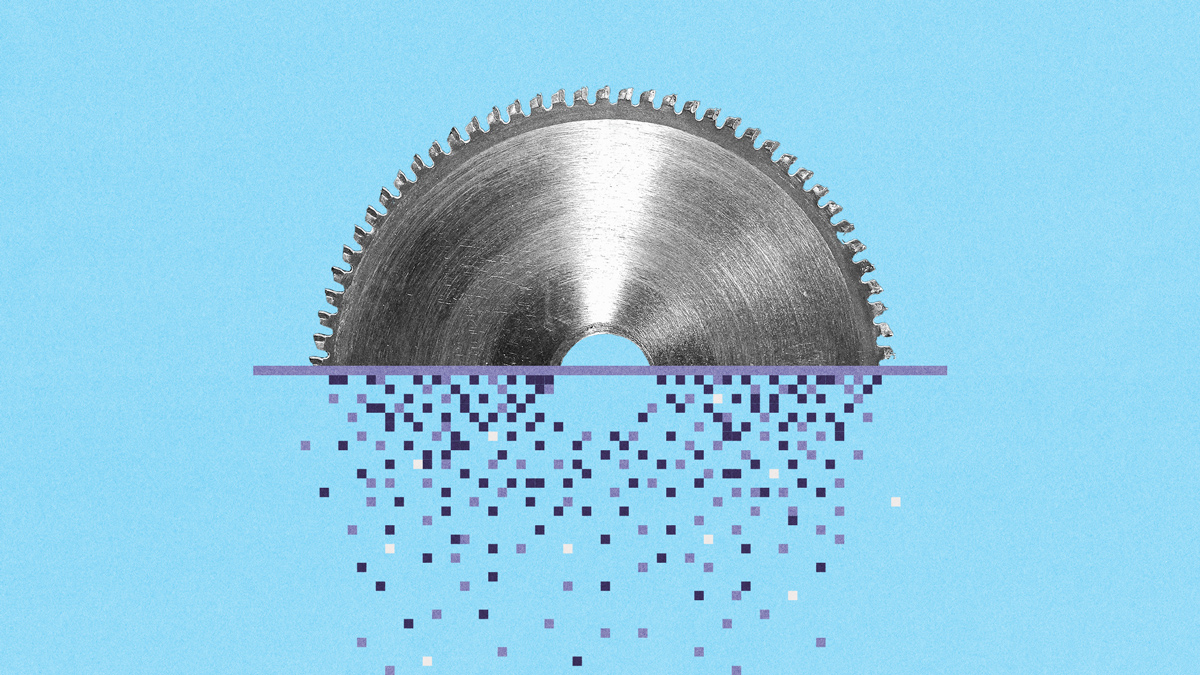
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
15倍のペースで成長する建設技術への投資
建設業界は世界で13兆ドル規模の巨大産業だが、長年にわたって、非効率、遅延、汚職といった問題に悩まされている。従来、こうした問題は避けようがないとされてきた。建設業界は極めて細分化されており、複雑な規制が多いうえに、デジタル化が進んでおらず、バリューチェーン全体を通して労働力不足や計画立案の不備といった課題が山積しているからだ。
しかも、これらの問題は簡単に解決できるものではない。多くの場合、問題の根底には、ステークホルダー間のインセンティブの不一致や透明性の欠如、情報の非対称性、一貫性のない規制や基準といった原因がある。また、問題の多くは、プロジェクトが始動する以前の調達段階で、すでに生じている。
こうした課題に対応すべく、建設業界は設計やエンジニアリングの分野で以前から活用していたAIを、調達プロセスにも取り入れつつある。調達プロセスでのAI活用は、財務面と倫理面の成果に多大な影響をもたらす可能性を秘めており、計画立案のサポート、汚職や談合の検出、施工業者の意思決定の改善などを可能にする。実際、建設技術へのベンチャーキャピタル投資は、ベンチャーキャピタル業界全体の15倍のペースで伸びている。
しかし、AIの利用が広がるにつれて、建設業界には新たな問題も浮上している。コスト削減につながる可能性がある一方で、競争と透明性を損なう手段としても使われかねないという問題である。
建設業界内部や業界関係者のリーダーたち、つまり公共部門の幹部や企業経営者、調達の専門家、インフラ開発関連の政策立案者は、AIツールの活用がもたらす功罪両面を理解する必要がある。効率性の向上、施工業者選定の改良、談合や汚職の検出といったプラス面がある一方で、巧妙な入札操作が可能になるというマイナス面もある。
本稿では、実際の取り組みや新たな研究、現場で検証されたツールに基づき、建設業界の調達分野にAIがもたらすチャンスとリスクを概説する。
プロジェクトオーナーはAIによって効率性を改善できる
複雑で高コストの建設プロジェクト──高速道路、病院、スタジアム、冬季オリンピックのボブスレー競技用トラックのような大型スポーツイベント向けインフラなど──を計画する状況を想像してみよう。インフラ関連省庁の政府職員、地方の公共事業部門の職員、調達担当者、民間セクターのプロジェクトマネジャー、エンジニアリングコンサルタント、建設企業の経営陣は、さまざまな関係者のニーズを調整しながら、安全性と環境基準を遵守し、耐久性を確保しなければならない。
そうしたプロジェクトでは、ほんの些細な見落としでさえも、工期の遅延や予算超過、効率の悪さといった問題につながるおそれがある。信頼できない施工業者や資材価格の高騰、地元住民からの反対、公共調達における汚職などのリスクも、事態をいちだんと複雑にさせる。
AIには、大規模プロジェクトの計画段階の効率性を劇的に向上させる力がある。たとえば、2021年にイタリア・コルティナ・ダンペッツォで開催された国際スキー連盟(FIS)主催のアルペンスキー世界選手権では、政府コミッショナーとマイクロソフトが連携して、デジタルプロジェクト管理システム「オープン・コルティナ・プラットフォーム」を開発した。これは公共事業の運営の効率化を目的としたプラットフォームで、政府機関や施工業者、コンサルタントなど多くの関係者がデータを共有して協働するための一元化されたデジタル環境という機能を有していた。
このプラットフォームのおかげで、競技会場の建設、改修やインフラ改善、その他の関連プロジェクトについて、構造化されたデジタルデータの収集、分析、発信が可能となった。また、ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)とクラウドベースのリソースを統合したことで、プロジェクトのタイムライン、リソース、規制基準の遵守状況をリアルタイムでモニタリング、管理できるようになった(注:筆者の一人であるフランチェスコ・デカローリスは、このプロジェクトで政府コミッショナーのアドバイザーを務めた)。
オープン・コルティナ・プラットフォームの導入は、プロジェクトの実施面にも顕著な改善をもたらした。関係者に最新情報を提供することによって透明性を向上させ、これが市民からの信頼獲得につながったのである。
さらにAIは意思決定プロセスの効率化にも役立っており、おかげで工期の遅れが減り、世界選手権開催前の期限までにプロジェクトを完了させることができた。参照可能な資料には、コスト削減と工期短縮に関する具体的な定量データは記されていなかったが、全体的な評価としては、プロジェクト管理の効率性や関係者間の協働にポジティブな効果があったとされている。
調達機関も、こうしたツールを使って、施工業者の評価、選定の改善に取り組んでいる。たとえば、米国防兵站局(DLA)はAIツールを活用して、サプライヤーの過去の実績や行動を分析し、価格を不当に吊り上げるおそれのある業者を自動的に特定している。英国のクラウン・コマーシャル・サービス(CCS)は、みずからAIを用いて業者を評価、選定するわけではないが、公共部門の組織がサプライヤーを効果的に評価できるよう、必要なツールやフレームワークを提供している。
調達機関に加えて、彼らにプロジェクト資金を提供する開発銀行も、施工業者選定の仕組みを導入するよう調達機関に義務づけている。こうした業者選定の仕組みは、最近のAI研究の成果と重なる面も多い。
欧州復興開発銀行(EBRD)とドイツ復興金融公庫(KfW)は、より健全な競争を促すための試みとして、過剰な業務を抱える業者を入札段階で除外し、その時点での業務量が年間売上高の1.2倍未満の業者のみが入札に参加できるようにした。筆者の一人であるエムラ・エルゲレンが携わった研究によれば、施工業者の業務量が年間売上高の1.2倍から0.7倍に減少すると、その業者の競争力は平均24%向上するという。
AIを活用して汚職や談合を検出する
AIは効率性の改善だけでなく、政府調達の長年の課題である汚職や談合の防止にも役立つ。よく知られている推計として、汚職によって失われる額は、世界全体で年間2.6兆ドル以上、世界のGDPの5%に相当するという数字がある。各国政府はさまざまな検出手法を採用しているが、そのコストは規模や使用ツール、地域、行政機関の能力に応じて大きな幅がある。
汚職や談合の検出に世界全体で投じられている総コストを正確に見積もるのは難しいが、多くの場合、不正の検出は極めて費用対効果の高い対策といえる。たとえば欧州不正対策局(OLAF)は2023年、わずか6000万ユーロの予算で、不正に支出された10億ユーロ以上のEU資金を回収する措置を提案し、さらに2億ユーロ以上の不正支出を未然に防いだ。
この方向に向けてすでに大きな一歩を踏み出している事例が、世界各地にいくつかある。たとえば、英国の競争市場庁(CMA)は、従来のスクリーニングから高度なAI活用への移行を進めている。CMAは2023年に建設会社10社に対して、総額およそ6000万ポンドの制裁金を科した。2024年には学校の屋根工事契約をめぐる談合の調査を開始し、複数の無名企業の施工業者と技術アドバイザーの事務所を強制捜査した。
ブラジルでも、競争当局である経済擁護行政委員会がスクリーニングとデータマイニングのツール「セレブロ・プロジェクト」を利用しており、2021年には42社と43名の個人に対して、官民の調達におけるカルテル疑惑で手続きを開始した。
38カ国が加盟する国際政策フォーラムである経済協力開発機構(OECD)は、談合の検出に用いられるスクリーニング手法を10種類に分類している。そこに含まれる入札価格の分布分析、構造的な変化の検出、市場シェアの安定性のチェックなどの手法にAIモデルを組み合わせ、入札者の特性や過去の行動履歴を分析することで、疑わしいパターン──ありえないほど規則的に価格が設定されている、順番に落札に成功するなど──を特定できる。
ただし、こうした手法を成功させるには、単にアルゴリズムを導入するだけでは不十分だ。公的機関はデータサイエンスの専門家と連携して、組織内部の分析能力の養成に投資をする必要がある。
たとえば、イタリア当局は2022年、企業レベルの汚職リスクに関するデータへのアクセスを、一部の研究者に前例にない形で認めることで、汚職リスクの監視能力を向上させた。その結果、研究者たちはイタリア当局に対し、今後の進め方に関するロードマップを提示し、汚職リスクの正確な評価のために活用すべきAI技術として、ランダムフォレスト・アルゴリズムなど具体的な手法を特定した。また、人間の目では通常無視されるようなデータが、汚職の予測において重要な要素だと判明した点も注目に値する。
談合と戦うためには、AIに関する特定の専門知識も求められる。データ駆動型の手法は、契約を落札させるために採用された特定の入札方式のリスクや特性に応じて、柔軟に調整される必要があるからだ。
調達に関するルールは、談合やカルテル形成が行われる可能性に多大な影響を与える。たとえば、筆者の一人であるデカローリスの研究によって、平均値落札方式は、特に入札価格の調整につながりやすいことが明らかになっている。こうした誘因を理解することで、事前調整された入札を検出する統計モデルを構築できる。
公正性と競争を維持する上でAIツールが有用であることから、政府機関に留まらず、より広範囲でのAI採用が進みつつある。ドイツの国有鉄道会社ドイチェ・バーンなど一部の公営企業では、すでに自社内で内部監視システムの開発を進めている。このアプローチは、AIを調達ガバナンスにうまく統合すれば、不正の摘発と抑止の両面で効果を発揮することを示している。
AI活用による不正検出の改善が、技術的に困難な場合もある。技術面の潜在力を最大限に引き出すために、政策立案者や調達担当者は、汚職や談合の検出にAIを導入する際、以下のようなステップを踏むべきだ。
・さまざまな情報源から構造化されていないデータを集めて、統合的プラットフォームに集約させる。
・データをクレンジングし、利用可能なフォーマットに分類する。
・データを訓練用(たとえば80%)と検証用(たとえば20%)のサンプルに分割する。
・全体のプロセスを担うチームが、必要なスキルセットを有していることを確認する。
・AIモデルと連携できるよう、規制面の枠組みを見直す。
・公的機関でのAIモデルの使用を義務づける。
・他国の公的機関と連携し、知見、データセット、ソフトウェアを共有してモデルの改善を図る。
施工業者が競争力を磨く武器としてAIを活用する
調達のテーブルの向かい側に座る立場である施工業者も、AIを洗練された形で活用し始めている。競合他社の行動を予測したり、入札で勝つために必要な知見を得たりするために、AIを使っているのだ。
施工業者向けのAIツールでは、請負残高、その地域での実績、プロジェクトのタイプについての専門性、地元パートナーとの連携関係といった変数を組み込むことで、入札の複雑性を反映できる。その結果、入札結果を正確に予測できるようになり、その精度は最大で96%にも達している。
全体として、AI技術は以下の3つの重要な意思決定を支援することで、施工業者の業務効率を改善できる。
・入札への参加:入札の勝率をAIが予測することで、施工業者は勝てる見込みのない案件への参加を回避して時間とコストを節約できる。また、勝率の高い案件に参加することで、機会損失を避けることも可能になる。
・勝率の向上:入札の勝率に影響を与える重要な要素を特定することで、時間と資金と労力を正しい方向に投資できる。他の施工業者との連携も、その一例だ。
・マークアップの規模:競合他社の特徴を分析して行動パターンを予測することで、入札の勝率を大きく損なうことなく、利益率を高められるよう、入札戦略を調整できる。
施工業者の意思決定におけるAIの貢献が如実に表れたのが、パキスタン・カラチの領事館プロジェクトだ。筆者らの一人であるエルゲレンによれば、自身が経営幹部だったトルコのアルゲ・コンストラクションは当初、このプロジェクトへの入札に消極的だった。だが、カナダのフラックス・コンサルティングが開発したAI入札モデルの予測によって、あるスペイン企業(同じ発注者の類似の案件を受けた実績があった)とジョイントベンチャーを組めば勝率を大きく高められることがわかったため、入札に参加することにした。さらに、このAIモデルを用いてマークアップの調整も行ったところ、同社のJVが最も低価格で入札できた。
施工業者によるAI活用は入札戦略だけに留まらない。正確なコスト予測を作成するツールとして、オートデスク・プロエスト、エディファイ、ヘビービッド、トリンブル、ピンポイント、ビルドエグザクト、セージなどが挙げられる。また、複雑な入札書類の作成、管理、提出を支援する専用ツールには、オートデスク・ビルディングコネクテッド、トランクトゥールズ、プロコア、パンテラ、スマートビッド、CMICなどがある。
複数の言語が使用される入札に参加するグローバル企業が近年、有用なツールとして注目しているのが大規模言語モデル(LLM)だ。AIによる翻訳と文書解析機能を通して、企業は入札関連文書や技術仕様、法的な要件をこれまでよりも迅速かつ正確に理解できるようになった。
重要なのは、こうしたツールは主に入札準備のサポートとして社内で使われており、最終的な提案書の作成や提出には使われていないという点だ。正確性と法令遵守、文書を読む相手に適した内容を担保するために、最終的な書類はすべて、法務チームや技術担当者が精査している。
AIが競争と透明性を阻害する
建設プロセスにおいて、AIは調達側と受注側の双方の効率化に資すると期待されるが、一方で負の側面も存在する。本来、公平性と効率性をもたらすはずのAIツールが、逆に入札操作や競合の排除のために悪用されるおそれがある。
特に、類似の形式で頻繁に行われる調達では、共謀する企業同士が順番に落札する戦略や、ダミー会社を使って入札し、競争が存在するよう見せかける戦略に、AIが悪用されるケースがある。共謀行為にAIが用いられることで、当局による不正検出は一段と困難になる。
AIのリスクは共謀の問題だけに留まらない。アルゴリズムへの過度の依存は、意思決定の不透明化や競争の低下を引き起こし、AIツールにアクセスできない中小企業に新たな障壁をもたらす可能性がある。ただし、今後、技術コストが低下していけば、AIツールも手の届きやすい価格になるかもしれない。
BIMとAIの統合も、異なるフォーマットの非互換性やセキュリティ上の懸念によって妨げられるおそれがある。機密性の高い建設データの共有にはリスクが伴うからである。
建設業界での調達においてAIのポテンシャルを最大限に引き出すためには、責任ある導入と適切な監督体制が不可欠だ。AIは効率性と透明性の面で前例のないチャンスをもたらすが、調達の最終的な判断は人間に委ねられるよう、規制の枠組みを整備する必要がある。規制当局が、統計モデルの異常値だけを根拠に、処罰を課すことがあってはならない。
調達担当者にとっての重要な気づきは、調達関連の規制が市場のインセンティブに及ぼす影響を慎重に評価すべきという点だ。オークションの形式、透明性の要件、資格基準など、入札手続きの設計次第で、公正な競争が促されることもあれば、談合や協調の余地を生むこともある。健全で信頼性の高い調達システムを構築するうえでは、こうした力学を理解することが不可欠だ。
政策決定者と企業経営者、調達担当者は、イノベーションと包摂性、効率と誠実さのバランスを目指す必要がある。AIは単に新たなツールというだけではなく、建設業界の調達ルールそのものを再定義する存在だ。賢く活用すれば、業界全体を前進させられるが、管理されないまま放置すれば、長年の課題を新たな形式で固定化してしまうおそれもある。
"How the Construction Sector Is Using AI to Cut Waste and Fraud," HBR.org, April 16, 2025.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









