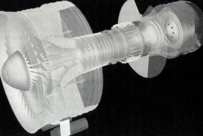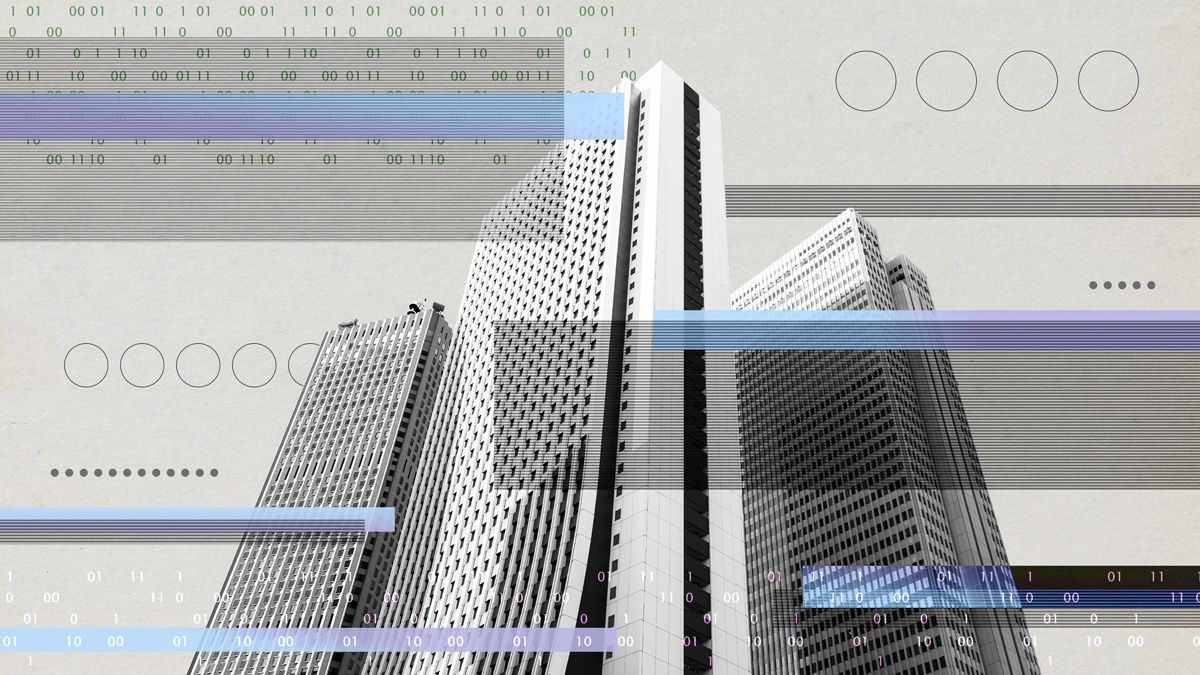
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
AIが社会の不平等を悪化させる可能性
AIが飛躍的進歩を遂げ、世の中の話題の中心を占めるようになって、すでに2年以上が経つ。メディアは、AIが社会に革命的な変化をもたらすと喧伝し続けている。しかし、AIが社会と経済に脆弱性を生み出すのではないかと不安視する声が根強く存在することも事実だ。
マサチューセッツ工科大学(MIT)研究所教授のダロン・アセモグルなど、ノーベル賞受賞者たちは、AIが所得格差を悪化させるのではないかと懸念している。また、米国の一般の労働者たちも、AIが雇用に及ぼす影響に不安を募らせている。実際、AIの性能が以前より向上しているにもかかわらず、AIに対する人々の信頼はむしろ低下し続けている。
いまAIに対する不安が広がっている大きな要因は、筆者が「AI不平等」(artificial inequality)と呼ぶ構造的な現象にある。AIの影響により、社会の不平等がいっそう悪化することが恐れられているのだ。そのような現象が起きるのは、AIの進歩に伴い、社会的・経済的な機会と成果が一部の層にばかり集中し、それ以外の層の機会と成果が奪われることに原因がある。
残念ながら、AI不平等は極めて複雑な現象であり、是正することは容易でない。筆者は、AIがさまざまな社会問題──雇用の喪失、気候変動の悪化、AIの恩恵を受ける度合いの地域格差など──に及ぼす影響を調べてみた。すると、AI不平等の拡大に寄与する6種類の「格差」が見えてきた。データの格差、所得の格差、利用の格差、グローバルな格差、業種による格差、エネルギーに関する格差である。
これらの要素は互いに影響を及ぼし合い、格差をさらに増幅させることが多い。たとえば、データのバイアスによって不利な状況に陥りやすい人は、AIを用いた生産性ツールの恩恵に浴しにくく、AIの普及に伴うエネルギーコストの上昇により打撃を受けやすい。
この問題の最も自然な解決策は、政府の規制と政策的介入だが、少なくとも差し当たりは、そのような解決策が優先的に実践されるとは考えにくい。AIに関して世界の先頭を走っている国である米国では、トランプ政権が規制緩和を推進しようとしており、規制の導入は見送られそうだ。すでに強力な規制の枠組みを持っている欧州連合(EU)も、ユーザーの保護よりも「行動」と「機会」を優先させる意向を示唆している。
しかし、明るい材料もある。企業のリーダーたちが行動を起こせば、6つの領域のすべてでAI不平等のリスクを緩和できるのだ。AI不平等は、AI開発企業と導入企業の両方に壊滅的な打撃を及ぼす可能性がある。したがって、企業はできる限りの対策を講じるべきだ。
企業のリーダーがAI不平等に関して取ることのできる対策は3種類ある。
・テクノロジーを通じた対策:新しいテクノロジーは、新しい問題を生み出すだけでなく、問題を解決する役に立つ場合もある。企業は、自社のテクノロジーがどのように機能するのか、どのような点でうまくいかない可能性があるのか、自社が責任を持って目標を達成するうえでどのような新しいツールが役立つ可能性があるのかを知っておく必要がある。
・機関を通じた対策:企業は、こうしたことをすべて独力で行う必要はない。サードパーティの団体とパートナーになることもできるし、社外の方法論や枠組みを利用して学習し、適応していくこともできる。
・市場を通じた対策:ほとんどの企業は、新しい市場をつくり出したり、市場のあり方を変えたりすることはできないかもしれないが、ユーザーの需要の動向についてのシグナルを読み取ることはできる。新しいパラダイムの中で何に目を向けるべきかがわかっていれば、適切なソリューションとビジネスモデルを見出しやすい。
AI不平等には、いくつもの格差が影響を及ぼしており、企業が問題の全体を是正する能力は限られているかもしれない。しかし、それぞれの格差を個別に検討すると、自社が対策を実行できる領域が見えてくる可能性もある。
以下では、6つの格差を一つひとつ順番に見ていく。
1. データの格差
AIは、数学とデータの組み合わせだ。その点、数学は差別をしないかもしれないが、データは差別をする。データにはしばしば、バイアスが入り込むからだ。情報が不完全だったり、まったくの虚偽だったりする場合がある。
データの格差は、極めて重大な結果を招く可能性がある。たとえば、アルゴリズムを利用した胸部X線診断システムは、有色人種と女性の患者の診断精度が白人男性より一貫して低い。また、ある研究によると、アルゴリズムを用いて住宅ローン審査を行う場合、シカゴのローン会社が黒人のローン申請者を却下する確率は、似たような条件の白人申請者の1.5倍に達した。別の研究によると、テキサス州ウェイコでは、中南米系のローン申請者が却下される確率は、似たような条件の白人申請者の2倍に達した。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)