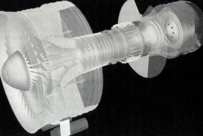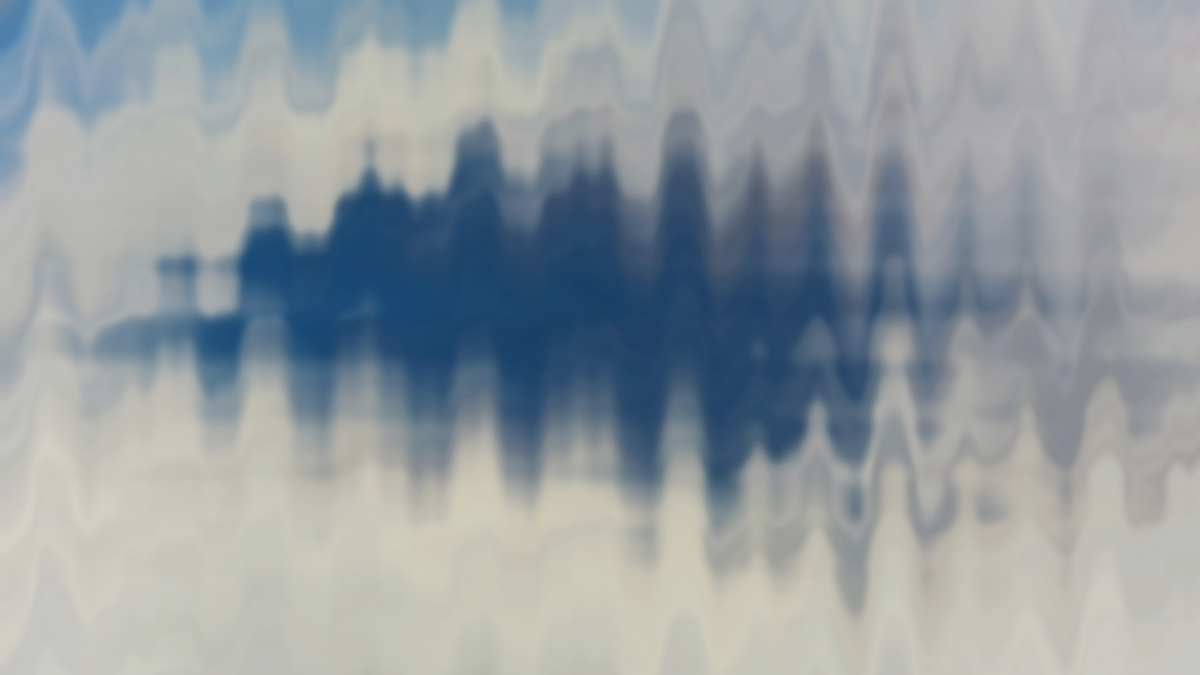
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
SaaS型ソフトウェアからAIへ
2011年、ベンチャーキャピタリストのマーク・アンドリーセンは「ソフトウェアが世界を飲み込む」と宣言し、ソフトウェア主導の企業があらゆる業界を一変させると論じた。2010年代がデジタル・トランスフォーメーション(DX)の時代となった理由も、この見解で説明できる。既存の企業も新興企業も、ワークフローを自動化し、デジタルネイティブな新規参入企業に対抗するために、エンタープライズソフトウェアに巨額の投資を行ったのだ。
現在、企業は似たような転換点に立たされている。今回の主役は生成AI。その影響は業界を破壊するだけでなく、前回のDXを巻き起こしたソフトウェアそのものをも破壊するだろう。エンタープライズソフトウェア製品によって無数の企業を支えてきたマイクロソフトCEOのサティア・ナデラでさえ、生成AIへの危機感を明言している。
生成AIによる破壊的変化が波及する範囲はソフトウェア企業に留まらない。大半の大手企業は、売上げの記録、財務結果の算出、給与支払いなどの基幹業務で多様なエンタープライズシステムを利用している。何千人ものIT専門家がそうしたソフトウェアを支えており、何百万人もの従業員が日々の業務でそれを活用している。
SaaS型ソフトウェアからAIへの移行が進めば、こうした業務の多くが劇的に変化し、一部は完全に消え去るだろう。シニアリーダーは、そうした転換点をうまく乗り切れるよう組織を導くという難題に直面している。
「ワークフローのシステム」から「ワークのシステム」へ
セールスフォースやワークデイなど主要なエンタープライズプラットフォームの多くは、組織を「ワークフローのシステム」と捉えている。ワークフローとは、社員の採用やオンボーディングから、新規顧客の開拓、既存顧客との関係拡大まで、組織があらゆる業務を遂行するためのプロセスを意味する。
こうしたワークフローは情報処理システムとして分析され、そのシステムによってデータの流れがマッピングされ、構造化された分析が自動で行われる。そしてユーザーは、あらかじめ設定された枠組みの中で情報を入力・確認・処理する。
たとえばワークデイでは、従業員の記録を中心にデータが構成されており、それに基づいて給与処理や業績評価、研修の管理、福利厚生の運用が行われる。「新規採用者の追加」や「給与振込口座の変更」のタスクを実行する際には、この複雑なソフトウェアシステム上で、ユーザーインターフェースに組み込まれた明確なステップに沿って操作する。
同様に、セールスフォースのようなCRM(顧客関係管理)システムでは、営業のステージがいくつかに分けられており、営業チームはそのステージに沿って、見込み顧客を分類したり、ステータスを更新したり、次に取るべきアクションを実行したりする。時間が経つにつれて、こうしたCRMのワークフローは日々の業務の中に組み込まれていく。
一方、生成AIを活用した「ワークのシステム」は、組織を目標志向のタスク環境と捉えている。このアプローチでは、あらゆるワークフローのあらゆるステップを詳細にマッピングする代わりに、ハーバード大学のクレイトン・クリステンセンが提唱したように、「達成すべきジョブ」を起点として、必要なアクションを推論していく。
内部では、多様なデータ(構造化されているものも、されていないものもある)からのシグナルをAIが取り込み、目標達成に必要なタスクを動的に組み立てていく。あらかじめ決められた画面やフォームに沿った手順は存在せず、むしろシステムが常に例外から学び、推奨内容を取り入れていく。そして、人間が作成したスクリプトを用いることなく、部署間の機能横断的な連携を創り出す。
つまりAIが、構造化されていないインプットを、構造化された行動に変換してくれる。その結果、ユーザーはワークフローの構造を理解する必要がなくなり、求める成果を実現することだけに集中できる。
たとえばCRMにおいては、AIシステムがメール、通話記録、提案書の修正履歴などのシグナルを解析し、見込み顧客のステータスを自動的に更新する。過去の成果から学習して、基盤となるプロセスを改良するため、手作業のデータ入力が不要となり、プロセスの遅延を減らせる。
同様に、かつてはデータアナリストが構造化照会言語(SQL)に変換して対応していたような複雑なクエリについても、いまではシンプルな対話形式のプロンプトで事足りる。たとえば「ドイツで今四半期に10万ドル超の成約に至った見込み顧客は何件か」というクエリがあったとしよう。生成AIシステムは構造化されていないインプットを解析し、必要なデータベースクエリを生成し、即座に回答を出すことができる。
この転換が重要な理由:ワークフローソフトウェアとAIシステムの違い
この変革はただの漸進的な変化ではない。業務の設計方法と実行方法の関係そのものが再定義されるのである。
従来のワークフローソフトウェアは、工場の組立ラインとの共通点が多い。
・逐次的:タスクは順序立てられたステップとして定義される。
・明示的:あらゆるアクションが事前に定義され、承認される必要がある。
・硬直的:プロセスを調整する際にはデータモデルやインターフェースの再設計が必要になる。
・専門家への依存:効果的に運用するには、ワークフローとソフトウェアの双方についての深い知識が求められる。
これに対して、AIを活用した「ワークのシステム」は、反応的な有機体に近い。
・流動的:プロセスは目的や状況に応じて動的に生成される。
・暗示的:ワークフローはデータのパターンやユーザーの意図から推測される。
・適応的:システムが例外から学び、プロセスを継続的に改良していく。
・ユーザー中心:インターフェースは自然言語や直感的な操作に基づいている。
たとえば、新入社員のオンボーディングを行う際、AI駆動の人事システムなら「ジェーン・ドウのオンボーディングを開始して」という指示だけで十分かもしれない。指示を受けたシステムは、オファーレターを作成し、オリエンテーションの日程を調整し、端末を手配し、福利厚生への登録を行う。人間の介入なしで、複数のバックエンドシステムにまたがる調整を実行できるのだ。
要するに、従来型のソフトウェアが過去の導入プロジェクトから得られたベストプラクティスをコード化したものである一方、生成AIはリアルタイムでベストプラクティスを生み出し、成果を継続的に最適化していくのである。
この転換はすでに始まっている
こうした変革は仮定の話ではない。従来型のソフトウェアシステムへの依存を減らす方向に舵を切る企業が日々増え続けている。例を挙げよう。
・8500万人の顧客を有するスウェーデンのフィンテック企業クラーナは2024年、セールスフォースやワークデイなど主要なSaaSプロバイダーの使用を停止し、社内のAI駆動型記録システムに移行する計画を発表した。同社はまず、Neo4jでエンタープライズデータの統合データベースを構築し、次に自社のAIソフトウェアスタックを活用して、LLM駆動のツールを用いた専用のアプリケーションを開発した。
・世界的な重工業企業シーメンスは、従来の企業資源計画(ERP)システムの使用を止め、自社開発の対話型AIボットを採用。このAIボットを用いて、製品ライフサイクル管理プラットフォームにクエリを投げかけ、サプライチェーンの問題やコスト超過について調査している。
・メイヨー・クリニックなどの先進的な医療機関では、生成AIツールを試験的に導入し、患者の病歴の統合やケアプランの考案など、医師による臨床資料の作成を支援している。
・JPモルガンなどの金融機関では、リサーチアナリストに対し、過去から現在に至る膨大な財務データを検索し、完成形に近い調査報告書を自動作成してくれるツールを提供している。
・日立製作所のグローバル部門では人事部がエマ・アンリミテッドのエージェント型プラットフォームを導入。4つの事業部門にまたがるシェアードサービスの運用効率を70%向上させた。このソリューションは、12万人の従業員を対象に8週間で構想・導入された。
どの業界でも、早いタイミングで舵を切った企業は20~30%の効率向上を実現している。また、硬直化した全社的なソフトウェアシステムの代わりに、あるいはそれを補完する形で、ユーザー主導の柔軟な生成AIツールを取り入れることで、サービスの拡大も進めている。
こうした破壊的変革は強大な影響力を秘めている。2023年、エンタープライズソフトウェアへの支出は世界全体で9130億ドルに達し、前年比12.4%の増加を記録した。ベンチャーキャピタルはこれまでにSaaSスタートアップに数十億ドル規模の投資をしてきたが、現在では老舗のベンダーも新興のSaaS企業もそろって存続の危機に立たされている(開示:本稿の筆者2名はいずれも、AIおよびエンタープライズソフトウェア企業への投資を行うベンチャーキャピタルとの関係を有している)。
最初にこうした変革の標的となるのは、経費精算、求人の掲載、応募者の追跡、ITサポート、営業報酬など、目的が単一で、処理件数の多い業務だ。
経費精算を例に取って、違いを見てみよう。
・現状:従業員は金額、日付、カテゴリーなど数十の項目に手動で入力したり、プルダウンメニューから選択したりして、承認ルートを通じて報告書を提出する。いずれの段階でも、手間やミス、遅延のリスクがある。
・今後:従業員はレシートの写真を撮影して、AIに報告書をつくるよう依頼する。ポリシーに違反していなければ、システムが品目を抽出し、カレンダーの予定と照らし合わせて経費を検証し、ポリシールールを確認し、自動で承認し、払い戻しの処理をする。製造計画や財務予測、見込み顧客の精査のような複雑な領域でも、今後5年以内にこうした機能が実現する。
変革が示唆するものと、リーダーの対応
生成AIの登場による「ワークフローのシステム」から「ワークのシステム」への移行は、リーダーにとって重大な意味を持つ。このAI変革を成功させるために、リーダーは以下のような重要項目に注力する必要がある。
ガバナンスとリスク管理
頑強なデータガバナンス体制を構築し、データの品質と安全性、出所、コンプライアンスを確保する必要がある。そして、AIモデルの劣化、バイアス、規制遵守について継続的なモニタリングを実施しよう。また、人間とAIが協働する際には、引き継ぎのタイミング、説明責任、監督体制を明確に定めることで、システムへの信頼性を維持し、ミスを軽減することが重要だ。導入初期にガバナンスを確立することで、AIシステムへの信頼が生まれ、この時期に付き物の課題を乗り越えやすくなる。
組織としての準備
ワークフロー関連のソフトウェアの導入・カスタマイズ・保守をメインとする職種は、形が変わるか、縮小することになると認識しよう。人事、財務、ITなどの管理部門は縮小、または再編され、イノベーションや戦略的業務に人材が回される。ソフトウェアサービスを主軸とするサプライヤーや投資家、地域経済も、こうした変化の影響を受けるだろう。AIシステムへの移行を実現し、加速させるためには、特に、影響を受け、適応を求められる人々に対するチェンジ・マネジメントを慎重に進めるべきだ。
戦略的対応
エンタープライズソフトウェア業界を牽引してきた既存企業は、一連の変革を積極的に主導しない限り、台頭する破壊的スタートアップに優位性を奪われる。既存企業はその点を理解し、競争力の維持に向けて以下の取り組みを進めるべきだ。
(1)相互運用性を重視する:オープンAPIとモジュール型アーキテクチャによって、従来型のシステムと新たなAIエージェントを統合した分散型AIエコシステムを構築する。
(2)ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンスを対話型ワークフローに合うよう再設計する:従来のフォーム入力型のユーザーインターフェースを、自然言語や音声のインターフェースに置き換え、導入の障壁を引き下げる。
(3)段階的なAI導入ルートを提供する:完全自律型エージェント、人間との協働型、ハイブリッド型など、顧客がコントロールとリスクのバランスを調整できるような選択肢を用意する。
(4)「達成すべきジョブ」にフォーカスする:自動化された硬直的なプロセスから、測定可能な成果の実現にシフトし、顧客が目的を明確に示し、AIが最適なワークフローを導き出せるようサポートする。
統一性のあるリーダーシップアジェンダの元で、ガバナンス、組織としての準備、戦略的対応を一体化させることで、従来型の企業は不確実性をチャンスに変え、AI駆動型の職場革命の最前線を走ることができる。
* * *
生成AIの台頭は、エンタープライズITのコストと複雑性を軽減する千載一遇のチャンスだ。組織は硬直的なワークフローから解放されて、業務の形を一から再構築できる。
リーダーは視野を広げる必要がある。既存のシステムを強化するだけに留まらず、AIエージェントと人間がシームレスに協働する、柔軟で組み合わせ自在な職場を構想すべきだ。過去15年間にソフトウェアが世界を飲み込んできたのと同じように、今度は生成AIがソフトウェア自体を変革し、今後数十年間にわたる新たな働き方を再定義していくのである。
"How Gen AI Could Disrupt SaaS - and Change the Companies That Use it," HBR.org, May 21, 2025.








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)