
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「世界のフラット化」を信じ込まされていないか
ニューヨーク・タイムズ紙のコラムニスト、トーマス・フリードマンは「世界はフラットだ」と提唱した(注1)。テクノロジーの進歩のおかげで、グローバルな活動の舞台は均一化した。地球上のどこに住んでいようとも、だれもが手を伸ばせば報酬を得られ、活動に参加できる。「フラットな世界では、どの国にいてもイノベーション競争に参加できる」とフリードマンは自著『フラット化する世界』で述べている。
これは長く語られてきた古い話の延長線上にある発想だ。交易とテクノロジーの均一化が地理的条件を無意味なものにしたという考えを、批評家たちは20世紀の始まり以来、繰り返し主張してきた。電信や電話、車や飛行機の発明に始まり、パーソナル・コンピュータやインターネットの普及によって、物理的な距離の経済的重要性は徐々に失われていると、多くの者が主張してきた。
にもかかわらず、こうした旧態依然とした主張がいまだになされているのだ。たとえばエコノミスト誌は1995年、「物理的な距離概念の消滅」を表紙で大々的に謳った。その誌面では、ジャーナリストのフランシス・ケアンクロスが「テクノロジーと通信会社の競争のおかげで、物理的な距離はじきに問題ではなくなる」と論じた。四年後、同誌は「物理的距離の克服」を誇らしげに宣言し、「ワイヤレス革命が地理的条件の絶対権力を、より完全なかたちで終わらせようとしている」とした(注2)。
グローバル化の進む世界においては、新しいコミュニケーション技術は「巨大な地ならし機」となることが明らかになっている。私たちが何の迷いもなく「自分の望む場所に住みたい」と考えるようになったのも、「地理的条件はもはや問題ではない」と信じ込まされた結果とも言える。
私たちは理論上、どこでも自由に暮らすことができる。しかしその一方で、ある特定の場所では圧倒的に多くのメリットを享受できる。これがまさにグローバル経済の現実なのである。
世界が決してフラットではないことを証明する
カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の経済学者、エドワード・リーマーは、『フラット化する世界』の書評でこのように記した。「知性、身体能力や敏捷性、外見、両親の庇護を含めて、人間には生まれながらにして格差がある。そして住んでいる場所もその重要な一つである」。この衝撃的なレビューは、一流の学術誌ジャーナル・オブ・エコノミック・リタラチャー誌に掲載された(注3)。
私は、過去10年間の大半を費やし、グローバル経済における地理的条件の重要性について、大量の研究論文や統計上の証拠、反証などをくまなく調べあげた(調査結果は、以後の本書『クリエイティブ都市論』の2つの章で詳しく述べる)。
世界がフラット化しているという仮説は大きな問題をはらんでいると思われる。フラット化する世界説の問題点は世界各地の都市の爆発的な成長を見落としていることにある。大都市圏への人口の集中は顕著で、いますぐに沈静化するとはとうてい思えない。1800年には全世界の人口に占める都市人口の割合はたった3%だったが、1900年には14%、1950年までには30%に達した。そして今日では50%を超え、先進国では人口の4分の3が都市部に住んでいる(注4)。
とはいえ人口の増加率だけでは、世界が決してフラットではないことを証明しきれない。そこで本書『クリエイティブ都市論』第2章では、経済活動やイノベーションが特定の地域に偏って集中する様子を、世界地図に細かく書き込んでみたいと思う。
純粋に経済力と最先端のイノベーションの面から考察すると、現代のグローバル経済を牽引しているのは、きわめて少数の地域である。そのうえ、グローバル経済の舞台がフラット化する兆候はまったく見られない。スパイキーな世界の山頂に位置する地域、つまり世界経済をリードする都市や地域は、かつてないほどの発展を遂げている。その一方で、スパイキーな世界の谷底にあたる地域、つまり何らかの経済活動が認められるとしても、発展の兆しが見られない大方の地域は、衰退しているのだ。
グローバリゼーションの影響力はたしかに絶大だ。新興国や開発途上国も世界経済に参加するチャンスを得たが、すべての国がその恩恵に与ったわけではない。イノベーションと経済的資源の集中は、高いレベルで続いている。結果として、世界経済の舞台で本当に発展可能な地域は、ごく一部に限られたままだ。
実際、グローバリゼーションには2つの側面がある。まず表立った側面として、単純労働による製造業やサービス業(たとえば電話のコールセンター業)といった、旧来型の経済機能の地理的な分散である。他方、表面からは見えにくいが、イノベーション、デザイン、金融、メディアなどの付加価値のより高い経済活動に対するニーズの増加である。これらは、いずれも比較的限られた地域に集中している。
フリードマンをはじめとする批評家は、グローバリゼーションによる経済活動の分散化を強調する一方、集積化の実態を見落としがちである。しかし先見の明のある者は、この「地理的条件のパラドックス」に気づいている。ハーバード・ビジネス・スクールの教授で、競争戦略論で知られるマイケル・ポーターは2006年8月のビジネスウィーク誌で「地理的条件はいまも重要だ」と述べている。「世の中の移動性が高まるにつれて、地理的条件はいっそう決定的な意味を持つ。この事実に、多くの識者が足下をすくわれてきた」と彼は付け加えている(注5)。
そもそもの間違いは、グローバリゼーションを二者択一の理論でとらえようとしたところにある。私たちを取り巻くグローバル化の新たな現実を知る手がかりは、世界がフラットであると同時に、スパイキーである実態を理解することにある。すなわち経済活動は分散する一方で、集積しているのだ。
* * *
本連載は今回で最終回である。『クリエイティブ都市論』では、「クリエイティブ・クラス」という新たな経済の支配階級にとって、いまや自己実現の重要な手段となっている居住地の選択について、独自の経済分析、性格心理学の知見を使って実践的に解説している。詳しくはぜひ本書で確認していただきたい。
【関連記事】
リチャード・フロリダらの新たな記事>>ナレッジ・キャンパス:知識経済に生産性を最大化する都市モデル――東京のCBDの発展から読み解く
[著者]リチャード・フロリダ
[翻訳者]井口典夫
[内容紹介]「クリエイティブ・クラス」という新たな経済の支配階級の動向から、グローバル経済における地域間競争の変質を読み取り、世界中から注目を浴びた都市経済学者リチャード・フロリダ。2008年に発表された本書は、クリエイティブ・クラスが主導する経済において、先端的な経済発展はメガ地域に集中し、相似形になっていく世界都市の現実と近未来像を描いている。さらに、クリエイティブ・クラスにとって、いまや自己実現の重要な手段となっている居住地の選択について、独自の経済分析、性格心理学の知見を使って実践的に解説する。
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
【注】
1)Thomas Friedman, The World Is Flat, Farrar, Straus and Giroux, 2005(邦訳『フラット化する世界』上下、日本経済新聞社、2006年).
2)Frances Cairncross,“The Death of Distance,”The Economist 336, 7934, September 30, 1995より。のちにThe Death of Distance, Harvard Business School Press, 2001 (first ed., 1997)(邦訳『国境なき世界』トッパン、1998年)として出版されている。さらに“Conquest of Location,”The Economist, October 7, 1999がある。
3)Edward E. Leamer,“A Flat World, A Level Playing Field, a Small World After All or None of the Above? Review of Thomas L. Friedman, The World Is Flat,” Journal of Economic Literature 45, 1, 2007, pp. 83-126.
4)都市化現象のデータは“World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database,”Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations 2007による。esa.un.org/unppで入手可能。
5)“Q&A with Michael Porter,”Business Week, August 21, 2006. www.businessweek.com/magazine/content/06_34/b3998460.htm.

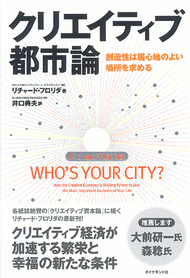




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









