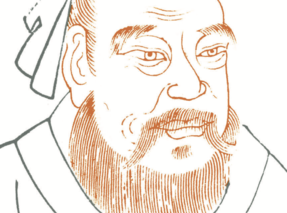-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
開けられた竹のカーテン
だれでもかまわない。世界を相手にビジネスしているマネジャーに尋ねてみるとよい。共産主義国家である中国が、この25年間、いかに変貌してきたか、熱く語ってくれることだろう。いまの中国は、地上というより、むしろ天上に存在するビジネス界かのようだ。何しろその市場成長率は世界最高にある。
1978年から2002年までの間、中国のGDP成長率は年平均9.3%(アメリカの実に3倍)、1人当たり国民所得も、年231ドルから940ドルと4倍以上に伸びている。人口は13億人、すなわち世界最多の消費者を抱えており、ここに何とか割って入りたいという企業がほとんどのはずだ。
78年、中国政府が「竹のカーテン」を取り払い始めて以来、相当数の多国籍企業が中国に進出してきた。そして2001年12月、中国がWTO(世界貿易機関)に加盟すると、想像を超えるほどの可能性を秘めた中国市場を目指して、ますます外国企業が殺到するようになった。
しかしほとんどの外国企業が、中国を近視眼的に見ている。市場としての可能性、低賃金の労働力ばかりに目を奪われ、生産施設の建設や製品の売り込みしか頭になかった。みな、大きな流れを見落としていた。そう、中国企業は強力なライバルとして台頭しているのだ。それも中国国内にとどまらず、グローバルな市場で──。
すでにいくつもの中国企業が力をつけて、生産におけるコスト構造を一変させるだけでは満足できない段階に突入している。アジアで、ヨーロッパで、アメリカで、中国発のブランドが、伝統も規模も資金力も勝る既存企業から、じわじわとシェアを奪っている。
たとえば、青島(チンタオ)を本拠とする海爾(ハイアール)グループは、家電機器メーカーとして世界最大級にまで成長しており、2002年、アメリカ市場における同社の小型冷蔵庫のシェアは全体の50%近くに及んでいる。
広州の格蘭仕(ギャランツ)は、すでに世界の電子レンジの3分の1を生産しており、2002年、ヨーロッパ市場における格蘭仕ブランドが40%のシェアを占めている。また中国国際海運集装箱(コンテナ)(CIMC:China International Marine Containers)も、同じく2002年に冷凍コンテナの世界シェアを40%台に乗せた。
海外市場におけるこれらの企業の浸透スピードから考えると、中国ブランドが遠からず、さまざまな業界でグローバル市場を席巻する可能性がある。ではなぜ、中国ブランドは、各国企業のアンテナに引っかかってこないのだろうか。