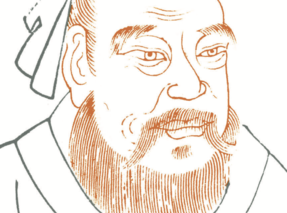-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
ハングリーで勤勉な中国の労働力
DHBR(以下色文字):2002年に中国最大の電機メーカー、海爾(ハイアール)と包括提携しました。そのきっかけは何だったのでしょうか。
井植(以下略):私は2~3年に一度、アラブ首長国連邦(UAE)の首都ドバイに行きます。ドバイは自由貿易圏のため中近東の販売基地になっていて、日本から直接輸出できないようなイランとかイラクにも商品が供給されている。ドバイに行くと、世界の商品がどんな動きをしているのか手に取るようにわかるんですね。
2000年にドバイに行った時、その変化にショックを受けた。その前の1997年に行った時は、韓国製品がすごく多かった。LG、三星(サムスン)、大宇の3社が大変目立っていて、日本の製品がどんどん置き換わっていた。「こら日本はあかんな」と思ったものです。ところが2000年にドバイのショッピングセンターをのぞいてみたら、今度は中国製品がものすごい勢いで増えていた。そのなかでも、特に海爾の商品が目立っていたんです。実は海爾の名前は前から知っていた。冷蔵庫のアメリカ市場でうちのライバル企業だったから。その時にドバイの小売店の社長さんは「2005年になったらもう中国製品でいっぱいになっちゃうよ」って言ってました。
それで日本に帰ってきてすぐに、海爾をベンチマークするように指示しました。そして同時に、海爾さんに「一度会社を見せてもらえないか」とお願いしました。で、2001年9月に青島(チンタオ)に見学に行きました。私はその時初めて青島に行ったんですが、海爾ともう一社、別の国有企業を見学したんです。国有企業と民間の海爾との違いはすごかったですね。
その時に海爾のCEOの張瑞敏さんに企業哲学なんかを聞かせてもらい、会社や工場を案内してもらった。その時は特に提携の話なんて出なかったけど、張さんに「ぜひ三洋も見に来てください」と言って、来てもらった。当社を見学した後、二人で話し合って、いろんな考え方が共通しているなと。じゃあプロジェクト・チームつくって検討して、2001年の年末までに結論出しましょう、という話になった。それで年末に中国に行って提携の仮調印して、1月に発表したわけです。みなさん3カ月で提携を決めるなんてすごいスピードだと言われましたけど、いまの中国の物事のスピードはそんなものですよ。張さんはあるパネルディスカッションで「なぜ提携相手に三洋を選んだのか」と聞かれて、「企業哲学が似ていたことと、スピード性があったこと」と言っていましたが、18年間であれだけ会社を成長させた彼らのスピードからすれば、3カ月で決めたというのもそれほどのことではないんじゃないですか。
海爾のどんなところがすごいと思ったのですか。
実際に海爾という会社を見て感じたのは、ハングリーさであり、勤勉さですね。社会主義から市場主義だと言って中国が変わってきた最初のうち、90年代初めくらいまではそうでなかった。いまはみんなものすごい働きますよ。「働きたい」という意欲がものすごくある。
それは一つは、日本企業では絶対できないようなインセンティブやペナルティを与えることで変わったんだと思う。たとえば海爾で見せてもらったのは、工場のなかに「今月の優秀な人たち」といって名前と写真が貼り出してある。それだけでなく、悪い人も名前と写真が出てるんです。毎月変わるんだけど、3回悪いほうに出たらクビなんです。「こういう能力の人は会社にはいらない」と。