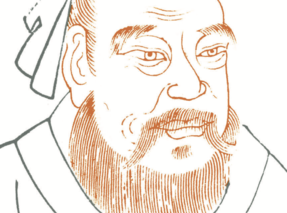-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
再来:中国脅威論
中国を経済的脅威と見る保護主義的な意見が日欧米で登場している。
ポール・クルーグマンは、HBRで──もちろんその数多い著作のなかでも──次のようなメッセージを繰り返し発してきた。
「実業界には『国民経済を企業経営の論理で語る』という過ちを犯す人が少なくない」
「学識あるエコノミストたちが、たとえば、なぜ『先進国の新たな脅威は新興諸国である』などと、平気で理論を無視したことを言うのか」
これまで槍玉に上げられた人物は、レスター・サロー(マサチューセッツ工科大学)、マイケル・ポーター(ハーバード大学)、クラウス・シュワブ(元世界経済フォーラム議長)、ジャック・ドロール(元EU委員会委員長)、ロバート・ライシュ(ハーバード大学、元アメリカ労働長官)といったアカデミア、さらにはジョージ・ソロス、スティーブ・ジョブスといった実業界の面々にも手加減しない。
ここ数年、中国の経済成長が本格化し始め、クルーグマンがこれまで繰り返し警告してきた、冒頭の愚がまた犯されている。たとえば、人民元の切り上げ、あるいは変動相場制への移行といった議論である。ここでも彼は、「自国が抱える政治経済的な問題をかわすために、中国をスケープゴートに利用しているのではないか」と疑う。
日本には「建設的なアジア政策がない」と指摘する向きは少なくない。その一方、産業界は──一部には1980年代のトラウマが残っているようだが──中国投資を拡大しつつある。現在、国際化の洗礼を受けてきた企業の重点課題に「中国戦略」が挙がっていないところはないだろう。
しかし、国と企業との温度差は歴然としており、国策と企業戦略は食い違いを見せている。たとえば、人民元の切り上げを言い出したのは政界だが、産業界は為替よりも中国経済の安定を望んでいた。また、海外からも求められている行財政改革の遅れは、間違いなく産業界の足を引っ張る。
とはいえ、産業界の一部でも、中国の生産性の向上が、日本の国際競争力を低下させ、日本経済そのものを圧迫するといった中国脅威論、かつてのアジア進出ブームでも唱えられた産業空洞化論が頭をもたげ始めている。