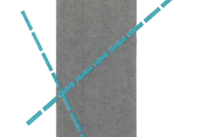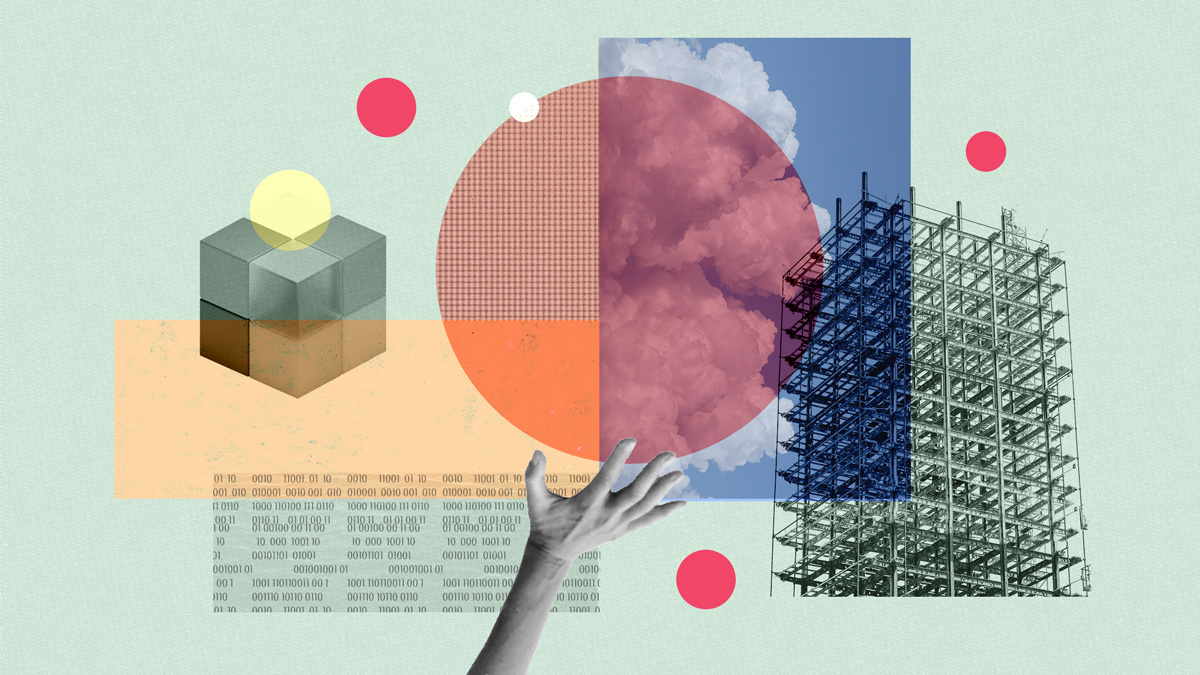
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
AI変革の成否は、投資額の多さでは決まらない
AIに何百万ドルも投資したのに、ライバル企業がそれより少ない投資で自社より高い成果を上げているのはなぜなのか。
この疑問は、企業が直面する戦略的ジレンマを表している。「AIにどのように経営資源を投じるのがベストなのか」「どのような場合に自社開発し、どのような場合に外部から調達すべきなのか」。その答えは、一方を選べばよいという単純なものではない。
企業は、自社開発か外部調達の二者択一ではなく、より繊細なアプローチを採用している。IDC(インターナショナルデーターコーポレイション)によれば、AIモデルを一から構築する計画のあるITリーダーはわずか13%であり、トレーニング済みのモデルを基盤にし、それを自社データで強化しようとするITリーダーは53%であった。こうした戦略的導入(戦略的提携の拡大を含む)へのシフトは、AIの成功が投資額の多さではなく、内製(Build)、外部調達(Buy)、融合(Blend)、提携(Partner)といった選択肢の中で、いかに賢く投資するかにかかっていることを表している。
筆者は、AI変革アドバイザーとして、企業がこの意思決定を下しながら、同時に新技術に対応するために人材の再配置を進めるのを間近で見てきた。あらゆる規模の企業でAI導入が加速するにつれ、こうした意思決定の緊急性は高まっている。TriNetの「2024 State of the Workplace」レポートによれば、中小企業の雇用者88%、従業員の71%がしでに職場でAIを活用している。AIによるメリットを最も得ている企業は、コスト面の検討に留まらず、体系的なアプローチを確立していた。
戦略的意思決定のための枠組み
最も成功を収めている企業は、AIの各能力を体系的な枠組みに基づいて評価している。最初に問うべきは「内製か外部調達か」ではなく、「この能力は、当社の顧客に独自の価値を提供し、それは他社に簡単に真似できないものか」である。
この戦略的価値評価では、3つの重要な側面を検討する必要がある。すなわち、差別化の可能性、組織としての準備状況、長期的戦略との整合性である。この評価プロセスに長けた企業は、主に初期費用や技術的志向に基づいて意思決定を行う企業よりも一貫して高い成果を上げている。
内製すべき場合
企業は、以下の条件を満たす場合に、内製を選択すべきである。つまり、AIの能力が競争力の中核を担い、自社のデータや専門知識が独自の参入障壁を形成できる場合、大規模展開後における長期的なコスト効率が高い初期投資を正当化できる場合、またはビジネスモデルにおいて知的財産権の保護が不可欠な場合である。
内製アプローチには、総合的な計画と体系的な実行が求められる。まずは詳細な能力マッピングを行って、顧客向けアプリケーションから運用システムまで、必要なAI能力をすべて洗い出す。カスタム開発が必要な各能力については、技術要件、人材要件、インフラ要件を評価する徹底した実現可能性の調査を実施する。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)