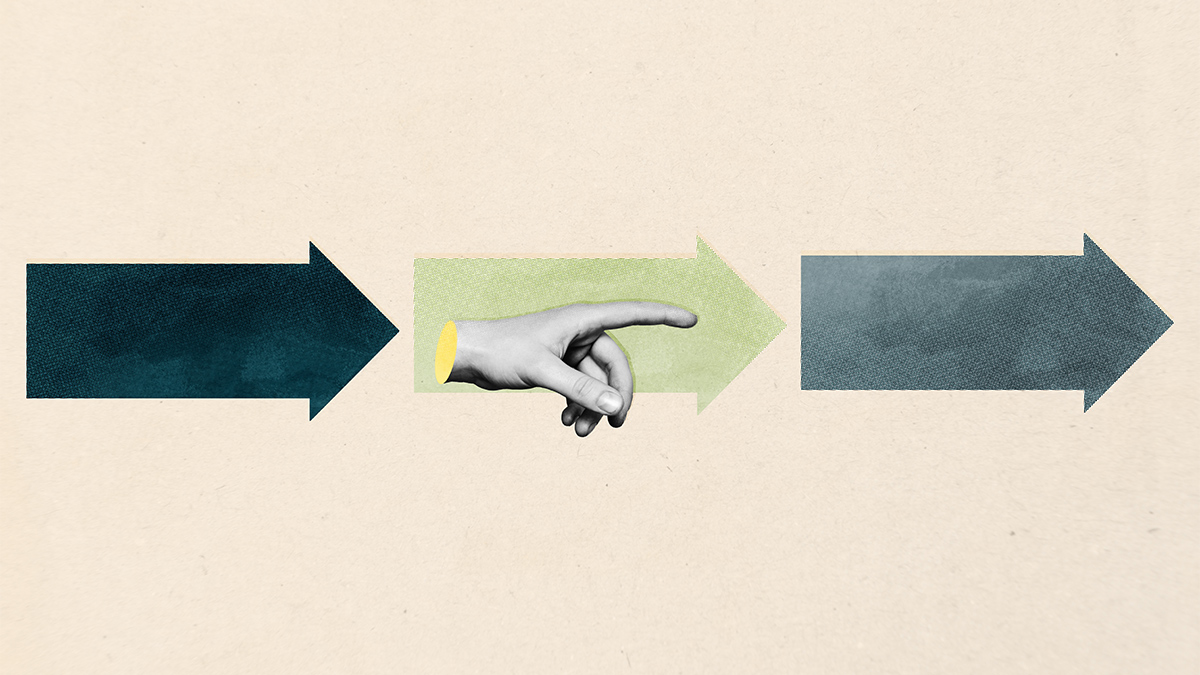
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
直観は磨くことができる
2008年の時点で、配車サービス「ウーバー」のビジネスアイデアは、救いようがないものに見えた。規制面の逆風は強く、ビジネスモデルの有効性も未知数だった。それに、スマートフォンのアプリで見ず知らずの人のマイカーを呼び出して、それに乗せてもらうなどという発想は、多くの人に不安を感じさせずにはいられなかった。
どんなに経験豊富な投資家も、このビジネスに投資することには腰が引けていた。話を聞く限り、うまくいくアイデアとは思えなかったのだろう。しかし、初期にウーバーに投資した一握りの投資家たちだけは、それとは違うものを感じ取っていた。この人たちは、このアイデアに「確実性」があるとは言えないまでも、「明確性」があると感じていた。頭の中でピンとくるものがあったのだ。
当時、そうした投資家たちは、そのピンとくるものについて完全に言葉で説明することはできなかった。「ただそうわかる」としか言いようがなかった。
このような瞬時の認識を「本能的なひらめき」という言葉で表現する人が多い。それもあってか、企業幹部の意思決定を論じる人たちは、この種のひらめきを衝動的もしくは感情的なものと思い込んでいるケースが少なくない。しかし、現実には、それはもっと繊細でもっと強力なものだ。それは、「直観的洞察」とでも呼ぶべきプロセスの産物なのである。
筆者は、行動科学者としての研究、そして企業の上級幹部たちに対するコーチングの経験を通じて気づいたことがある。リーダーたちに向けて唱えられるアドバイスは、データの重要性を説くものがほとんどだが、世界でトップレベルの成果を上げているCEOたちはたいてい、それとはまったく異なるものに頼っている。それが直観的洞察である。
ことのほか大きな成果を上げているCEOたちは、そのような直観を生まれもっての超能力のようには考えていない。それを一つのスキルと位置づけ、磨きをかけてきたのだ。
直観的洞察とは(本当のところ)どのようなものなのか
筆者の研究では、「直観的洞察」を、経験とデータを統合する内面の──時には潜在意識下の──プロセスと定義している。それは、脳が膨大な量のパターン認識と感情的な記憶、状況にふさわしい対応力に基づいて、方向性を見出すプロセスと言える。この内面のプロセスは、最終的に「本能的なひらめき」という形で結実する。この状態に到達した瞬間、自分がどうすべきかがはっきりと理解できるのだ。
「直観的洞察」と「本能的なひらめき」という2つの概念は混同されやすいが、この両者を区別することは極めて重要だ。まとめると、次のようになる。
・直観的洞察とは、プロセスである。
・本能的なひらめきとは、プロセスの結果である。
豊富な経験を持っているCEOが「私は本能的なひらめきを信じて行動しています」と言う場合、実際にはたいてい、長年にわたって蓄えてきた大量の小さな意思決定や失敗の経験、パターン、フィードバックループ、メンタルモデルを信じて行動しているのだ。
それは、高度にパーソナライズされたデータによって訓練されるアルゴリズムと似ている面がある。このような人たちの抱く直観は、たえず洗練され続けているのだ。その人がしっかり振り返りを行い、直観を修正し、自分の直観の限界を認識している場合は、とりわけ高いレベルまで洗練されていく。
本能的なひらめきは単なる感情ではない、それは「経験+データ」である
筆者は博士論文の執筆準備をしていた時、アーリーステージのスタートアップ企業に投資する投資家たちの意思決定について研究した。旧来の分析がうまくいかない状況で、利害得失の大きな意思決定をどのように行っているのかを調べたのだ。
この研究により明らかになったのは、投資家が「本能的なひらめき」について言及する場合、衝動的な勘のことを言っているわけではない、ということだった。それは、何段階にもわたる静かな推論のプロセスを通じて、分析的な情報を、感情に深く結びついた経験と組み合わせた結果なのだ。
ここで興味深いことがある。「本能的なひらめき」に到達するまでに、データはみずからの記憶と感情に完全に統合されており、もはや外から得られた情報とは感じられなくなっているのだ。それは、自分の私的なものに感じられる。私たちは甘いアイスドリンクを飲む時、ドリンクに糖分が添加されていることはわかっているが、それは完全に液体の中に溶けている。このドリンクを飲む人は、糖分などの個々の成分を味わうのではなく、ドリンク全体を味わう。それと同様のことが起きているといえるかもしれない。
「本能的なひらめき」を言葉ですべて説明しようとするとしばしば裏目に出る理由は、ここにある。論理と事実だけに基づいて自身の意思決定の正当性を説明しようとする投資家は、せっかくの正しい判断を放棄してしまうことが多い。直観とは、頭で考える内容がすべてではなく、潜在意識のレベルで知っていることの場合もあるからだ。
データが過剰になるケース
途方もない量の情報、さまざまな推薦を提示するアルゴリズム、そしてあまりに大きな認知的負荷が当然になっている世界で、リーダーにとって本当に難しい課題は、データを入手することではない。データを解釈することだ。データをもとに、どのように行動すべきかを判断すること、と言い換えてもよいだろう。このような状況において、直観は戦略上の強みになりうる。
傑出したCEOは、曖昧な要素が多い環境で成功を収めることができる。グローバルな危機が持ち上がっていたり、新しい市場でのビジネスに乗り出していたり、テクノロジーを取り巻く環境が変化し続けていたり、人材の流動性が高まっていたり……このような環境では、データは不完全だったり、互いに食い違っていたりする可能性がある。
それでも、CEOは決定を下さなくてはならない。それも、重圧の下で、素早く決定しなくてはならないことが多い。
その意味で、直観は一つのソフトスキルの域に留まらず、一つの差別化要因と言える。
よい直観を持っているとは、ファクトを無視する姿勢を意味するわけではない。数字が意味を成さず、いわば数字の声ではなく、みずからの内面の声に耳を傾けるべきケースを見極められることを意味する。フォーチュン100に名を連ねる大企業のCEOが筆者にこう語ったことがある。「データだけでは85%までしか到達できないタイプの意思決定があります。その場合、残りの15%は本能的なひらめきで決まります」
内面のささやき声に耳を傾ける
現代のリーダーはかつてなく、騒々しい環境に身を置いている。メディアの報道、市場からのプレッシャー、社会の期待、さらにはAIモデルまで、多くの要素が私たちの関心を引きつけようと、いわば大声を上げているのだ。それに対し、直観的な意思決定は、静かに意識的に行われる。そうした意思決定は、その人が咀嚼したデータと蓄積してきた経験の両方によって形づくられる。
ところが、人間の本能は、静かな声に注意を払うようにはできていない。そして、社会的なノイズが執拗で仰々しいものであるのとは対照的に、直観が大げさに自己アピールすることはない。直観は、さりげなくシグナルを発し、そっと私たちの背中を押し、自然に表面に浮上してくる。直観のささやき声に耳を傾ける習慣を身につけることは難しいが、そうしたささやき声にこそ、しばしば真のインサイトが含まれている。
有効な直観を持っているリーダーはどこが違うのか
すべての人の直観が同じ水準に達しているわけではない。企業幹部の中には、信頼性の高い内面の指針を持っている人もいるが、不安やバイアスや自尊心をインサイトと誤解してしまう人たちもいる。この両者の違いは、その人物の直観がどれくらい訓練されているかという点にある。
筆者の研究により、有効な直観を持っている人とそうでない人を分ける4つの条件が明らかになった。
1. 経験の量と多様性:多様な状況を目の当たりにしてきたリーダーほど、充実したパターン認識を育んでいる。数回にわたる景気後退やリストラ、あるいは市場拡大を経験してきたCEOは、いわば内面に豊かな資料室を築いていて、それを武器に有効な本能的直観を発揮できるのだ。
2. 計画的な内省:直観は、経験だけで育まれるものではない。みずからの経験を分析することが不可欠だ。優れたリーダーは、しっかり時間を取って、みずからの意思決定や、成功と失敗を振り返っている。「私はどのように感じていたのか」「私は何を感じ取ったのか」「私は何を読み間違ったのか」。このようなメタ認知を抱くことにより、未来の判断がより洗練されたものになる。
3. 文脈の調整:極めて直観の質が高いリーダーは、あらゆる場面に同じ直観を当てはめたりはしない。自分の直観がどのような局面で有効で、どのような局面でうまくいかないのかを知っているのだ。たとえば、ある企業幹部は、契約を法的に検討する時、直観に頼ることはけっしてないが、人材採用で自社と採用候補者の相性を検討する時は直観に頼ると、筆者に語ったことがある。直観は、自身が充実した経験をもっている領域では威力を発揮するが、経験が乏しい領域では危険を伴う。
4. 静かな傾聴:直観は、大声を上げて自己アピールしたりはしない。直観は小さな声でささやく。会議と会議の合い間の時間や、散歩や執筆や内省の時間など、精神が平穏な時に自然に浮上してくる。騒々しさとスピードが有利に働く世界にあっても、直観に重きを置くリーダーは、静かさを大切にし、静的なもののなかに潜むシグナルに耳を澄ます。
直観を磨くための実践的な方法
直観を研ぎ澄ましたいのであれば、まずは直観を筋肉のように扱うことから始めるべきだ。つまり、計画的な訓練によって強化できるものと考えるのである。以下に、筆者があらゆる業種の企業幹部たちに対して用いている5つの方法を紹介する。
1. 「平穏テスト」:強力な衝動に突き動かされて行動する前に、自分に問いかけよう──「もし私が完全に平穏な精神状態にあったとして、それでも同じ判断を下すだろうか」。このシンプルな問いは、感情的な切迫感と、ある状況が明確であるという感覚をはっきり区別する手立てになる。感情が悪しきものだというつもりはない。しかし、それは直観とは異なるものだ。その点は頭に入れておこう。
2. 意思決定の振り返り:利害得失の大きな意思決定を行った後は常に、その時に自分が感じたこと、目に留まったパターン、決定の手掛かりにした要素を書き留めるようにしよう。そして、数週間、もしくは数カ月後に振り返り、判断の正確さの度合いを検討するのだ。こうしたことを繰り返すうちに、自分の内面にシグナルの資料室を築いていけるだろう。
3. プロセスに名前をつける:いま自分が身を置いている段階に名前をつけよう。「いま私は情報を収集している段階だ」「いま私はシグナルを解釈している段階だ」「いま私は不確実性に向き合っている段階だ」「いま私は明晰な段階に到達した段階だ」……。直観的判断を下すプロセスで自分がどの段階にあるのかをはっきりさせることにより、自己に関する意識を高めて、衝動を弱めることができる。
4. 物事の理解を助けてくれる人物を周囲に配する:自分の思い込みに異を唱えてくれる同僚や相談相手の輪をつくろう。といっても、その人たちに正解を教えてもらうことが目的ではない。みずからの直観の声をよりはっきり聞くためだ。本能的判断の妥当性を確認するための最良の手立ては、よい問いを投げかけてくれる人たちによってもたらされる場合も少なくないのだ。
5. ミクロの意思決定を掘り下げて検討する:最良のリーダーは、小さなことに関しても直観に基づいて意思決定を行う。たとえば、誰を昇進させるか、会議でどのように反応するか、いつ沈黙を守るかといったことだ。こうした一つひとつのミクロの意思決定は、より正確に、より自信をもって判断を下すための内的指針を築くうえで役立つデータになる。
行動することにより、直観が有益なものになる
直観的な意思決定に関して、過小評価されている要素がもう一つある。その要素とは決断力だ。直観の威力の源泉は、インサイトそのものにあるわけではない。その威力の源泉は、インサイトに基づいて行動しようという意思をもつことにある。それを意図とスピードと表現することもできるだろう。
ウーバーへの初期の投資家たちは、明晰な理解に達したと感じただけでなく、その理解に基づいて行動を起こしたのだ。そうした投資家たちは、静かなシグナルを思い切った行動に転換し、そのうえで経営陣へのメンタリングを行ったり、適切なリソースを提供したり、正しい戦略的な方向性を示したりすることを通じて、自分たちの決定を「正解」にしていった。決断力が内面のシグナルを強化し、未来の直観的判断の質を向上させたのである。
一言でいえば、直観は意思決定の根拠になるだけでなく、物事の結果を左右する場合もあるのだ。
* * *
直観は、傑出した成果を上げるための近道ではない。それは、あなたがこれまで見てきたこと、学んできたこと、生きてきたことの総和と考えるべきだ。そして、それは自分の内面の声という形で表れる。その声は、恐怖や自尊心やプレッシャーよりも小さい声かもしれないが、常にそこにある。
直観に磨きをかけ、それを活用するすべを見出すことのできたCEOにとって、直観に勝る強みはない。予測とパフォーマンスがことさらに重んじられる世界にあって、直観的洞察は、すべての知恵が声高に自己主張するわけではなく、すべてのシグナルに名前がついているわけでもなく、すべての優れた意思決定が表計算ソフトから始まるわけでもないと教えてくれる。
時に、質の高い意思決定は、小さなささやき声から始まることもあるのだ。
"How CEOs Hone and Harness Their Intuition," HBR.org, July 17, 2025.






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









