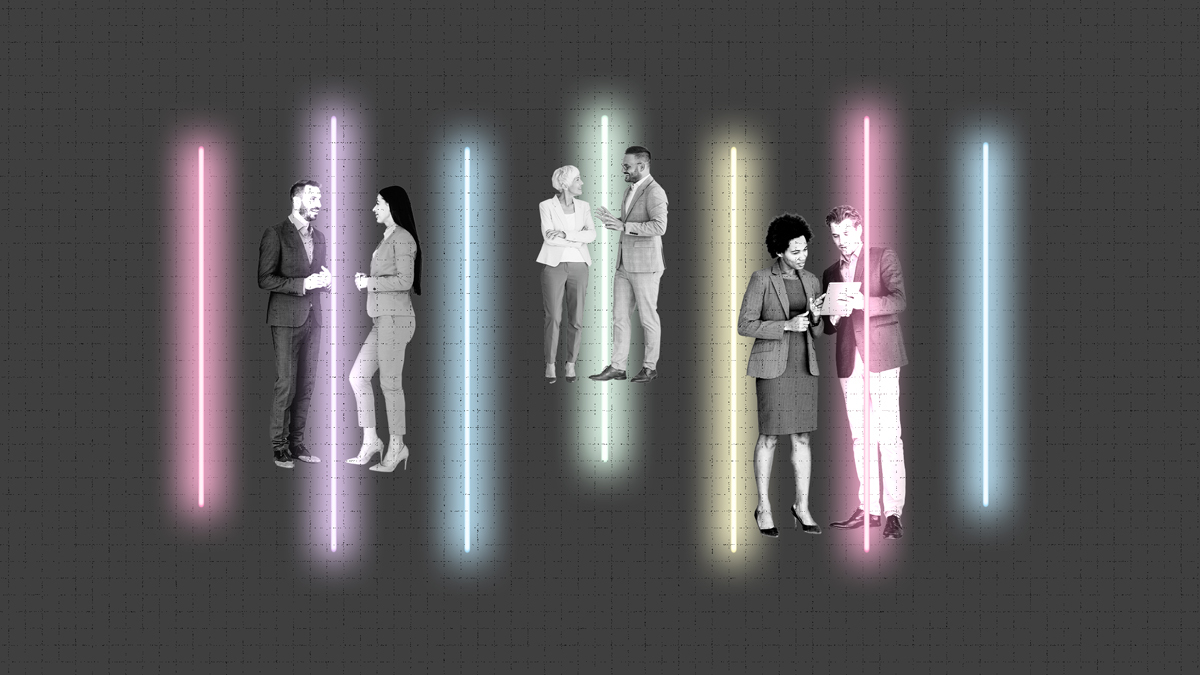
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
チームでの協働にAIを取り入れるには
筆者らは先日、ある会社のAI責任者を務めるマーク(仮名)が主催するAI戦略ワークショップに招かれた。このセッションには組織内のAIコミュニティのメンバーが集まり、AIに関する戦略的優先事項を話し合った。その場の全員がAIに精通しており、丸一日をかけて議論、ブレインストーミング、計画策定が行われた。
ワークショップの終わりにマークからフィードバックを求められた我々は、単純な質問を返した。「今日、この場にAIがなかったことに気づきましたか」
マークは驚き、一瞬沈黙した。そして「このチームでの協働でAIを使うことは、考えてもみませんでした」と認めた。
マークは例外ではない。毎日の定例会議、ブレインストーミング、オフサイトミーティング、企画会議、戦略検討といった集団的な取り組みの場では、AIに最も精通した人たちでさえ、AI以前の慣行とルーチンに戻ってしまう様子を筆者らは何度も目にする。これは単なる機会損失のみならず、組織の隅々にまで広がる構造的な盲点である。チームは生産性の向上だけでなく、より鋭敏な思考、意思決定の迅速化、連携の強化、より画期的なアイデアといった価値も取り逃がしているのだ。
我々のフィードバックについて考えをめぐらせたマークは、AIによってワークショップの前後と最中にはるかに多くの価値を引き出せたはずだと認めた。しかし、障壁は技術的なものではなく、マインドセットである。我々が質問するまで、AIの活用など考えてもみなかったと彼は言った。
これこそがリスクである。マネジャーが現状維持を基準にすると、一つのワークショップにおいてだけでなく、より大きな規模での抜本的な業務変革の機会を逃してしまう。これに組織の各所で行われている数十のワークショップや会議、協働セッションを掛け合わせてみれば、何もしないことのコストが明白となる。これらの集団的場面がAIによって再構築されない限り、職場におけるAIの効果は限られたままだろう。
AIが協働を向上させる可能性は、単なる理論上のものではない。一部のマネジャーはすでに従来のやり方に対抗し、チームの協働、思考、意思決定の方法にAIを組み込んでいる。
筆者らは新たなベストプラクティスを探る取り組みの中で、定性調査とフィールド実験を行い、3~4人の小グループで働くマネジャー100人余りを観察した。すると注目すべき結果が判明した。マネジャーの3人に2人が、チームレベルでAIを用いると成果の質が高まったと報告したのである。リスクがより効果的に軽減されたという指摘も同程度の割合を占めた。
これらのマネジャーは、より多くAIに疑問を投げかけ(「AIのアウトプットに対し、より積極的に疑問をぶつけた」)、より多く実験し(「異なるアプローチを試し、プロンプトを比較した」)、より綿密な振り返りをした(「チームでの議論によって、より思慮深く慎重なAIの活用が促進された」)。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









