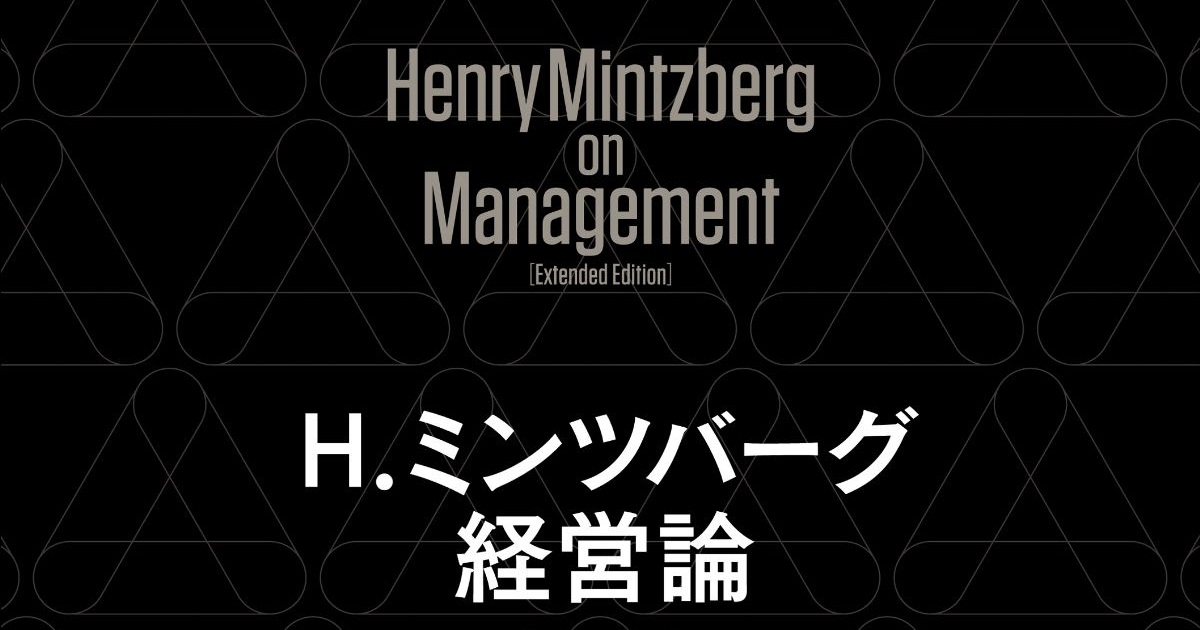
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
入山章栄教授が最も強調する
ミンツバーグ経営論が重要だといえる3つ目の理由
前回の記事はこちら→「入山章栄教授が語る、ミンツバーグ経営論がいまこそ重要である理由」
『H. ミンツバーグ経営論[増補版]』の刊行に当たり、筆者は前回、ミンツバーグ経営論が世界で支持され、あらためて重要が高まっている背景には、3つの理由があると述べた。そして、第1の理由として、ミンツバーグ氏ほど、経営論において包括的な視点をバランスよく持つ人はいない点を、第2の理由として、包括的に経営の視点・考え方を整理したうえで、それらを巧みに再構築し、独自のわかりやすい言葉に置き換えることに圧倒的に長けている点を挙げた。
そして第3の点──これこそが筆者が最も強調したい点なのだが──は、ミンツバーグ氏の主張が、これからの「AI全盛時代」において、経営者・マネジャーが果たすべき役割を明確に示していることだ。同氏は、現代のビジネスにおいて軽視されがちだが、実は極めて重要なもの、すなわち「直感」「創造性」「考えるより、まず先に行動すること」の重要性を思い起こさせてくれる。
この主張は、先に紹介した彼の代表的論文「戦略クラフティング」(本書『H. ミンツバーグ経営論[増補版]』第4章に掲載)に象徴的に表れている。同論文でミンツバーグ氏は、「戦略とは、陶芸家がろくろを回しながら土をこね、作品を形づくっていくプロセスに似ている」と論じる。現実の経営における戦略形成とは、MBAの教科書にあるように「将来を予測し、きちんと計画を立て、その通りに実行する」ものではない。むしろ陶芸家が土を触り、ろくろを回しながら作品の形を見出していくように、まず行動を起こし、予期せぬ出来事に直面しながらも修正を重ね、試行錯誤を繰り返すことで、自分たちが本当に目指したい戦略が次第に浮かび上がってくるものなのだ。
そして筆者から見れば、これこそがAI時代の経営・マネジメントにいっそう求められるものである。なぜなら、これからは「事前の分析・計画」は、ほぼすべてAIが担えるからだ。他方、AIに決定的にできないことは、「不確実性が極めて高く、計画通りに進まない現実において、誰も正解を教えてくれない中で、直感・経験を駆使しながら臨機応変に対応し、意思決定を下し、行動し続けること」である。AIは正解のある問いに解を出すことは得意だが、正解のない状況で、直感も踏まえながら意思決定することはできない。これからのマネジメントにおいて人間が果たすべき役割は、まさにミンツバーグ経営論の主張そのものといえるのだ。
この3つの理由で、いまこそミンツバーグ経営論がさらに評価されるべき時代になった、と筆者は確信する。もしビジネスパーソンから「経営学者が書いた著作の中で、一番最初に読むべきものは何か」と問われたら、筆者は迷いなく本書を含めたミンツバーグ氏の一連の著作を挙げるだろう。
最後になるが、先に述べた2025年5月のミンツバーグ氏の来日において、筆者は北海道で同氏と半日以上をともに過ごし、約1時間半にわたりじっくりと対話させていただく機会に恵まれた。今回の来日は、北海道の生活協同組合コープさっぽろ(筆者は理事を務める)の取り組みに同氏が関心を抱いたことがきっかけであった。同氏はコープさっぽろを取材するために1週間近く道内に滞在されたのだ。
※来日時のミンツバーグ教授と入山教授の対談、コープさっぽろの大見英明理事長との鼎談などをまとめた記事はこちら。
【連載】リバランシング・ソサエティ 私たちはどこまで資本主義に従うのか
ミンツバーグ氏と過ごした半日は、筆者の人生で忘れがたい時間となった。その理由は対話の内容だけではなく、同氏の素晴らしい人柄にある。ミンツバーグ氏は驚くほど謙虚で、優しく、非常に好奇心旺盛で、何より大変チャーミングな方であった。
たとえばコープさっぽろの大見英明理事長に自著をプレゼントする際には、何と大見氏ではなくお孫さんの名前を記し(さりげない会話の中で知ったらしい)、「この本をぜひ渡してほしい」と進呈されたのである。大見氏はその心遣いに感激し、涙を流されていた。本書『H. ミンツバーグ経営論[増補版]』の中にもウィットに富んだ表現が多くあるが、それはミンツバーグ氏のそんな人柄を示すものなのだ。
筆者はいまこそ、日本中のビジネスパーソンにぜひ本書を手に取っていただき、ミンツバーグ経営論(というよりも、実は最も王道の、現実に基づいた経営論)の真髄に迫ってほしい。本書はどの章からでも読めるように構成されているので、ボリュームに圧倒される必要はない。関心のある章、たとえば最近のインタビューである第16章「経営者に必要なのはエンゲージング・マネジメントである」や第17章「マネジャーの仕事は『普通の創造性』を育むことである」から始めてみるのもお薦めだ。
これからミンツバーグ経営論が、世界でさらに注目されることは疑いない。本書を通じて、ミンツバーグ経営論が日本のビジネスパーソンにさらに浸透することを、筆者は心から願っている。
期間限定プレゼントのお知らせ
書籍『H. ミンツバーグ経営論[増補版]』の第10章「[インタビュー]アングロサクソン経営を越えて」の一部をまとめたPDFを期間限定(2025年12月31日まで)でプレゼント中です。本インタビューは、『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』編集部が2002年に行った、日本オリジナルコンテンツです。
DHBR電子版の無料会員にご登録のうえ、対象論文をダウンロードしてください。

[著]ヘンリー・ミンツバーグ
[訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]ヘンリー・ミンツバーグ教授の『ハーバード・ビジネス・レビュー』に掲載されたすべての論文、および日本版限定インタビューを収録。入山章栄・早稲田ビジネススクール教授も「ミンツバーグ氏ほど、経営論において包括的な視点をバランスよく持つ人はいない。これからのAI全盛時代において、経営者・マネジャーが果たすべき役割を明確に示している」と絶賛! 1975年に発表され、新たなマネジャー論に先鞭をつけた論文「マネジャーの職務」を皮切りに、ミンツバーグ教授が歩んだ50年間を知ることのできる一冊です。
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









