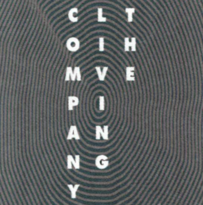「世界の三大偉人」とも称される、社会運動家・賀川豊彦
大正デモクラシー自体は、明治憲法体制を一新できませんでしたが、1925年(大正14)、いわゆる普選(普通選挙)法が実施されるという大きな成果を生みました。これを推進し、「普選の父」と称されるのが、中村太八郎(たはちろう・1868~1935)です。
信濃国筑摩郡大池村(現長野県東筑摩郡山形村)の豪農の家に生まれた中村は、自由民権運動の影響下に育ち、上京して法律などを学びます。帰郷後は、地価修正運動、中山道鉄道誘致運動、米穀取引所設置運動など地域の繁栄のための運動に尽力し、日清戦争後は、社会問題に鋭い関心を示し、1897年(明治30)7月、全国に先駆けて松本で木下尚江(なおえ)らと普通選挙期成同盟会を設立します。
生涯のほとんどを普選運動に捧げた中村は、職業を聞かれると、「職業は普通選挙だ」と答えていたといいます。県議会選挙での恐喝取財の容疑で1年10カ月の獄中生活を強いられたりしましたが、出獄後すぐに貴族院・衆議院への普選請願書を提出したり、雑誌『普通選挙』を発行したりと、普選運動の先頭に立って活動します。
中村らが普選運動を旗揚げして28年後の1925年(大正14)3月29日、普通選挙法案が衆議院、貴族院で可決成立します。同年5月5日に公布され、その翌日付の報知新聞は「三〇年の久しきにわたり、終始一貫献身的努力を普選の達成に捧げたる中村太八郎氏の功労を閑却してはならぬ」と報道しています。
中村はまた、土地国有論者としても有名で、土地国有講究会を組織してこの問題に取り組んだことから、「土地国有論の父」とも呼ばれています。これに関連して、わが国では日露戦争の頃から、地主の土地所有が強大となり、小作地面積は全国総耕地の45%を超え、地主による圧迫と小作料の重圧により小作人は窮乏を極めます。さらに、第一次世界大戦後の1920年(大正9)に勃発した経済恐慌をきっかけに農民の生活が悪化するなか、日本で初めて全国組織としての小作人組合「日本農民組合」が設立されます。地主層との闘いの前面に立って組織的な農民運動を確立した先駆者が、この組織の設立者の一人で、「農民の父」と呼ばれた杉山元治郎(もとじろう)(1885~1964)です。
大阪府日根郡下瓦屋村(現大阪府泉佐野市)に生まれた杉山は、16歳でキリスト教に入信し、伝道の道を歩むかたわらで農業にも従事し、多くの農民と接するうちに小作争議への関心を強めていきました。日本農民組合の委員長として小作争議を指導していた杉山は、無産政党結成の機運が高まるなか、1926年(大正15)に結成された労働農民党の初代執行委員長に就任します。1932年(昭和7)には第18回衆議院議員総選挙に全国労農大衆党公認で出馬して当選。以後、戦前・戦後を通じ九回の当選を果たしました。
 賀川豊彦(1888~1960)
賀川豊彦(1888~1960)
杉山と共に日本農民組合を設立した賀川豊彦(かがわとよひこ・1888~1960)は、農民運動はもとより、多くの社会運動を指導し、友愛・互助・平和の精神を唱え続けた不屈の伝道師として知られています。賀川は、結核などを病み、苦しみながら、当時の日本最大のスラム(貧民街)の一つ、神戸のスラムに住み込み、救済活動を続けた「貧民街の聖者」として世界的に知られています。海外布教は13回を数え、世界連邦建設運動の提唱など世界的に活動の幅を広げ、ノーベル平和賞候補にもなりました。評論家の大宅壮一氏は、賀川を「近代日本のナンバーワン」と評し、また、アメリカでは、「世界の三大偉人」として「賀川、ガンジー、シュバイツァー」を挙げる書籍があるほどです。
賀川が指導した社会運動のなかで最も成功したといわれるのが、後の生協・農協・医療生協などへつながる協同組合運動です。相互扶助の精神による消費者のための消費協同組合、生産者のための生産協同組合を目指し、1920年(大正9)に神戸購買組合を創設、「一人が万人のため、万人が一人のため」の標語をつくり、その後も現在の生協(COOP)・大学生協・JA共済に結びつく数々の生活協同組合を立ち上げたことから、「協同組合運動の父」「生協の父」と称されています。
賀川の社会運動を支えたのは著述業の収入でした。貧民街での救済事業、労働組合運動、農民組合運動などの体験に基づく自伝的小説『死線を越えて』(1920年・上巻)、『太陽を射るもの』(1921年・中巻)、『壁の声きく時』(1924年・下巻)の三部作は、累計400万部を売り上げ、大正期最大のベストセラーとなりました。
大正デモクラシー期は、労働者の地位向上や福祉の増進を目指す運動が盛んに行われ、さまざまな団体が組織され社会的関心を呼び起こしました。吉野や賀川のほかにも、現在の連合に繋がる労働運動の源流をつくった「日本労働運動の父」鈴木文治(ぶんじ・1885~1946)、職業紹介事業の基礎をつくった「わが国職業紹介事業の父」こと豊原又男(1872~1947)、労働災害防止運動の中心的存在として活躍し「安全の父」「労災防止の父」と呼ばれた蒲生俊文(がもうとしぶみ・1883~1966)などに、各分野の草分け的存在として「父」の称号が与えられています。
(つづく)
「民衆運動の父」人の墓所
田中正造墓所(阿弥陀堂境内・栃木県佐野市小中町/惣宗寺〔佐野厄よけ大師〕・栃木県佐野市金井上町/田中霊祠・栃木県栃木市藤岡町藤岡/寿徳寺・栃木県足利市野田町/雲龍寺・群馬県館林市下早川田町/北川辺西小学校敷地内・埼玉県加須市麦倉)
*正造の遺骨は生前ゆかりのあった六カ所に分骨された。
高野房太郎墓所(吉祥寺・東京都文京区本駒込)
片山潜墓所(赤の広場「クレムリンの壁」・ロシア/青山霊園・東京都港区南青山)
安部磯雄墓所(雑司ケ谷霊園・東京都豊島区南池袋)
堺利彦墓所(総持寺・神奈川県横浜市鶴見区鶴見)
吉野作造墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
中村太八郎墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
杉山元治郎墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
賀川豊彦墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
鈴木文治墓所(不明)
豊原又男墓所(金谷山宝祥寺・東京都新宿区若松町)
蒲生俊文墓所(不明)
※田中正造、吉野作造、およびタイトル写真出所:国立国会図書館ホームページ/
安部磯雄写真出所:前川写真館/賀川豊彦写真出所:賀川豊彦記念・松沢資料館





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)