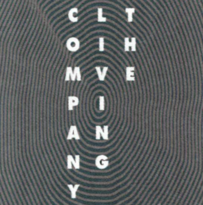-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
明治の義人――田中正造
明治時代初期に現在の栃木県と群馬県の間を流れる渡良瀬川(わたらせがわ)周辺で起きた足尾銅山鉱毒事件は、日本で最初の公害問題といわれています。この問題を提起し、生涯をかけてこれと闘ったのが、「明治の義人」田中正造(しょうぞう・1841~1913)です。
1841一八四一年(天保12)、下野(しもつけ)国安蘇(あそ)郡小中村(現栃木県佐野市)の名主家に生まれた正造は、17歳で家を継ぎますが、不正を働く領主の退陣を求めて投獄されます。解放された1869年(明治2)、正造29歳のこの年、政府は版籍奉還を行い、時代は変貌期を迎えていました。縁あって江刺(えさし)県(現岩手県)庁附属補に採用された正造は、農民が困窮する状態をつぶさに調査し、彼の提案を受け入れた県はただちに1800人分の救援米を支給したといいます。
ところが、またも試練が待ち受けていました。正造の直接の上司が殺害される事件が起き、殺人容疑の罪で逮捕されてしまうのです。1874年(明治7)、嫌疑は晴れますが、獄中生活は2年10カ月にも及びました。
郷里に戻った正造は、38歳で政治の道を志します。その際、実父から、正造の政治家としての道を暗示するような狂歌を贈られたといいます。
「死んでから仏になるはいらぬこと、生きているうちよき人となれ」
明治10年代、自由民権運動が全国に広まるなか、正造は郷里の区会議員に選ばれます。民権運動の推進力となっていた新聞紙の創刊が全国各地で相次ぐなか、栃木でも栃木新聞が再刊され(第二次栃木新聞。現下野新聞)、編集長に就任した正造は国会開設の急務を説くかたわら、栃木県議会の指導者になっていきます。
この時期、強引な土木工事を進めて「土木県令」「鬼県令」と呼ばれた福島県令の三島通庸(みしまみちつね)が栃木県令を兼任することになり、栃木市から宇都宮市への県庁移転を強行して官庁の建設や道路開削などが推し進められました。民権派が多数を占める県議会は三島の暴政に対抗し、正造は政府に訴えます。ところが、過激派による加波山(かばさん)事件が起き、正造は事件連累者として逮捕され、67日間に及ぶ三度目の獄中生活を送ります。
民衆の立場に立って熱弁をふるう正造には、主要都市に置かれた鎮台(軍隊)にちなみ、「栃鎮(とっちん)」(栃木の鎮台)の渾名がつけられます。この異名から、正造がいかに精力的な活動を行っていたかをうかがい知ることができます。
栃木県議会議長を経て、1890年(明治23)の第一回総選挙で衆議院議員に当選し、活躍の舞台を国政に移すと、1891年(明治24)の第二回帝国議会で、農作物や魚に大きな被害を与えていた足尾銅山の鉱毒問題を初めて取り上げ、政府や銅山側の責任を厳しく追及します。渡良瀬川沿いの人々を救うための闘いを続ける正造が提出した質問書は、300人の議員から提出された全質問書の一割強に当たる35件に及び、国政での奮闘によって、「たなしょう」の渾名で一躍名物代議士となります。当時、内村鑑三は、政界の暴れん坊として「押し通る」の異名を持つ星亨(ほしとおる)を引き合いに「一の田中は一〇〇の星に勝ります」と語ったほどで、黎明期の帝国議会で、正造の存在感がいかに大きかったかを物語っています。
正造の追及により、政府は銅山側に一定の責任を認め、また、新聞各紙は徐々に被害地の惨状を報道したため、世論をつくり出すことに成功します。ところが1900年(明治33)2月13日、現地農民と警官隊が群馬の川俣村(現群馬県邑楽(おうら)郡明和町(めいわまち))で衝突し、農民多数が逮捕される川俣事件が発生。事件直後、正造は国会で事件に関する質問を行いました。これが、「亡国に至るを知らざれば、これすなわち亡国の儀につき質問書」で日本の憲政史上に残る大演説といわれるものです。
しかし、時の首相・山県有朋の答弁は、「質問の旨、趣その要領を得ず、よって答弁せず」というものでした。以後、国の政策に、まったく改善は見られませんでした。
それにもめげず、正造は国会での奮闘、各地での遊説に明け暮れますが、過労のため入退院を繰り返すようになります。すでに還暦を迎え、心身共に疲れ果てた彼は、1901年(明治34)10月、議員を辞職して11年間の代議士生活に終わりを告げました。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)