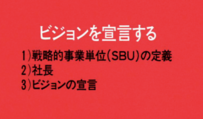仮説・検証サイクルにおける対話の重要性
セブン‐イレブン・ジャパンにおいて、仮説・検証のプロセスは店舗だけでなく、様々なレベルで実行されています。店舗開発の担当者は出店候補地の事情をつぶさに観察し、「この土地のオーナーは何を求めているだろうか」と考えます。そして、仮説を立てた上で提案するから、オーナーも話を聞いてくれる。いきなり「セブン‐イレブンに加盟しませんか」と聞いても、おそらく門前払いされるだけでしょう。商品開発も同じです。仮説に基づいて開発された新商品はPOSデータによって検証され、その結果は次の商品開発に反映されます。
では、セブン‐イレブン・ジャパンはどのように仮説をつくり、どのように仮説・検証のサイクルを根付かせているのでしょうか。ここで決定的に重要なのが不断に行われる対話です。
店舗に関する業務についていえば、店長とアルバイト、あるいは1人が8店舗程度をサポートするOFC(オペレーション・フィールド・カウンセラー)と呼ばれる本社側の担当者などが頻繁に対話を繰り返しています。その中で、よりよい仮説が生まれるのです。
対話の質を高めるために相当の費用もかけています。セブン‐イレブンの店舗の壁の向こう側には、ミーティングスペースがあります。他のコンビニチェーンの場合、スペースを「節約」して店舗に回すケースが多いのですが、セブン‐イレブンは一見非効率なようにも見えるスペースを確保しています。
こうした場を通じて、店長はアルバイトの高校生に「最近、高校では何が流行っているの」と聞いたりする。高校生の動向に詳しいのは、店長ではなく高校生です。同様に、その地域のことを一番よく知っているのは地域に住む人たちです。パート主婦などからも、店舗にとって貴重な情報が寄せられます。
対話の代表例は、毎月2回開かれるOFCミーティングでしょう。全国各地に散らばる数千人のOFCを1つの場所に集めて、これだけの頻度で直接顔を合わせることにより、情報共有や対話が行われているのです。また、FCオーナーのミーティングなども定期的に開催されています。
対話を通じた仮説・検証のサイクルは店舗では毎日繰り返されており、各スタッフの中に定着しています。毎日の繰り返しにより仮説・検証の“型”のようなものが形成されるとともに、世の中の変化への対応が実践されているのです。
1人1人が自分で考えて行動する自律分散型組織
冒頭、「世の中の変化への対応」、「基本の徹底」、「近くて便利」というセブン‐イレブン・ジャパンの3つのビジョンを紹介しました。同社は仮説・検証サイクルに基づく果てしない自己革新により、ビジョンを追求し続けています。
この運動に軸を与えているのが、「世の中に必要とされる企業であり続けたい」という強い意識です。社会的な存在価値と持続性の軸と言ってもいいでしょう。「近くて便利」の実践により、社会に対してより大きな価値を提供する。そんな意識を共有することで、変化し続けながらも、ぶれのない組織を実現しているのだと思います。

このような軸と仮説検証の型は、個々人が「自分で考える」ためのよりどころにもなっています。例えば、OFCは上司や同僚などに相談を持ちかけることもできますし、現場に出てFCオーナーと向き合い、商売の世界で数十年の経験を持つオーナーと対等に会話し、ときには説得を行ないます。
自分なりの仮説を立てて実行する個人、自分で考え行動する個人によって、セブン‐イレブン・ジャパンは自律分散型の組織を構築しています。いくら優れた経営戦略を立案しても、それを実行するのは現場の個々人です。店舗やOFC、商品開発、店舗開発などの現場に仮説・検証サイクルを埋め込み、自律分散的な業務運営を実現していること。そこに、知識創造企業としてのセブン‐イレブン・ジャパンの凄みがあります。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)