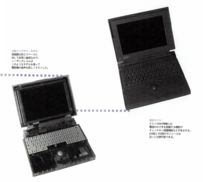会場から寄せられたいくつかの興味深い質問に対して、以下に私の考えを改めて載せておこう。
質問:顧客の消費習慣が短期間で変化することを考えると、競合に対する競争優位を獲得するためには、綿密な市場調査を時に妥協すべきなのか。
「市場調査についての妥協」が何を指すかによる。実際の市場で発売してみて、短いサイクルで改善を繰り返すことが、最良の市場調査である場合もある。綿密に計画した市場調査を段階を追って実施し、それに基づいて新製品発売を慎重に最適化する――こうした手法は多くの市場で、過去のものとなった。市場の変化の速さは驚くべきものだ。しかし、何もわからないまま闇雲に発売せよ、ということではない。定性的な調査をより重視する、あるいは市場での類似事例を投入戦略の参考にする、といった方法もあるだろう。
質問:製品やサービスの品質基準は、文化によって変わるものなのか。あるいは、誰もが目安とするべき絶対的な基準があるのか。
品質とは相対的な概念である、というのが私の前提だ。たしかに、ある商品区分においては、認識に明らかな違いがあるだろう。たとえば、欧米の多くの市場では女性の美の基準として、日焼けした肌が美しいとされる。そこで消費者は日焼け用品や関連商品を購入する。一方、複数のアジアの市場では、女性の透き通るような白い肌が美しいとされる。そこでドラッグストアの店頭には美白用品が溢れている。市場と顧客については現場で現実を知ることが何より大切だ。これはパネル討論で終始取り上げられたテーマであり、市場による品質基準の違いを理解するためには欠かせないことである。
質問:新興国市場に参入する際、自社の製品が模倣されてしまうような現地の慣行や風潮に対して、どのように防衛策を講じるべきか。
こうした質問が出たときには、私はこう答えている。人々を釘づけにするような新しい製品やサービスを次々と提供し続けることにより、模倣者たちの一歩先を行くのだ。この方程式のもうひとつの側面は、統合されたビジネスモデルを模倣へのヘッジ手段として利用することである。イケアがその好例である。イケアの家具を模倣することはそれほど難しくはない。だが、イケアが提供している顧客体験をプロセスの最初から最後まですべて模倣することは、恐ろしく困難である。これはまた、ビジネスモデルのイノベーションがいかに重要かを示すものでもある。
質問:消費者のニーズや文化的嗜好をより深く理解している地元の競合企業には、どう対抗すればよいか。たとえば漢方薬などがこれにあたる。
ローカル市場の微妙なニュアンスを理解する能力は、たしかに重要な資産である。このスキルを獲得するために、現地で積極的に提携先や買収候補を探す企業もある。たとえば2008年に、ジョンソン・エンド・ジョンソンのコンシューマー部門は、中国で個人向けスキンケア商品などの強力なブランドを多く所有する北京大宝化粧品有限公司を買収した。食品会社や飲料メーカーの場合も、それぞれ地元の市場で愛好されている商品を自社ブランドで代替するよりも、現地のブランドを買収するほうがずっと理にかなっていると判断する場合が多い。買収や提携は、新興国市場に割って入ろうとする企業にとって、とても重要な手段である。
質問:中間層あるいは富裕層を対象に投資するのとは違って、低所得層(BOP:ボトム・オブ・ザ・ピラミッド)向けに投資する企業は、利益を犠牲にしなければならないのか。
いわゆるボトム・オブ・ザ・ピラミッドの魅力が長らく言われている。しかし市場の現実を鑑みると、少なくとも一部の企業にとっては、利益を上げるのは非常に難しい。これは、過去に成功例がないとか、今後成功の見込みがないということではない。「もし中国人(あるいはインド人、インドネシア人、ブラジル人、ナイジェリア人)の消費者から、1人1ドルずつ獲得できる方法を見つけさえすれば……」と言っているだけではどうにもならないということだ。その1ドルを獲得するのは途方もなく困難なのだ。もちろん、低所得市場で事業を営む社会的な意義もたくさん存在する。したがって、この市場を無視するというのも得策ではない。現実をしっかり注視して進出しなければならない。
質問:たとえばブラジルのような新興国市場で、汎用品を法人向けに販売する場合、新規参入企業は最低価格を提示する戦略をとるべきか、それとも付加価値のある製品を提供する戦略をとるべきだろうか。
これについては、両方とも行うべき価値提案だと思う。もしも優れた生産方式、グローバルな規模の経済、独自のサプライチェーン管理能力などを基に、コスト競争力が維持できるのであれば、可能な限り低価格戦略を追求するべきである。同時に、ターゲットとする顧客企業を本当に理解し、相手のビジネスモデルに自社製品がどれだけ適合するのかを理解する必要がある。在庫管理、リスク分散、需要創造など、地元企業が直面しているさまざまな課題について支援を提供するチャンスがきっとあるだろう。かつて伝説の野球選手ヨギ・ベラが言ったように、「分かれ道に来たら、とにかく進め」ということだ。
以上のような魅力的なセッションに参加できたことについて、パネル討論に加わってくれたパネリスト、主催者のハーバード・ビジネス・レビュー、後援者のシンガポール経済開発庁に感謝したい。近いうちに、また議論できることを楽しみにしている。
HBR.ORG原文:The Right Entry Point for Emerging Markets March 12, 2012






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)