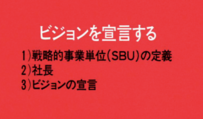-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
昨年12月に猪瀬直樹東京都知事が誕生して、東京メトロと都営地下鉄の今後が、再び注目されている。そこで本稿では両企業が統合するとしたら、それぞれの企業価値はどれくらいで、合併比率はどのくらいが適正なのかを探ってみたい。
1.九段下駅の壁、浅草駅・日本橋駅のシャッター
東京メトロ(東京地下鉄株式会社)と東京都交通局は、3月16日から、都営地下鉄とメトロの乗り換えをしやすくすると発表した。九段下駅では半蔵門線の押上方面行きホームと新宿線の新宿方面行きホームを隔てる壁を撤去し、改札を通らず乗り換えられるようにするとのことである。これまで、九段下駅で乗り換えるためには、階段を上り、改札を通り、もう一度、階段を下りる必要があった。
これは、猪瀬都知事が副都知事時代に出版した『地下鉄は誰のものか』(筑摩書房)で指摘されていた問題点である。また、同書においては、浅草駅・日本橋駅の東京メトロのシャッターが閉まっていたため、都営からメトロ、あるいはその逆の始発電車に乗り換えることができなかった事実を、東京メトロの株主総会で指摘したところ、ただちに改善されたとの記述がある。都知事の精力的な活動により、地下鉄利用者の利便性が向上するのは素晴らしいことである。
2. 何が論点なのか?
現在、東京メトロの株式は、国が53.4%、東京都が46.6%、それぞれ保有している。東京メトロの前身である営団地下鉄(帝都高速度交通営団)を株式会社化するときの法律によって、国はできるだけ早く東京メトロの株式を売却しなければならないことになっている。そこで、東京都は、国の保有株式を購入し、東京都を実質的な持株会社として、東京メトロと都営地下鉄の経営統合を図る計画を立てているらしい。国から都への株式売却代金は、一説によると、約2000億円と報道されている。
この問題の主な論点は、国から都への株式売却価格が適切かどうかである。国から都への株式売却価格が実態より安すぎれば、(東京都民以外の)日本国民から東京都民へ富の移転が生じる。株式売却価格が高すぎれば、おそらく東京都は自発的に株式を購入しようとはしないだろう。
また、東京メトロの株式売却価格が適正だとしても、東京都が経営統合の実施主体となれば、経営統合の効果は、日本国民ではなく、東京都民に帰属することになる。具体的には、統合会社の上場による上場益のうち、経営統合の効果の部分は、日本国ではなく、東京都に帰属することになろう。これがフェアかどうかが議論になる。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)