-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
前回は、市場の逆説性に目を向けました。市場とは、こうした反転が起こる場です。だからこそ、マーケティングにおける企業や地域の弱みは強みに転じていくわけです。さて、これも前回述べたように、この市場の逆説性そのものは広く知られた現象です。ところが、さまざまな実践の事例を見渡すと、企業のマーケティング担当者や地域のリーダーは、こうした逆説性を忘れてしまい、反転など起こらないと思い込んでしまいやすいのです。なぜ、そのような思い込みが起きるのでしょうか。そして、その克服にはどのような対応が必要なのでしょうか。こうしたマーケティング上の思考の罠の問題を、今回からの5回にわたって検討していきましょう。
なぜ、逆説性を見逃すのか--マーケティング近視眼
企業のマーケティング担当者や地域のリーダーが、市場の逆説性を見落としてしまう要因として、古くから繰り返し指摘されてきたのが「マーケティング近視眼(マイオピア)」です。
この問題を指摘したセオドア・レビットは、当時乗降客や貨物輸送の減少に直面していたアメリカの鉄道産業に向けて、「自らを衰退産業だと位置づけてはならない」と警鐘を発しました。なるほど、鉄道の乗降客や貨物輸送は減少していました。しかし、人やモノの「移動」に対するニーズは増える一方なのだとレビットは述べています。たしかに、バスやトラック、そして航空機による移動を含めると、人やモノの移動は増加傾向にあったのです。つまり衰退の原因は、自社の事業を移動産業ではなく鉄道産業と定義する近視眼だというのがレビットの見解です。
こうした近視眼の罠に陥らないためにも、企業のマーケティング担当者や地域のリーダーは、「自分たちは何を売ろうとしているか」という問いを、繰り返し自問しなければなりません。正解は、1つではありません。この問いへの回答は本質的に多様であることが、重要なポイントです。
惣菜店の事業の定義
たとえば、私たちの研究事例でいえば、デパ地下や駅ナカで人気の惣菜店「RF1」を運営する「ロック・フィールド」がこのような近視眼の罠に挑んでいました。今でこそ、話題のデパ地下や駅ナカの惣菜店ですが、かつてはそうではありませんでした。デパ地下や駅ナカというと新しい業種のようですが、惣菜店は昔から商店街や市場にありました。1970年代、80年代の日本でこの家族経営の商いを見て、これが巨大な近代産業になると予想できた人は少なかったはずです。
ロック・フィールドは注目すべき2つのイノベーションに取り組んでいます。第1はサプライチェーンの変革です。一般的な惣菜店では、外部から仕入れた原材料や半製品を店舗で調理しながら販売するのですが、ロック・フィールドは、セントラルキッチンと呼ばれる自社工場を設け、ここで食材を下処理して、半製品やキットにし、それらを店舗に届け、店頭で最終の仕上げをしながら販売をするというシステムを確立しています。店に届くものが異なれば、必要な調理設備も変わってくるので、出店に関する制約や考え方も違ってくるといいます。
第2は、「自分たちは何を売ろうとしているか」という事業の定義の問い直しです。かつての惣菜には、主婦の手抜きというマイナスのイメージがつきまとっていました。そのために、ロック・フィールドで働く社員の人たちも誇りをもてない。これが社長の岩田弘三氏の悩みでした。そのようなある日、岩田氏は、自社の女性社員から次のような話を聞いたといいます。
この女性社員は、子供の頃、母親が惣菜を買って帰ってくる日が楽しみだったというのです。母親は外で働いていました。いつもは夕方に仕事から帰ってくると、大急ぎで台所で料理を始めます。しかし惣菜を買ってきた日は違ったというのです。
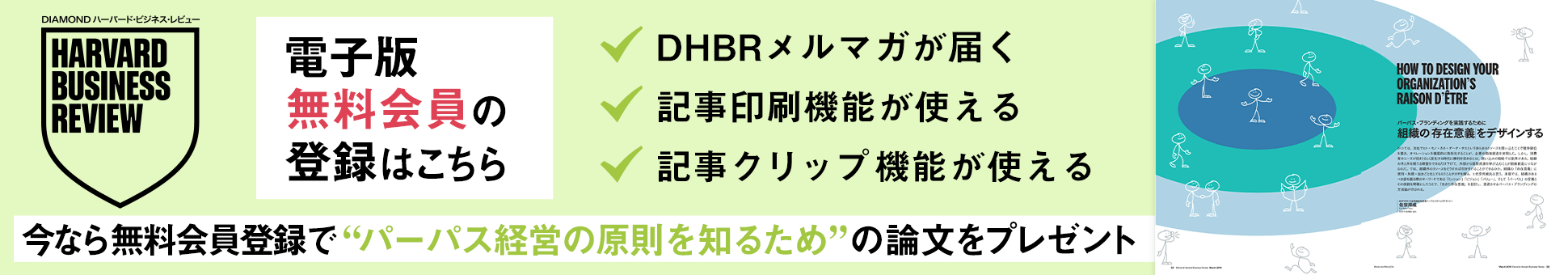




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









