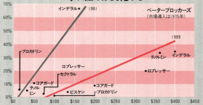-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ストーリーの大幅な書き換えにまで踏み込む戦略転換が相対的にやりやすくなるもう一つの条件は、あからさまに業績が低迷しているということ。「ひところと比べてだいぶ業績が落ち込んできたな。そのうち何とかしなければ……」というような「普通の業績悪化」では不十分で、「もうこのままではやっていけない。近い将来確実にアウト、ゲームオーバー、会社がなくなる!」という危機感が上から下まで肌感覚で共有されるほど行き詰っている。こうした「にっちもさっちもどうにもこうにもブルドッグ状態」(←意味不明な方はスルーよろしく)になれば、戦略転換が強制される。
前回話したように、『プラダを着た悪魔』の主人公、アン・ハサウェイの演じるジャーナリストの卵のリポジショニングは、戦略転換というよりも実際は戦略がまだ定まっていない状態での試行錯誤だった。しかも、それは「個人の物語」である。これに対して『フラガール』が描いているのは、企業変革に取り組む「組織の物語」になっている。『プラダを着た悪魔』と『フラガール』の対比で言えば、戦略転換の事例としてリアリティと迫力があるのは後者のほうだ。
『フラガール』が描く戦略転換は、あからさまな業績低迷による行き詰まりが変革を促したという典型例だ。炭鉱業がいずれ行き詰るのは誰の目にも見えていた。1962年に日本は原油輸入自由化に踏み切り、これが炭鉱業の斜陽化を決定的にした。映画のモデルになった炭鉱会社、常磐興産が、新規事業として観光業を始めるべく、運営子会社の常磐湯元温泉観光株式会社を設立したのが1964年。「常磐ハワイアンセンター」(現在の「スパリゾートハワイアンズ」)のオープンが1966年である。
興味深いのは、常磐興産が変革のためのアクションを次々に打った60年代半ばよりもずっと前から、炭鉱業は慢性的な不振だったということだ。事実、常磐興産は、観光業の操業開始に先行すること11年の1955年には早くも従業員のリストラ(整理解雇)に手をつけている。新規事業の意思決定をし、リソースを投入する時点では、経営者だけでなく、従業員やその家族にまで、「座して死を待つ」でいいのか、何とかしなければ、という意識が行き渡っていたと考えられる。逆に言えば、それだけ時間をかけて徹底的に行き詰らなければ、炭鉱業から観光業へという戦略転換はできなかったということだ。
大胆な企業変革に成功した企業の事例を見ると、程度の差こそあれ、変革に先行してわりと深刻な業績低迷のフェーズを経験しているという点で共通している。1999年にカルロス・ゴーン社長が登板して以来、日産が「日産リバイバルプラン」の実行で大胆な変革に成功したのは周知のとおりだが、それ以前の同社は、2兆円の有利子負債を抱え、国内シェアが12%まで落ち込むという明らかな経営危機状態にあった。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)