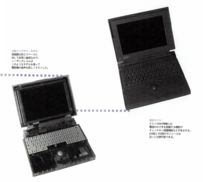前者からは、厳密という言葉について興味深い定義が見えてくる。それは数字上・統計上の観点から見た厳密さだ。しかしその「厳密さ」を手に入れるために、私たちが何を諦める必要があるか考えてみよう。つまり、回答者の言葉ではなく、企業側の言葉が使われなければならいのだ。
たとえば「購入を決めるにあたって、徹底したアフターサービスという評判はどの程度重要ですか。1から5までの数字で示してください」という質問があったとする。調査ツールを設計する人は、「評判」「徹底した」「サービス」「購入を決める」という言葉が何を意味するかわかっている。「1から5まで」の意味もわかっている。そして、サンプル顧客に協力してもらい、この調査ツールを事前に厳密にテストすれば、典型的な回答者がこれらの言葉をどのように解釈するかもわかる。
しかし私たちは、この質問に実際に回答する人がどう解釈するかを知ることはできない。回答者が購入の意思決定についてまったく別の解釈をしたとしても、わからないのだ。たとえ別の解釈がなされたとしても、その回答は採用され、他の回答と合計され、厳密な定量分析が行われる――まるで、すべての回答者が同じ解釈をしたかのように。顧客を「厳密に理解する」ために、企業は顧客との非常に浅い関係を受け入れなければならない。言い換えると、「厳密」であろうとすることによって本当にたくさんのものを諦めなければならないのだ。
定性的な分析、特に観察調査やエスノグラフィー調査(対象者の生活の場に入り込んで、観察やインタビューを行う調査)を行えば、企業とその製品・サービスと顧客の関係をもっと深く掘り下げて調査することができる。こうした調査では、全部の回答を足し合わせて「厳密な定量分析」を行うことが焦点ではないので、顧客は自分の声や言葉や語彙を用いることができる。また、顧客は製品やサービス、その提供企業に対する気持ちを口頭でうまく表現できない場合が多いが、企業は顧客が「こうする」と言う(本当はしないかもしれない)言葉を聞くのではなく、実際に何を行うかを見ることができる。これらすべてにより、顧客に関するより詳細な姿が見えてくるのだ。
しかし、これらの調査には企業側の定性的な判断が反映される。顧客との関係の質と深さは、解釈する企業側の目や耳の質に左右されるのだ。それでも、定性調査には努力次第で顧客を深く理解できるチャンスがある。定量調査にはそのチャンスがまったくない。定量調査では顧客が考えていることや必要なもの、欲しいものを尋ねるのに対し、定性調査ではじっくりと考えて解釈を行うことが仕事となる。
もちろん、定性調査があらゆる面で定量調査に勝っているというわけではない。定性調査に絶えず存在する危険は、調査対象者が顧客全体を代表するものではないということだ。その原因は主に、調査が多くの時間を必要とするためサンプル数が非常に少なくなってしまうからだ。加えて、定量調査は経験豊かな業者に外注される場合が多いのに対し、定性調査では重要な幹部の時間を使うことになる可能性が高い。
しかしそうであっても、顧客と深い関係を築きたいのであれば、定量的な調査ツールを通じた顧客との対話に時間を費やすべきではない。
HBR.ORG原文:The Secret to Meaningful Customer Relationships March 24, 2010






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)