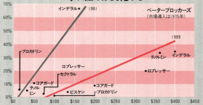-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
医者に依存しきった患者、疲弊する医療現場……医療システムの悪循環が誰の目にも明らかになっている。「社会システム・デザイン」の考え方を用いて、医療システムの良循環を描き、「サブシステム」ごとに行動ステップを具体化していく。元マッキンゼー東京支社長であり、現在、東大エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(EMP)で次世代リーダーを育成している横山禎徳氏の好評連載、第6回。
今回はこれまで述べてきたステップをすべて具体的に示す例として、「医療システム・デザイン」を取り上げてみる。
高齢化社会で明るみに出た、医療システムの「隠れた問題」
日本の医療における中核課題は、患者、医者、保険者の三者に間にやり取りを通じて自己規律が醸成されるようになっていないことだと思う。
医療はジュースを飲むようにはいかない。ジュースはうまいかどうか、高いか安いか価値判断はすぐできるが、医療の場合、どの治療がいいのかは素人には判断できない。治療費も健康保険が大半を払ってくれるため、実際にいくらかかっているのかの実感が持てないまま、治療というサービスを濫用する可能性がある。そこに患者としての自己規律が働いていない。
医者は自分の医療行為に関してはプロフェショナルとしての自己規律は働いているが、それがどの程度の価値があり、その対価はいくらかを考える必要はない。後で医療関係の訴訟になった時、なぜ十分な治療をしなかったのかを問われないよう、また、医師の良心としてできる限りの治療をしたいが、費用をコントロールするという自己規律は働かない。健保組合などの保険者は医療機関から支払請求が症例に対して妥当な治療かどうかの判断はせず、法律上の過誤がない限り、決められた保険点数に応じて支払う。
このように患者、医者、保険者の三者間に医療サービス提供に対して、価格の妥当性を判断し、対価を支払う形のやり取りではないため、それぞれの自己規律を醸成するようになっていない。
国民皆保険制度が発足した1961年当時はほとんどの病気が肺病も含めて感染症であり、抗生物質の発達のおかげで大半は比較的短期間に治る病気であったので、この自己規律の問題はあまり顕在化しなかった。しかし、高齢化によって「生活習慣病」という、がん、高血圧、糖尿病、心臓病などの慢性病、複合病が中心になると隠れていた問題が露呈し始めたのである。その意味で「医療システム・デザイン」は「高齢化社会をどう経営するか」というより大きな課題と一体で捉えるべきである。
慢性病ではそう簡単に死ななくなったが、かといって、完治することはない。常にモニターし、必要な治療をしないといけない。多くの難病は遺伝病が多く、決定的な治療法も確立していないまま治療を続けないといけない。国民皆保険制度が発足した時には全く想定していなかった新たな状況でいくつかの「悪循環」がめぐり始めている。
医師の処置にミスがあった場合、なぜそうなったのかの原因を詳しく知りたい、心から謝ってほしいと患者なり家族が思い、裁判に訴えてみるが、求めた満足を得ることができず、よりいっそう司法に頼るという司法が絡む「悪循環」がある。
高齢者医療を支えるため現役世代の保険料負担を増やせば増やすほど、十分払い込んだという思いから引退後の濫用が30年近く続くため、健康保険制度の収支改善につながらないという保険者が絡む「悪循環」もある。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)