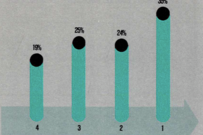-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「ハーバード生活で最も印象に残った」「他のクラスと違って人間味に溢れていた」「卒業後の進路を考え直すきっかけとなった」……。ハーバード・ビジネススクールでいま1番熱いヤンミ・ムン教授のマーケティングの授業。そのエッセンスを1冊に凝縮したのが『ビジネスで一番、大切なこと』である。本誌9月号特集「顧客を読むマーケティング」にちなみ、を5回にわたって無料で公開する。
はじめに
上の息子は小学2年生になると、毎週のように詩の宿題を持って帰るようになった。私たちは、毎晩一節を繰り返し暗唱し、小さくて柔らかい脳に刻み込んだ。
しばらくすると、私はこの頭の体操の目的について考えるようになった。ここ10年ほどハーバード・ビジネススクールでマーケティングを教えており、学生たちをフレームワークやベストプラクティスといったビジネス文法漬けにして特殊な言語をマスターさせようとしている。
しかし、教師としての実感からいえば、暗唱は能力を高める一方、ある種の惰性をもたらす。多くの教育者が批判するように、頭を使わなくなるのだ。1度覚え込むと、それ以上学ぼうとしなくなる。これが今、ビジネスの世界で起きている現象だ。
ビジネスパーソンは特定の行動様式やスキルに磨きをかけすぎていて、機械が寸分違わぬ製品を延々送り出すかのような不気味な状態に陥っている。本来の目的は、あなたや私のようなごく普通の人々にとって、有意義で魅力的な商品を作ることだったはずなのだが。
私は研究者であると同時に、一市民であり妻であり母でもある。私の日常は、おそらくあなたと変わらない。シャンプーやジュース、スニーカーを買いに出かけると、選択肢のあまりの多さに目まいがする。ほんの一昔前までは、片手で収まる程度だった。宣伝も、これでもかと言わんばかり。マーケティング言語を流暢に操ることは、明らかに誇張力を磨くことだ。どれもが「新しく」「改善」されていて、「これが1番」だと叫んでいる。
しかし、折からの不景気で風向きは変わった。住宅市場が破綻し、金融市場が麻痺したとき、私は高級住宅街に住んでいなかったのをありがたいとさえ感じた。以前は憧れていたはずなのに。経済的に安定している人々でさえ、消費パターンを見直しているという新聞記事もある。
理想の生活や所有に対する考え方は、一夜にして変わった。「過剰」は追い出され、住まいやクローゼットを満たすモノを慎重に吟味するようになっている。「豊かな時代は終わった。豊かでなくなったからではなく、豊かさが私たちの憧れの的としての地位を失ったからだ」。そう感じたのを覚えている。
マーケターたるもの、消費者が望むものはもちろん、望まないものにも注意を払い、欲望の特質を把握しなければならないはずだが、その感受性は鈍ったままだ。消費者としての私たちは、豊かさに心動かされる段階をとうに過ぎている。たいして違いのない大量の選択肢や、戸惑うほど多くの機能にうんざりしている。ところが店に足を踏み入れれば、企業がいまだにこのことを理解していないのは一目瞭然だ。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)