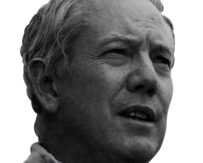-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
好評をいただいた山形氏の連載も、ついに今回が最終回です。ある説によると、人類の進化と集合知は切っても切り離せないといいます。「賢いほうが生存に有利だ」と言われるのに、なぜ世の中は天才だらけになっていないのでしょうか。その理由も集合知にあるかもしれないのです。
十分な目玉とツイッターのタコツボ:ソーシャルの2つの意味
前回の最後で、「十分な目玉」の話をした。集合知が機能するには、ある程度の数の人が情報の生産や改善に関わる必要がある。そしてジャーナリズムの例を引いて、十分な目玉というのは必ずしも人数だけのことではないという話もした。既存の情報を反復するだけの人がいくら増えても、それは目玉が増えたことにはならない。
そしてこれは、集合知に伴う難題の1つではある。集合が本当に「集合」になり、徒党にならないためにはどうすればいいのか?
こうした問題が露骨にあらわれる典型例は、ツイッターだ。ツイッターにはいろいろな人の意見が流れる。ソーシャルメディアによるジャーナリズムという主張は、それが集合知的な情報集約装置となりうるという希望からきたものだった。
だが……もちろんだれもツイッターに流れる無数のツイートをすべて見ているわけではない。自分のタイムラインには、自分が選んだフォロワーたちのツイートが流れる。そして、多くの人は、自分の仲間や自分と似たような関心=意見の人たちをフォローする。すると結果として、ツイッターのタイムラインは自分の鏡になってしまう。
もちろん仲間内のおしゃべりツールとしてツイッターを使うなら、これはまったく問題にならない。だが多くの人は、自分がたくさんの人をフォローしているから、それが社会全体のある程度の縮図となっていると思いがちだ。だが実はそこには自分の気に入る情報、自分が賛成する意見ばかりが選択的に登場しているだけだ。ソーシャルメディアの「ソーシャル」は、社会全体という意味もあれば、「社交」という意味もある。もともとは、それは後者の意味が強かったのに、それが一部の事例で政治的な動員ツールとしてうまく使われたこともあって、前者の社会という意味だと思い込む人が増えてきた。でも実際、ソーシャルメディアは、相変わらず社交メディアなのだ。
ある自治体首長選挙では、現職有利との報道に対し、特定の政策を支持する人々が対立候補を支持するツイートを大量に発していた。そしてこれだけ拡散したし、ツイートも盛り上がっているからいけるはずだ、と投票日には大騒ぎになった……が、結果は報道通り現職の圧勝。ツイッターの住民は、自分たちの仲間の中で盛り上がっていただけだった。それは世間とは隔絶した、自分たちのタコツボにすぎなかった。世の「炎上」と称する代物もほとんどこの結果だ。でも、ミクロな個人が自律的に選択し合い情報の選り分けを行う時――集合知の基本的な発想だ――には、そのタコツボがタコツボであることさえ認識できない。それをやるためには、多くの人が自分の関心から一歩下がり、それを否定する見解、馬鹿にする見解、無視する見解などもきちんと見ることが必要になるが、敢えてそんな面倒をしたがる人はほとんどいない。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)