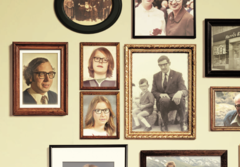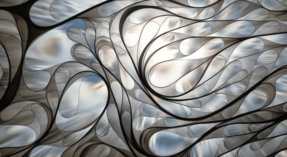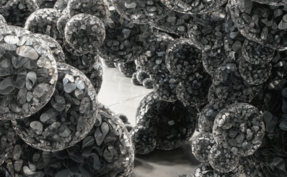-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
そもそも持続可能な競争優位は存在するのだろうか。アンソフ、チャンドラーからポーター、ミンツバーグまで、競争優位に関する理論は20世紀に進歩してきた。しかしながらほとんどの企業で、せっかく築いた競争優位も一時的なものに留まっている。これは多くの場合、事業や環境変化の予測困難性、不確実性がもたらす意思決定の問題(認知バイアス)、あるいは組織自体の適応力不足(経営劣化)に起因している。ただ、競争優位を持続している企業は存在している。ゼネラル・エレクトリック(GE)は、ダウ・ジョーンズ工業指数のリストに1896年に組み入れられて以来、9回の景気衰退期と大恐慌を乗り越えて、業績を上げ続けた唯一の企業であり、時代ごとに経営戦略の新しいスタイルを提案してきた企業でもある。GEは基本理念として3つのコア・バリューを掲げているが、就任したCEOは時代に応じたGEバリューを示してきた。ウェルチの掲げたGEバリュー、イメルトが強化したGEグロース・バリューを通して、持続可能な競争優位を実現するために何をすべきかを考える。
持続可能な競争優位は存在するか
ビジネスの成功は、非連続ともいえる絶え間ない環境変化に対して競争優位を持続させる能力にかかっている。しかし、ハイ・ベロシティと呼ばれる現代では、製品、サービス、人材、スキルそしてアイデアが比較的自由に国境を超えて動くグローバリゼーションがあり、技術革新、消費者ニーズ、事業機会は絶え間なく、しかも急速に変化する。
一方、製品設計や製造のアウトソーシング、中間財市場の発達、情報通信や交通インフラの普及によって比較的参入容易な事業環境が出現し、競争優位を永続的に持続することが難しい、といわれる。かつて企業経営が直面していた環境変化の状況をH. イゴール・アンソフは「乱気流渦巻く時代」、ピーター F. ドラッカーは「非連続な(断絶の)時代」と表現したが、現代の企業は、かつてない予測困難な状況に直面している。