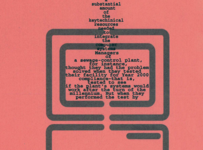――とはいえ、人によっては他にも寄付をしたい団体があるでしょうし、一個人の生活の中で寄付できる金額は限られています。コペルニクの競合となるのはどこでしょうか? どのようにドナーをモチベートし、サービスを差別化しているのでしょうか。
幸いにも競合するほどビジネスモデルが類似している企業はないようです。そもそも同じ寄付だからといって、ユニセフや赤十字は仕組みから活動からあまりに異なりますし、グローバルギビング(Global Giving)やキバ(Kiva)といったこの世界の大先輩にしても、途上国にテクノロジーを届けるといった具体的なプロジェクトに対して個人から寄付を集めることに特化している例はほとんど多くありません。
ドナーのモチベーションについては、今でもいろいろ苦労しています。常に強く意識しているのは、「誰に何が届いているか」を分かりやすくドナーに伝えるということです。我々は、ドナーのみなさまから大切なお金を預かるわけですから、「このテクノロジーがあれば、子供たちがこんなに生活が楽になります」といったことを分かりやすく伝えなければなりません。
たとえばソーラーライトは1個から寄付をすることができます。そして届いた後、実際に使用しているユーザーの姿を見ることができれば、強い一体感を感じることができます。つまり、ウェブサイト上で一対一の関連性をつくることに集中しているのです。ですから、単に事実を伝えるだけでなく、できる限り感情に訴える、エモーショナルなコミュニケーションが求められます。
また、財務状況を含む活動報告をウェブサイト上で公開し、透明性も確保しています。日本ではあまり重要視されていませんが、アメリカではNGOやNPOを評価する第三者機関があり、その格付けがオープンにされています。彼らの評価は、ドナーが我々の価値を判断する際の重要な指標となるので、我々も気を付けています。
シリコンバレーのスタートアップ同様、なかなか厳しい世界です。5年前の立ち上げ当初に情報交換をしていたNPO仲間のうち、いまも当時の組織のままで残っているのは20分の1ですから。
ユーザーにテクノロジーを届け、企業にマーケット情報を届ける
――企業のBOP市場進出のコンサルティングもされているそうですね。やはりCSR(起業の社会的責任)部門がメインでしょうか。
日本企業の場合、最初はCSR部門が中心でしたが、現在は事業部門とのお付き合いが半数を占めています。我々はインドネシアという、偶然にも現在、新興市場として注目されている国にいることもあって、たとえばBOPビジネス向け新製品を開発するR&D部門のお手伝いをすることもあります。欧米のグローバル企業の場合は、最初から事業部門とのお付き合いが多いですね。





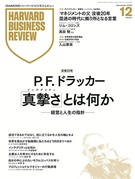
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)