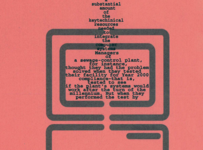いま世界中のグローバル企業が、貧困層を視野に入れた途上国の新興市場開拓に躍起となっています。そのためには、今までとはまったく異なるものづくり、そしてビジネスを展開していかなければなりません。そこで我々は、そもそもどんなニーズがあるのかをアドバイスしたり、プロトタイプを実際に現地に持ち込んでテストしたり、といったコンサルティングを提供しています。
こうしたことが可能になったのは、テクノロジーをユーザーに届ける流通チャネルを開拓していく過程で、現地のさまざまな法人や団体の間で信頼できる関係を構築できたからです。いまでは、テクノロジーの特徴さえ分かれば、「これなら漁村がいいな」「中所得者層が多いところがいいかもしれないな、だとしたらあの村だな」といったアタリをつけ、手伝ってくれそうなパートナーを見つけて、すぐに市場テストを提案することができるまでになりました。
テクノロジーを届ける(ディストリビューション)ということと、テクノロジーを持つ企業へのコンサルティングは、コペルニクのシナジーを生み出す両輪です。クライアント企業の開発者と一緒に現地を訪問し、肌感覚でいろんなことを感じていただく機会も増えています。
――信頼関係をつくるのは、一朝一夕にはいきませんよね。いろいろご苦労もあったのでは?
立ち上げ当初は、私が国連に在籍していた頃に一緒にプロジェクトを行っていた組織や人々に声をかけていきましたが、徐々に自分たちで開拓し、相手先を増やしていきました。重要なのは、それぞれの組織や人の専門性をつかんでおくことです。たとえば60もの拠点を持つ組織などは、広範囲にものを届ける時に効果的です。あるいはエネルギー専門で取り組んでいる人は、たとえばソーラーライトを持っていけばすぐに理解してくれそうだと予測できます。
苦労といえば……そうですね、輸送費を騙し取られたかな? と思うようなことはありました。とある港から村へプロダクトを運ぶ際に「500ドル足りない」という連絡が輸送会社から我々に入りました。急ぎ現地のスタッフに手渡しさせようとしたところ、「口座を指定するので振り込んでほしい」と言われました。諸般の事情で仕方なしにその口座に振り込んで連絡をすると、「まだ振り込まれていない」と。銀行から証明を取っているんですけどね。それでも振り込まれていないの一点張り。何度かやりとりをした挙げ句、このままではプロジェクトが前に進まないと判断し、現地のスタッフに今度は直接500ドルを手渡しさせて幕引きとなりました。その後、輸送は問題なく行われたのですが……。いまだに消えた500ドルは謎のままです。
(つづく)
*後編は、3月27日に公開します。
*中村俊裕さん緊急帰国!『世界を巻き込む。』 刊行記念無料セミナーが3月31日にダイヤモンド社にて開催されます。詳細はこちらから。
米国において501(c)(3)として承認された非営利組織。日本では、「一般社団法人コペルニク・ジャパン」として登録。インドネシアでも法人登録している。
途上国の人々の「生活の向上」と「自立」を目指し、革新的なテクノロジーを現地の人々へ届けている。
【書籍のご案内】
世界を巻き込む。
誰も思いつかなかった「しくみ」で問題を解決するコペルニクの挑戦
今、全世界から注目を集めているNPOがある。その名は「コペルニク」。 アジア、アフリカの援助すら届かない最貧層(=ラストマイル)へ、現地のニーズに即したシンプルなテクノロジーを届ているグローバルNPOだ。創設者である中村俊裕氏が、国連を辞めてまで起業した経緯から世界的なしくみづくりまでを初めて語る。
46判並製、264頁、定価(本体1500円+税)
ご購入はこちら
[Amazon.co.jp] [紀伊國屋書店BookWeb] [楽天ブックス]
【目次】
はじめに 必要な場所に、必要なものを。
──シンプルなテクノロジーで、世界を変える
第1章 僕が世界の最果てを「現場」とした理由
──24億人以上が抱える問題から目をそむけない
1 「ラストマイル」で生活をするということ
2 シンプルなテクノロジーが、世界を変える
第2章 国連でできたこと、国連ではできなかったこと
──なぜ、ボトムアップが課題解決への近道なのか?
1 スケールの大きな仕事がしたい──憧れの国連
2 ボトムから変えていく、ということ
3 シエラレオネで出会った「ラジオ」のパワー
第3章 いま求められているのは、クリエイティブな「ローテク」
──途上国のニーズをつかむための6つの課題と3つのアプローチ
1 ブルー・オーシャンはどこにあるのか
──ニーズを正しく把握しているか?
2 シンプルなテクノロジーが革新的な理由
──ロースペックだからこそできることとは
3 テクノロジーは、何のためにあるのか?
──インパクトという視点
第4章 憧れの国連を辞めるとき
──技術と現場とお金をつなぐ、三方よしのビジネスモデルで起業するまで
1 コペルニク創業──すべてをつなぐ「しくみ」はどのように生まれたのか?
2 コペルニクのしくみ──顧客、企業や大学、寄付者がみんなハッピーに
3 寄付とファンディングについて
第5章 危機を救ってくれたヒントはすべて「現場」にあった
──企業とNPOのコラボレーションが、新たなイノベーションを起こす
1 進化するコペルニク──なぜ僕はNPOの経営に力を入れるのか?
2 イノベーションの担い手は、企業だけなのか?
3 異分野の交流から、グローバル人材が生まれる
4 「つなぐ」ことこそ僕らの役目──シードコンテストを通じて得た手ごたえ
第6章 日本の「モノづくり」を、世界は待っている
──ボトムアップのアイデアを課題解決と製品づくりに活かす
1 東北にソーラーライトを!──被災地で求められたコペルニク
2 日本企業とコペルニクのパートナーシップ──現地ニーズに根差した製品・サービスを
3 コペルニクが描く未来──ボトムから世界を変えていく





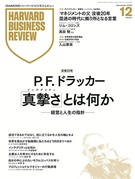
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)