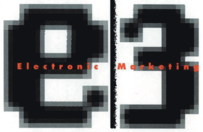実験の文化
このようなテストの利点として最も明白なのは、商品の改良と収益増加への貢献である。だが間接的なメリットもある。それは、テストが企業文化に深く根付いた時に現れるものだ。
第一に、実験の文化が確立されれば“HiPPO”の弊害がなくなる(Highest Paid Person's Opinion:「一番給料の高い人の意見」の頭字語)。A/Bテストは、誰の直感にも頼ることなく、予断のない決定を行う確実な方法だ。シャッターストックでは、会議でアイデアを持っている上級幹部に返される言葉は、「ではテストしてみましょう」である。
第二に、アイデアがホワイトボードの上で抹殺されたり、プレゼンテーションで却下されたりする代わりに、テストという形で日の目を見ることが多くなる。アイデアを試しやすい環境ならば、チームメンバーもまだ起こっていないことについて抽象的なことを言うのではなく、結果や次のステップについて話すことができる。そして最後に、社員の意欲が断然高まる。自分の考えが実際に運用されるのを、生で見ることができるからだ。
もちろんいいことづくしではなく、実験の文化にもいくつかの欠点がある。その1つは、次の大きなイノベーションを逃す場合があることだ。これは、テストですぐによい結果が出るような漸進的な改善を常に行っていることに起因する。ものによっては、短期的にはマイナスの結果が出ても、長期的にはプラスの結果に転じるものもある。前述したように、変化に対するユーザーの反発があるからだ。また別の欠点として、テスト戦略は難易度が高く、組織を新たな方向に動かすための戦略的思考が不足しがちとなる。
下図に示す「ブランド」対「最適化」の線上にあなたの組織が持つ実験の文化について現状と目標を位置づけることができる。「ブランド」側は、ビジュアルに関する厳密なガイドライン、オフラインとオンラインのマーケティングの整合性、エクスペリエンスの一貫性を特徴とする。一方「最適化」側は、何でもありだ。ロゴやヘッダーをテストし、どんな色やコピーでも試し、直感に頼ることはなく、コンバージョンが向上するならば商品が一貫性を欠くことにもやぶさかではない。あなたの企業の文化は、この軸のどこかに分類されるはずだ。
シャッターストックでは商品担当チームとマーケティングチームが、それぞれに好きな企業を軸上に配置するエクササイズを行った。そのうえで自社が現在どこに位置し、今後どこを目指すべきかを議論した。結論に至ったのは、「最適化」の最右端から非常に遠い場所だった。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)